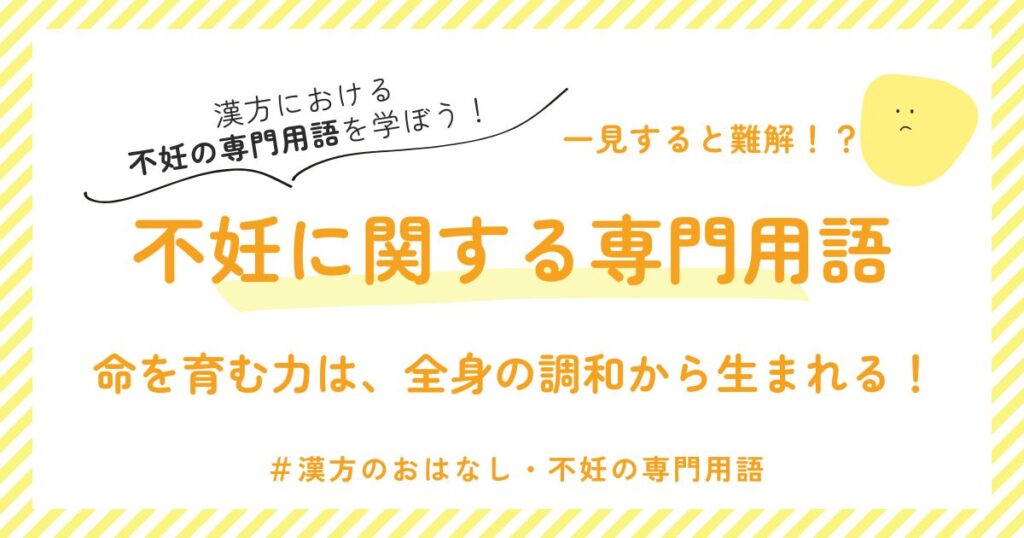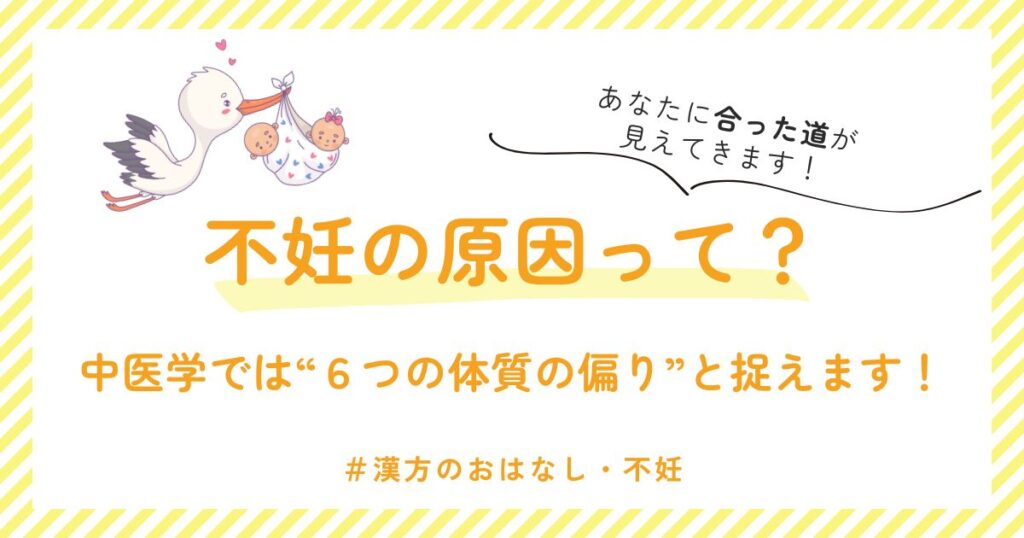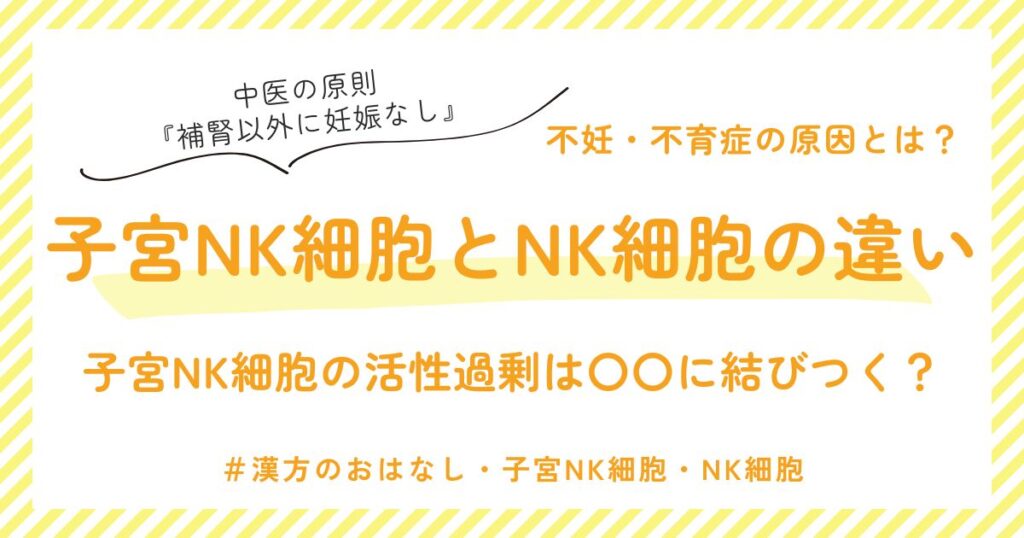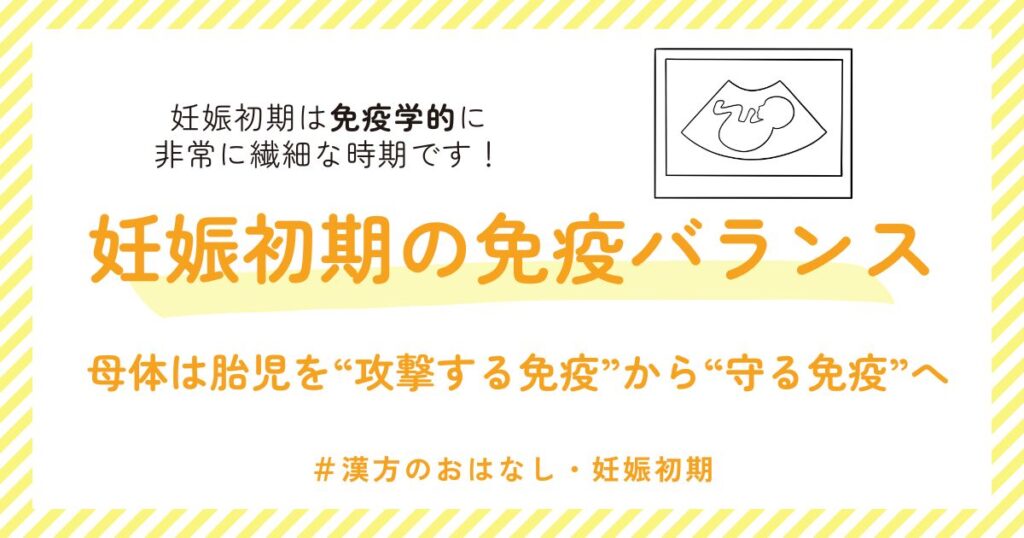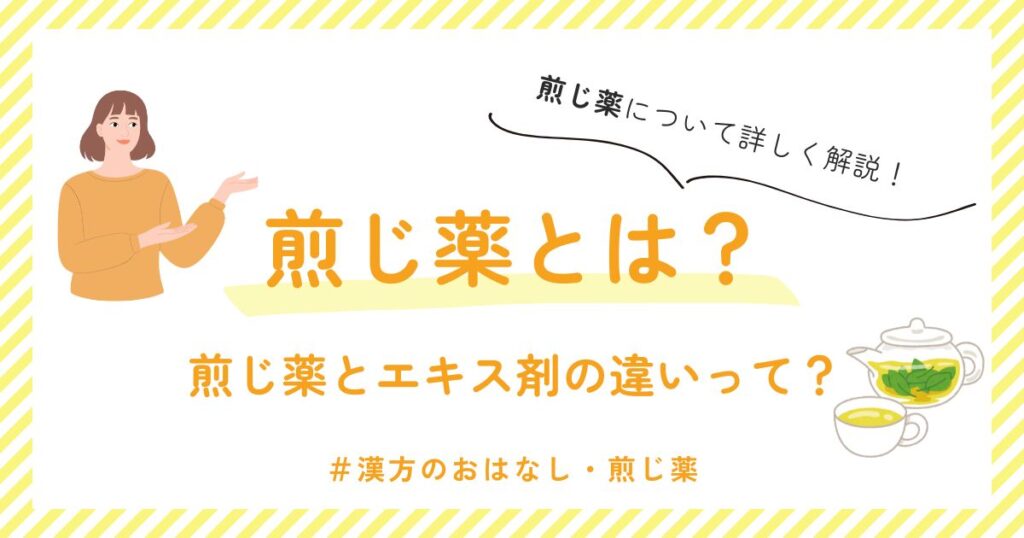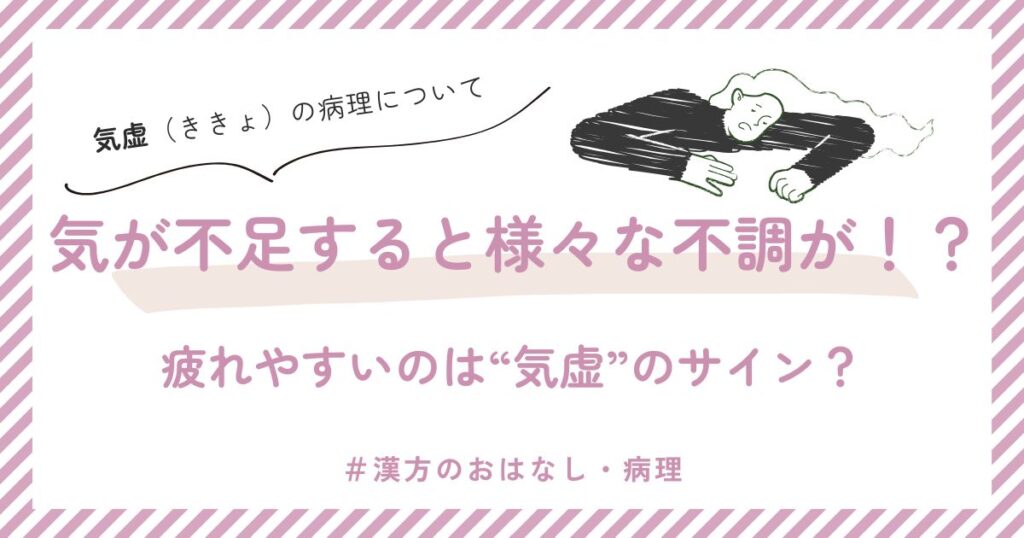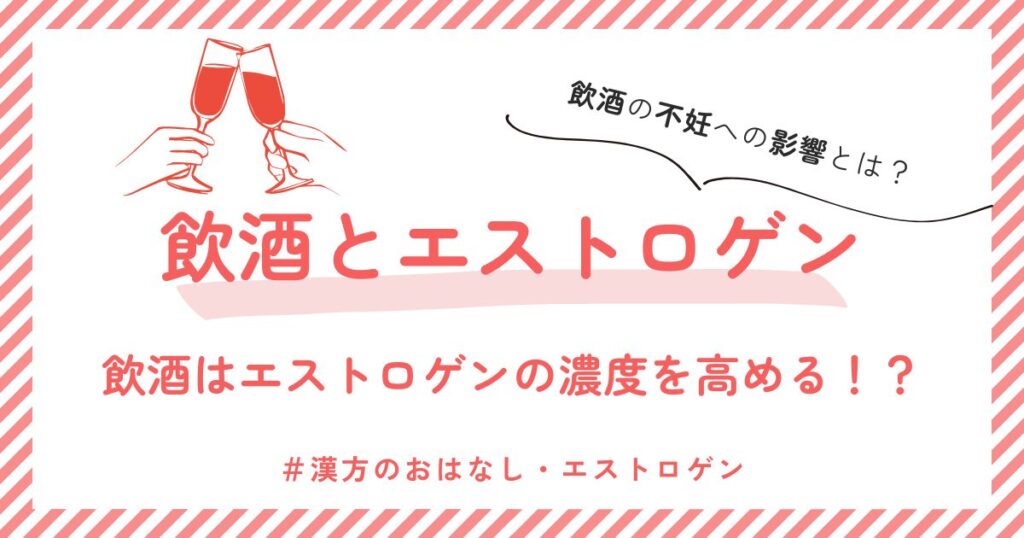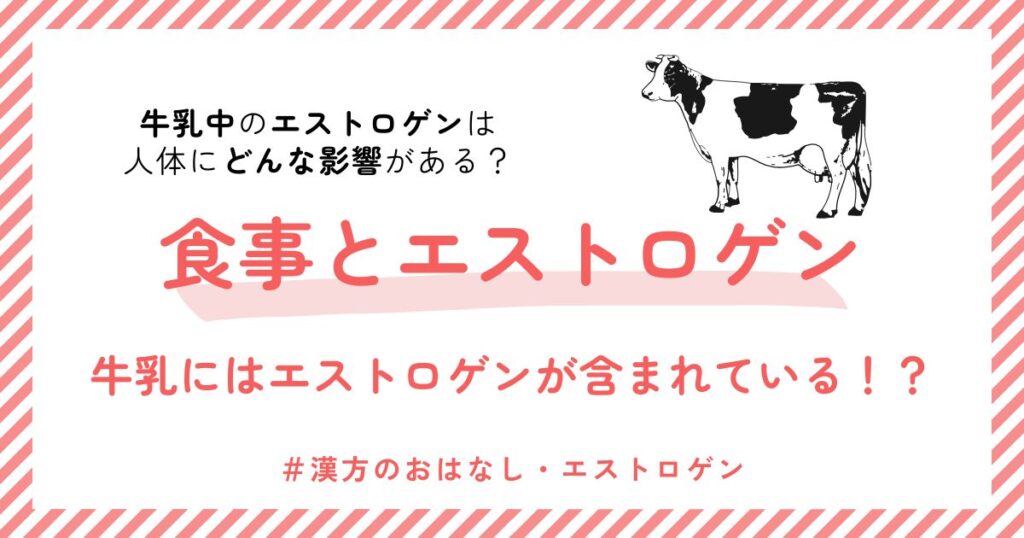身体の不調– tag –
-

妊娠と免疫
妊娠は、単なる受精と着床の結果ではなく、母体の免疫系が胎児を受け入れ、育てる準備を整えるプロセスです。その鍵を握るのが「サイトカイン」と呼ばれる免疫細胞のメ... -

不妊に関する専門用語を理解する
「不妊」という言葉に向き合うとき、私たちは単なる医学的現象ではなく、 心と体の繊細なバランスに触れることになります。 漢方では、このバランスを「気・血・水」や... -

妊娠を望む気持ちは、誰にも代われないほど大切なもの
中医学では、不妊の原因を「6つの体質の偏り」として捉えます。 これは、あなたの体がどんなサポートを求めているかを知るヒント。 6つのタイプは、どれが良い悪いで... -

子宮NK細胞とNK細胞の違い
NK細胞(Natural Killer cell)と子宮NK細胞(uterine NK cell)は名前こそ似ていますが、 由来・局在・機能・サイトカイン分泌パターンが大きく異なります。 子宮NK細... -

妊娠初期の免疫バランス
🔑Keyword 免疫寛容 IL-10・TGFβ ホルモン P4:プロゲステロン・hCヒト絨毛性ゴナドトロピン 免疫細胞 Th1・Th2・TH17・Treg 妊娠初期は、母体にとって**「... -

煎じ薬とは?
漢方薬の伝統的な服用方法で、乾燥した生薬を水で煮出して服用する薬。 「煎じる」とは、薬効成分を抽出するために弱火でじっくり煮ること。 古代中国から続く医療文化... -

気虚(ききょ)の病理
1. 気虚とは? 「気虚」 とは、中医学において 気(生命エネルギー)の不足 により、臓腑の機能が低下し、全身の活力が失われる状態を指します。気は**「推動・温煦・防... -

飲酒とエストロゲン
1.飲酒はエストロゲンの濃度を高める アルコールは肝臓で代謝され分解されます。また、体内で作られたエストロゲンも 肝臓で処理されます。飲酒により、肝臓はアルコ... -

食事とエストロゲン
1.食物中にもエストロゲンがある さまざまな食物にもエストロゲンが含まれています。例えば、肉や牛乳、 あるいは大豆製品である豆腐、納豆、みそなどです。このほか... -

食欲とエストロゲン
1.エストロゲンは食欲を低下させる エストロゲンには食欲を抑える作用があり、エストロゲン分泌が高まる発情期には 食欲が落ち、ヒトでも排卵期にはカロリー摂取量が...