「異病同治」の考え方は面白いですよね!
同じ原因や病理を持つ異なる病気に対して、同じ処方が効果を発揮するという
中医学の特徴的なアプローチです。
では、「小柴胡湯(しょうさいことう)」についてお話し致します。
目次
小柴胡湯(しょうさいことう)
主な適応症
- 肝炎、肝機能障害
- 胆嚢炎、胆石症
- 風邪の後の長引く咳
- 自律神経失調症
- 更年期障害
- 胃炎、消化不良
- 生理不順、月経困難症
用いる根拠
小柴胡湯は「少陽病」に対応します。少陽病は、病気が半表半裏にある状態を指し、熱が内部にこもっているが、外にも出ていない中間的な状態です。したがって、寒熱が入り混じり、体力が低下しているときに使われます。
方剤の方意
- 和解少陽:少陽病の寒熱を調整する。
- 調和肝脾:肝(気)と脾(消化吸収)のバランスを取る。
- 扶正祛邪:正気を強化し、邪気を取り除く。
各生薬の配合目的
- 柴胡(さいこ):少陽の主薬。熱を取り、肝気を調整する。
- 黄芩(おうごん):清熱燥湿。熱を冷まし、湿を取り除く。
- 半夏(はんげ):理気化痰。気を巡らせ、痰を取り除く。
- 生姜(しょうきょう):温中止嘔。胃腸を温め、吐き気を抑える。
- 大棗(たいそう):補中益気。脾胃を補い、気を巡らせる。
- 人参(にんじん):補気健脾。気を補い、脾胃を強くする。
甘草(かんぞう):調和諸薬。薬全体の調和を取る
まとめ
小柴胡湯は少陽病という半表半裏の状態を調整し
身体のバランスを整えることで、さまざまな病気に応用できます。
例えば
肝炎や胃炎などは根本的に「気の停滞」や「熱のこもり」が原因であることが多く
小柴胡湯を使うことでこれを解消します。
ご相談お待ちしています。

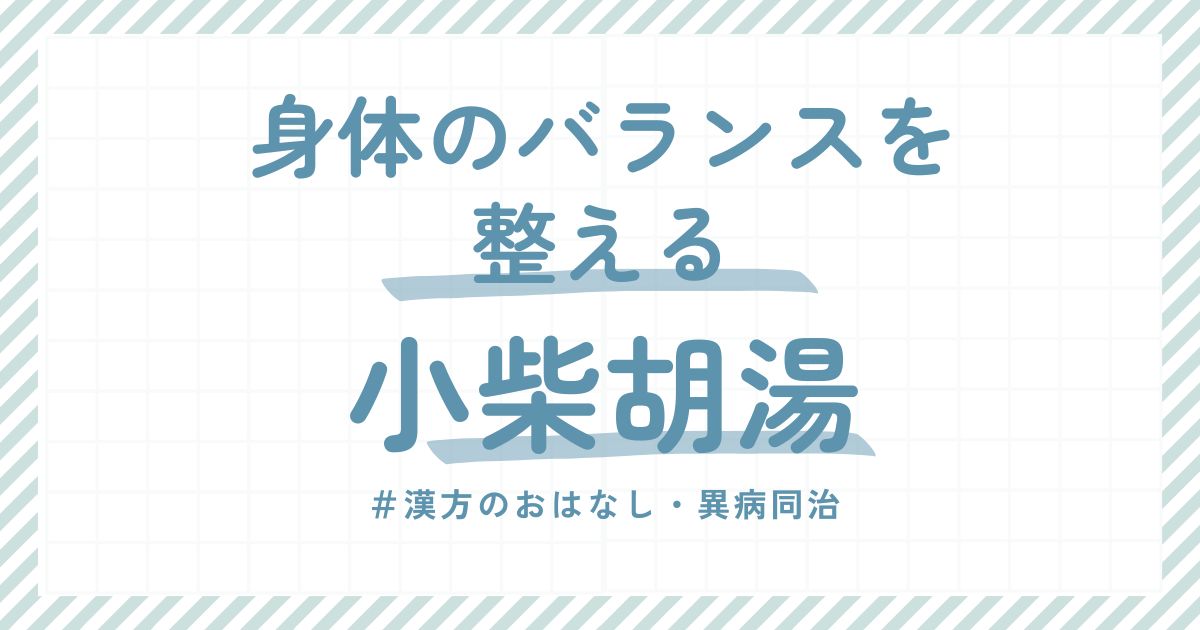
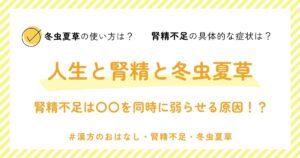
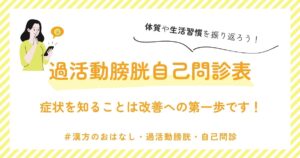
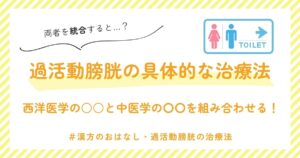
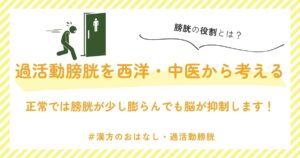
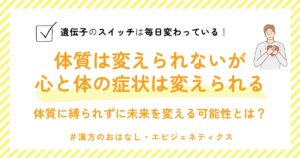
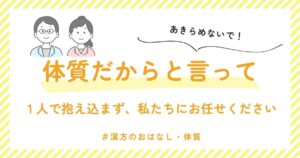
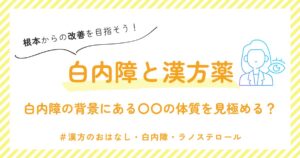
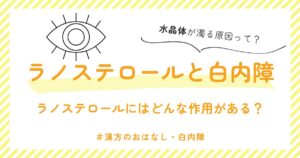
コメント