独活寄生丸を用いる疾病
慢性の関節痛・筋骨の衰え・血虚・肝腎不足に関連する症状 に広く用いる。
代表的な適応疾患は以下の通りです。
- 変形性関節症(OA)
- リウマチ性関節炎(RA)
- 坐骨神経痛
- 脊柱管狭窄症
- 五十肩(肩関節周囲炎)
- 慢性腰痛・腰椎椎間板ヘルニア
- 骨粗鬆症
- 加齢による筋肉・関節の衰え
- 四肢のしびれ・冷え・倦怠感
- パーキンソン病の筋固縮
目次
独活寄生丸を用いる根拠
中医において、これらの疾患は
「風湿痺証(ふうしつひしょう)」
「肝腎不足」 による 筋骨の衰え
血虚による関節の栄養不足 が原因
《主要な病機》
✔ 風寒湿の邪が関節・筋骨に留まり、気血の流れを阻害(疼痛・こわばり)
✔ 肝腎不足により、筋骨が栄養を受け取れず衰える(慢性的な関節変形・萎縮)
✔ 血虚により、関節や筋肉に十分な血が行き渡らない(しびれ・脱力感)
独活寄生丸
風湿を取り除きながら、肝腎を補い、血虚を改善し、筋骨を強化する ことで、これらの病態に対応します。
方剤の方意(処方全体の狙い)
- 去風湿(風湿を取り除く) → 風湿痺証による関節痛を改善
- 補肝腎(肝腎を強化) → 筋骨を強化し、関節の慢性変性を防ぐ
- 活血通絡(血行を改善) → 瘀血を取り除き、関節の栄養供給を助ける
- 補気養血(気血を補う) → 長期間の消耗による虚弱を改善
各生薬の配合目的
独活寄生丸は 15種類 の生薬から成り、それぞれが異なる作用を持ちながら、相互にバランスを取っています。
| 生薬 | 作用 | 目的 |
| 独活(どっかつ) | 祛風除湿・止痛 | 風湿を取り去り、痛みを止める |
| 防風(ぼうふう) | 祛風湿・解表 | 風寒湿の邪を取り除く |
| 秦艽(じんぎょう) | 祛風湿・清虚熱 | 風湿を除去し、虚熱を鎮める |
| 桂枝(けいし) | 温経通陽・散寒止痛 | 経絡の気血を巡らせ、冷えによる痛みを改善 |
| 細辛(さいしん) | 温経止痛・散寒 | 関節の深部にこもる寒湿を取り去る |
| 杜仲(とちゅう) | 補肝腎・強筋骨 | 肝腎を補い、筋骨を強化 |
| 牛膝(ごしつ) | 補肝腎・活血通絡 | 筋骨を強化し、血行を改善 |
| 桑寄生(そうきせい) | 補肝腎・強筋骨 | 筋骨を滋養し、関節を丈夫にする |
| 当帰(とうき) | 補血・活血 | 血を補い、関節の栄養を改善 |
| 川芎(せんきゅう) | 活血行気・止痛 | 瘀血を改善し、痛みを軽減 |
| 地黄(じおう) | 滋陰補血 | 肝腎を潤し、陰血を補う |
| 白芍(びゃくしゃく) | 養血柔肝・止痛 | 肝血を補い、筋の緊張を緩める |
| 人参(にんじん) | 補気健脾 | 気を補い、体力の消耗を防ぐ |
| 茯苓(ぶくりょう) | 健脾滲湿 | 脾の機能を高め、湿邪を除く |
| 甘草(かんぞう) | 調和諸薬 | 他の生薬の調和をとる |
まとめ
独活寄生丸を用いる疾病
- 変形性関節症・リウマチ・坐骨神経痛・慢性腰痛など
- 肝腎不足による筋骨の衰え
- 血虚や気虚を伴う関節痛
- 風湿痺証による関節の痛みやこわばり
独活寄生丸を用いる根拠
- 風湿邪を取り去り、関節痛を軽減
- 肝腎を補い、筋骨の衰えを防ぐ
- 血虚を改善し、関節の栄養状態を向上
- 気血を補い、慢性疲労・脱力を防ぐ

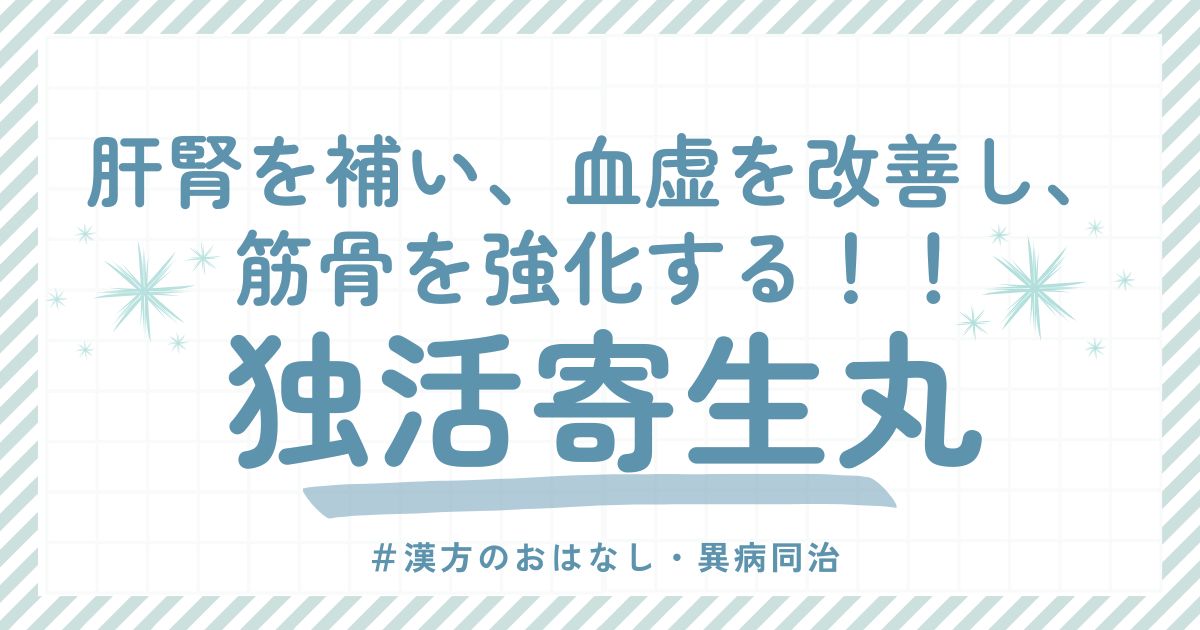
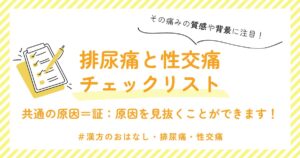
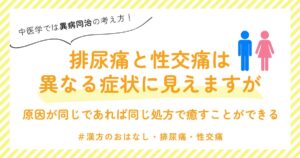
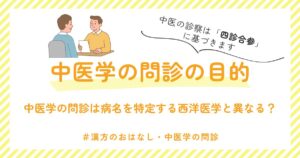
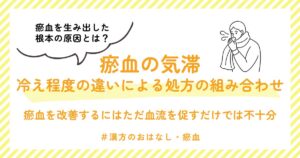

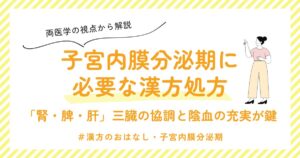
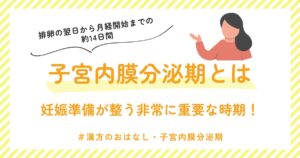
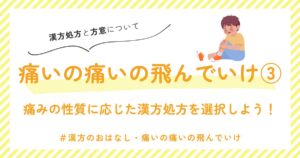
コメント