胃寒とは、胃に寒邪が侵入、または胃の陽気が不足することで、消化機能が低下し、
胃の冷えによる不調を引き起こす病態です。
寒邪により胃の気機が停滞し、胃痛、食欲不振、冷えによる嘔吐・下痢などが生じます。
目次
胃寒の病因(発生要因)
1.外寒の侵入
- 冷たい環境や寒冷な気候に長時間さらされることで、胃が冷える。
2.冷飲冷食の過剰摂取
- 冷たい飲食(氷水、アイス、刺身、生野菜など)が胃を冷やし、陽気を損なう。
3.脾胃陽虚
- 胃の陽気が不足していると、寒邪を受けやすくなり、胃寒が進行する。
4.気血の不足
- 気血が不足すると、陽気の生産・運行が低下し、胃が冷えてしまう。
5.情志の影響
- 過度なストレスや憂鬱な感情が胃の気の巡りを悪くし、寒の停滞を助長する。
胃寒の病理メカニズム
1.寒邪による胃の収縮
- 胃の陽気が損なわれると、血流が悪くなり、胃痛や消化不良が生じる。
2.気機の阻滞
- 胃の冷えが気の流れを滞らせ、膨満感や食欲不振を引き起こす。
3.寒邪の内盛(深部の冷え)
- 胃寒が進行すると、胃内に冷えがこもり、慢性的な胃痛や下痢を発生させる。
4.陽気の不足による消化機能低下
- 胃の運化機能が低下し、消化不良・便の異常が起こる。
胃寒の影響を受ける臓腑と症状
胃(消化機能の低下)
- 胃痛、食欲不振、胃の冷え
脾(消化吸収の低下)
- 消化不良、倦怠感、泥状便
腎(陽気の不足)
- 胃の冷えが持続し、慢性化すると腎陽虚に波及する
肝(気の巡りの影響)
- 胃寒が肝気の巡りを悪くし、食後の胃の不快感が生じる
胃寒の主な症状
- 冷えを伴う胃痛(温めると楽になる、冷たいもので悪化)
- 食後の胃の不快感(胃もたれ、膨満感)
- 悪心・嘔吐(胃の陽気が不足すると、温かい食べ物で改善)
- 泥状便・下痢(胃の寒邪が腸に影響し、水分がうまく吸収されない)
- 四肢の冷え(胃寒が進行すると全身の冷えが生じる)
- 顔色が青白い(胃寒による血流不足)
- 舌の特徴(淡白舌、白い苔、湿り気がある)
胃寒の悪化条件
- 冷たい飲食物の摂取 → 胃を直接冷やし、痛みや消化不良を悪化させる。
- 寒冷環境での長時間滞在 → 胃が外寒を受けて冷える。
- ストレスや気滞 → 胃の陽気の流れが悪くなり、寒邪の影響を受けやすくなる。
- 運動不足 → 気血の巡りが悪くなり、胃の陽気がさらに低下する。
胃寒の特徴
1.胃の痛みの特徴
「温かいものを食べると痛みが和らぎますか?」
2.冷飲冷食の影響
「冷たいものを摂ると、胃の調子が悪くなりませんか?」
3.排便の状態
「下痢が続いたり、泥状便になりやすくないですか?」
4.体の冷え
「手足が冷えやすくありませんか?」
5.食欲の変化
「食事をすると胃が重く感じますか?」
★まとめ
胃寒は、寒邪や胃の陽気不足により、胃の冷え、胃痛、消化不良、下痢などが生じる病態です。
治療の基本は、**温中散寒(胃を温め、寒を取り除く)**です。
食養生としては、冷たいものを避け、温かい飲食を心がけることが重要です。
特に、生姜、ネギ、シナモン、温かいスープなどを摂取し、胃を冷やさないようにすることが大切です。
また、適度な運動を取り入れて気血の巡りを良くし、胃の陽気を補うことも重要になります。

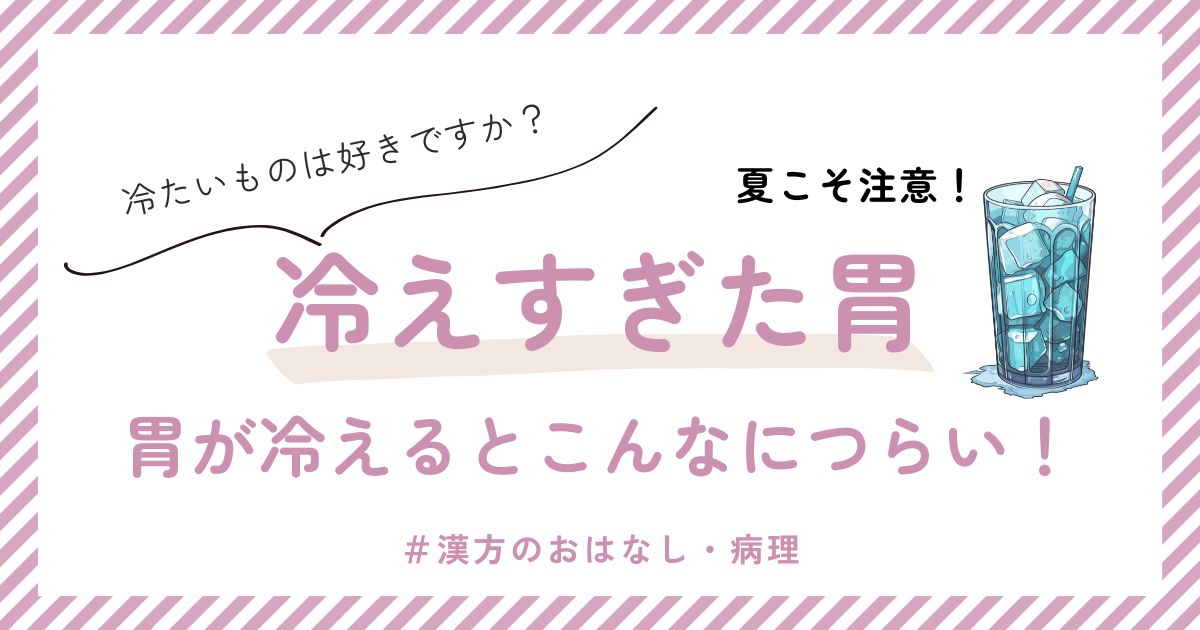
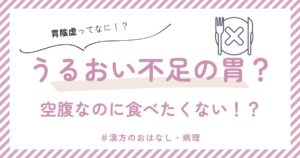
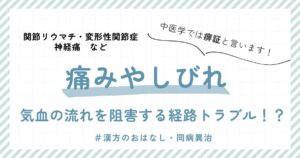
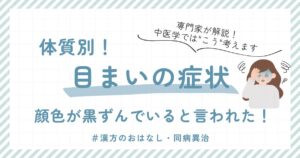
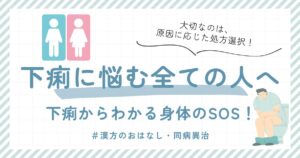
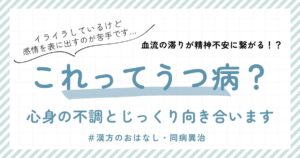
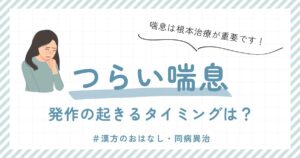
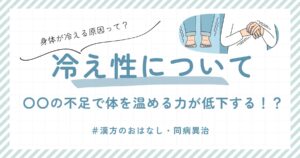
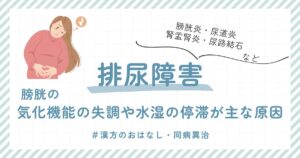
コメント