1.食物中にもエストロゲンがある
さまざまな食物にもエストロゲンが含まれています。例えば、肉や牛乳、
あるいは大豆製品である豆腐、納豆、みそなどです。このほか、多くの野菜、果物、
穀類などにさまざまなエストロゲン様物質が含まれています。
日常、摂取する食物中のエストロゲン(ヒトが作る活性の高いエストロゲンである
エストラジオールとエストロンに限る)の60~70%は、牛乳やチーズ、バター、ヨーグルト
などの乳製品に含まれているエストロゲンです。なお、植物エストロゲンは、動物に存在するエストロゲン
とはかなり異なった性質であり、同列に扱うわけにはいきません。
2.なぜ牛乳にエストロゲンが含まれるのか
野生の哺乳類やヒトは分娩後に乳を出します。分娩後には、エストロゲンはほとんど
分泌されません。また、授乳中の動物は自然な状態では妊娠することは極めてまれです。
そのため、本来は動物種を問わず、ミルク中のエストロゲン濃度は低値であります。
それゆえ、以前、人類が飲んでいた自然放牧された乳牛からとった牛乳中のエストロゲン
含量は低かったです。
しかし70年くらい前から、改良されたホルスタイン種などは、蛋白質を多量に含んだ
特殊な飼料で飼育すると、妊娠の後半にも乳が出るようになりました。この結果、
搾乳量は格段に増量しました。妊娠後半には、エストロゲンが多量に合成されるので、
妊娠後半中の乳牛が出す牛乳にはかなりの濃度のエストロゲンが含まれることになります。
妊娠中の乳牛は、エストロゲンとともに黄体ホルモンも多量に分泌するため、牛乳中には
黄体ホルモンも検出されます。つまり、搾乳効率を高める代価としてエストロゲン含量は
増加するということになります。
☑牛乳中のエストロゲンは人体に影響するか
牛乳中のエストロゲンは人体に影響があるのでしょうか。
月経のある女性、あるいは妊婦には相当量の内因性のエストロゲンがあるので、
牛乳を毎日400ml程度飲んでも、トータルのエストロゲン量には大きな影響は
与えません。しかし、まだ卵巣が機能していない未熟なラットに牛乳を与えると
子宮が増大することから、牛乳中のエストロゲンは実際にエストロゲンとしての
生物作用を発揮することがわかっています。
人体への影響は不明ではありますが、飲食によりエストロゲンを摂取したとしても
腸から吸収されるのはその一部です。また吸収されるとすぐに肝臓に移行しますが
エストロゲンの大部分は肝臓で不活化されます。そのため、仮に相当量のエストロゲンを
経口摂取しても全身の組織へ影響しうるエストロゲンは微量となります。
また、乳牛は牧草を食べているため、牛乳中には植物エストロゲンも相当量含んでいます。
植物エストロゲンは動物が作るエストロゲンとともに存在すると、後者の作用を一部
打ち消すように働くため、実際にはトータルとしてのエストロゲン活性の評価は困難です。
なお、牛乳などの食物を通じて摂取されるエストロゲン量は、1998年にJECFA(FAO/WHO
合同食品添加物専門会議)が定めた1日許容量を超えてはいけません。JECFAの許容量は体内で
産生される総エストロゲン量と比較して、はるかに小食ということで結論付けられたものであります。
そのため、体内でのエストロゲン産生量がきわめて少ない小児に対する影響は、不明という
意見もあります。また、男女ともに思春期に起こる全身の変化は、体内のエストロゲンの精妙な
調整によりもたらされます。そのため、外からのエストロゲンによる血中エストロゲン値の
微妙な変化が思春期の経過に全く影響しないという確証はありません。しかし、牛乳は栄養源
としては大変優れたものであり、その摂取量を論じる際には、栄養学的価値と残留ホルモンによる
影響とを総合的に勘案すべきであります。

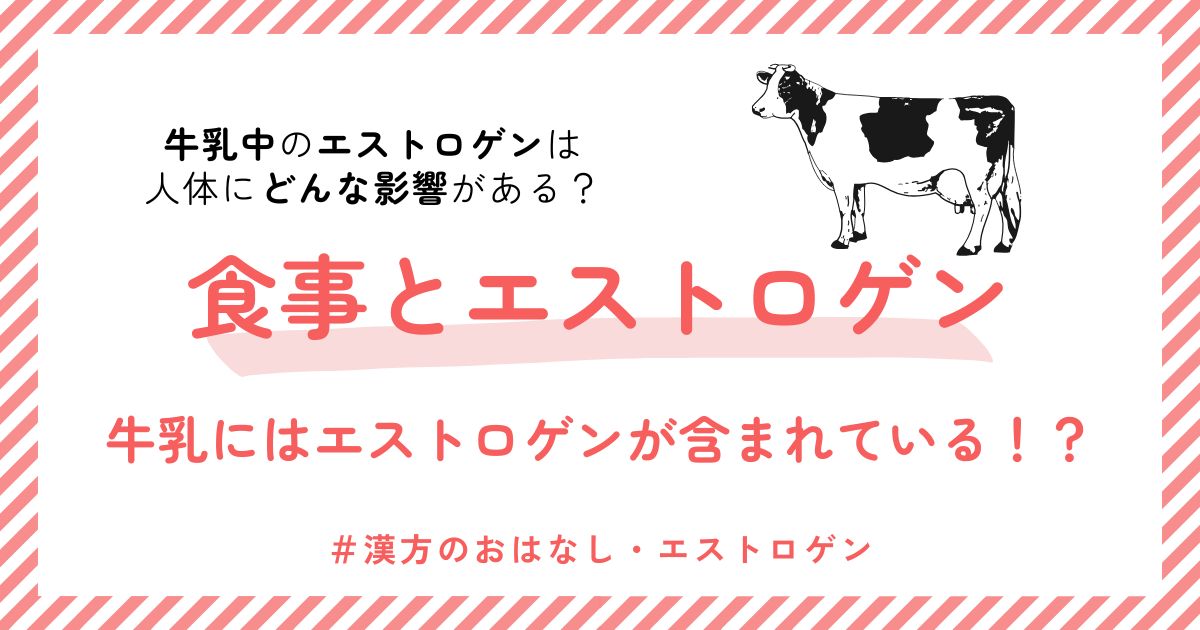
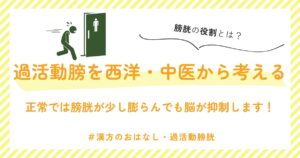
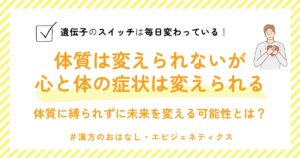
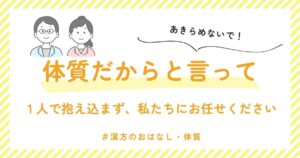
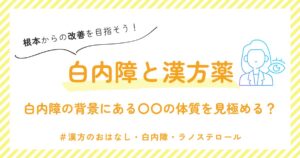
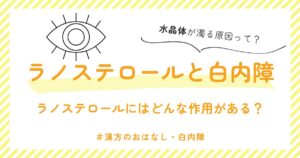
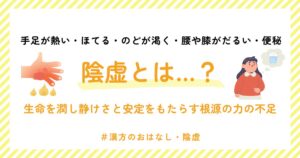
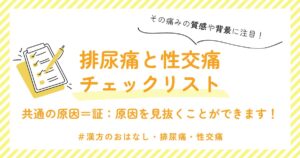
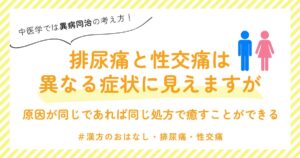
コメント