1.エストロゲンは食欲を低下させる
エストロゲンには食欲を抑える作用があり、エストロゲン分泌が高まる発情期には
食欲が落ち、ヒトでも排卵期にはカロリー摂取量が減ります。
一方、卵巣を摘出してエストロゲン欠乏状態になったラットでは、摂取量は増し
肥満傾向となりました。エストロゲンは受容体を介して生物効果を発揮しますが、
エストロゲンの受容体を欠いたマウスは、オスでもメスでも脂肪組織が増えます。
サルの実験でも卵巣を摘除すると過食傾向となり体重増加がみられます。
☑男女の違い
食欲の調節系には性差があります。メスではエストロゲンが低下すると食欲が増しますが
オスでは男性ホルモンが低下すると食欲も低下します。
閉経後はエストロゲンが低下する50歳前半の女性では、まだ月経がある女性と比較すると、
閉経を迎えた女性のほうが肥満の割合は高まります。なお、閉経後女性にエストロゲンを
補充すると、体重の増加は鈍化するという報告もあります。ただエストロゲンの補充が
体重を抑えるのか、あるいはエストロゲンが脂肪組織に働いて、その分解を高める
ことによるのかは不明です。サルなどの実験では、卵巣を摘除したあとにエストロゲンを
投与すると、少なくとも摂取量が低下することが認められています。
***
中医学では、食欲=脾異(ひい)の状態を反映します。
エストロゲンが安定している時期、(排卵前~排卵期)は
身体の中の『陰』が満ちていて、脾異も穏やかに働くため
食欲が安定しやすいです。
一方、エストロゲンが減る(黄体期~月経前)は
『陽』が相対的に強くなり、
イライラや気滞(きたい/気が滞る)、過食、甘いものへの
欲求がでやすいと考えられています。
***
2.エストロゲンは脳に作用して食欲を調整する
エストロゲンは、脳の視床下部に存在する食欲を調整する中枢に作用して、
食欲亢進因子を抑制したり、抑制因子の作用を増強させるなど摂食量に影響させると
考えられます。脳内には食欲を亢進する、あるいは抑制する物質が多数存在しています。
食欲を調節する物質の多くは、性機能の調節因子でもあり、摂食行動と性機能とは
密接に関連しています。食事を摂らないと個体の健康は維持できず、しかも、生殖のためには
良好な栄養状態であることが前提条件となります。
したがって、摂食と生殖の調節システムとがお互いに関連しあうことは合目的性があります。
両者の巧妙なバランスは、エストロゲンにより制御されています。
3.女性が甘いものを好む理由
一般に女性は、男性と比べ、ケーキ・チョコレート・アイスクリームなど甘いものを好みます。
文化的、社会的に男女の嗜好が定められていたことも関係していると考えられます。
しかし、生物学的にも味覚に関する性差はあるようです。動物でも甘いものに対する好みは
オスよりはメスのほうが強いといわれています。ラットを用いた研究でも、オスよりメスのほうが
糖分や甘味料を好みました。メスラットを去勢すると甘いものを控えるようになり、
エストロゲンと黄体ホルモンを投与すると元の好みに戻りました。
甘いものは糖分が多く含まれています。妊娠前、妊娠中や哺乳時には十分な糖分の摂取が必要であり、
女性が甘いものを好むのは生殖における男女の役割を考えると合理的といえます。


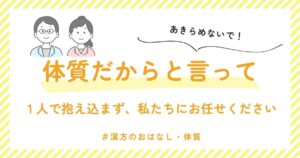
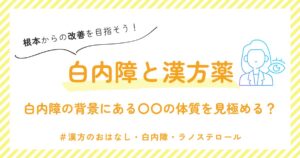
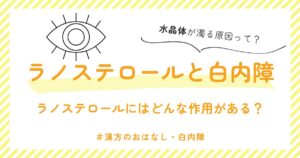
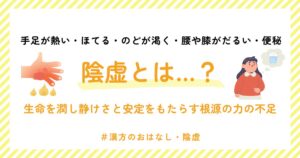
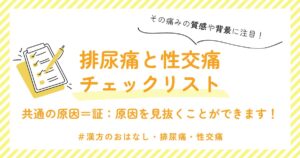
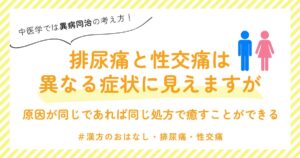
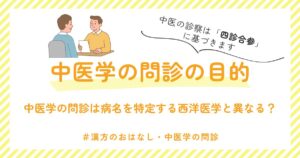
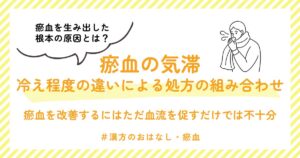
コメント