1.エストロゲンの母体に対する作用
絨毛細胞から出るエストロゲンは、胎盤内の血管を発達させることで
胎盤の発育を促進しています。なお、胎盤発育にかかわるエストロゲンの作用には、
血管を伸長させる血管成長因子が介入しています。
妊娠中は胎児発育とともに当然子宮も増大しますが、エストロゲンの作用によるものです。
さらに、妊娠中には胎児の発育を支えるために母体の全身の血管が拡張して
循環血液量が40%程度増えていますが、この機序にエストロゲンが
関与していると考えられます。
また、分娩が終了すると直ちに哺乳が必要となります。
このために妊娠中に乳腺を発育させ、下垂体のプロラクチン産生細胞を
増殖させる必要がありますが、このような母体の変化にもエストロゲンが重要な役割を果たしています。
2.エストロゲンの胎児に対する作用
サルを用いた研究から、エストロゲンは肺や肝臓などの主要臓器の
成熟にかかわっているとされています。さらに胎児の脳に作用して、
中枢の性分化(社会において、どの性として行動したいか、あるいは実際に
どう行動しているか、さらに性腺を調節する中枢の内分泌機能が男性型か女性型かなど)
のカギを握っている物質です。
胎児の下垂体には、胎齢8~10周ですでに下垂体ホルモンである
卵胞刺激ホルモン(FSH)、黄体刺激(LH)、プロラクチンなどを作る細胞が
認められています。これらの下垂体ホルモンの発想はエストロゲンにより刺激されます。
なお、副腎からDHEA-Sが分泌されないウシ、羊、ウサギの胎仔では卵巣で
エストロゲンが産生され、脳の性分化や卵巣発育に関係していると推定されています。
卵巣に存在する卵は胎児期に作られ、生後はその数は減少の一途をたどります。
ヒトでは胎齢15週から原始卵胞の形成が開始します。
卵巣にはエストロゲンの受容体(ER a 、 β)があり、妊娠中のサル(ヒヒ)に
エストロゲン合成酵素阻害剤(アロマターゼ阻害剤)を投与すると、胎児の卵の数(卵胞数)
が減少し、エストロゲンを同時に投与すると回復します。
以上のことから胎児期の卵巣での卵の形成には、エストロゲンが必要です。
3.妊娠由来のメカニズム
☑エストロゲンの関わり
分娩が開始する前に、母体血中のエストリオールの濃度は最大となり、
このことが陣痛開始と密接に関係する。
エストリオールと陣痛開始との関連を示唆する事実として妊娠中にエストリオールが
作られないような妊娠では分娩が遷延することがしばしばあります。
例えば、無脳児、胎児のスルファターゼ欠損症、胎児の副腎の形成不全などでは
いずれも母体血中のエストリオール値が低く、分娩の時期が遅れる傾向にあります。
☑エストリオールが陣痛を起こす仕組み
まず、子宮に作用して子宮頚管の熟化を促します。
さらに中枢からのオキシトシン分泌を促し、子宮でオキシトシン受容体を増やし、
オキシトシンの感受性が高まることなどで陣痛を誘発すると考えられます。
なお妊娠中には黄体ホルモンとエストロゲン両方が増えていて、黄体ホルモンは
妊娠を維持させるように子宮筋に作用することでエストロゲン(エストリオール)の
子宮への作用を抑えています。妊娠の進行とともに黄体ホルモン/エストロゲン比は低下し、
分娩が近づくと最も低くなることで、エストロゲンによる子宮の収縮作用が現れるようになります。
4.分娩開始のメカニズムは動物により異なる
分娩開始のメカニズムには種差があります。
ヒツジの分娩のタイミングのカギは胎仔副腎由来のコルチゾールが握っています。
胎児の視床下部-下垂体系-副腎系が十分に発達を遂げた後に、
分娩発来に必要な量のコルチゾールが分泌されると分娩が開始します。
コルチゾールは胎盤にてアロマターゼを介さない機序でエストロゲン産生を高め、
その結果分娩が起こるといわれています。なお、ウサギ、ラット、マウスなどの
妊娠期間の短い動物では妊娠期間を通じ母体の卵巣からエストロゲンが出ており、
胎児副腎-胎盤系の関与は乏しいです。

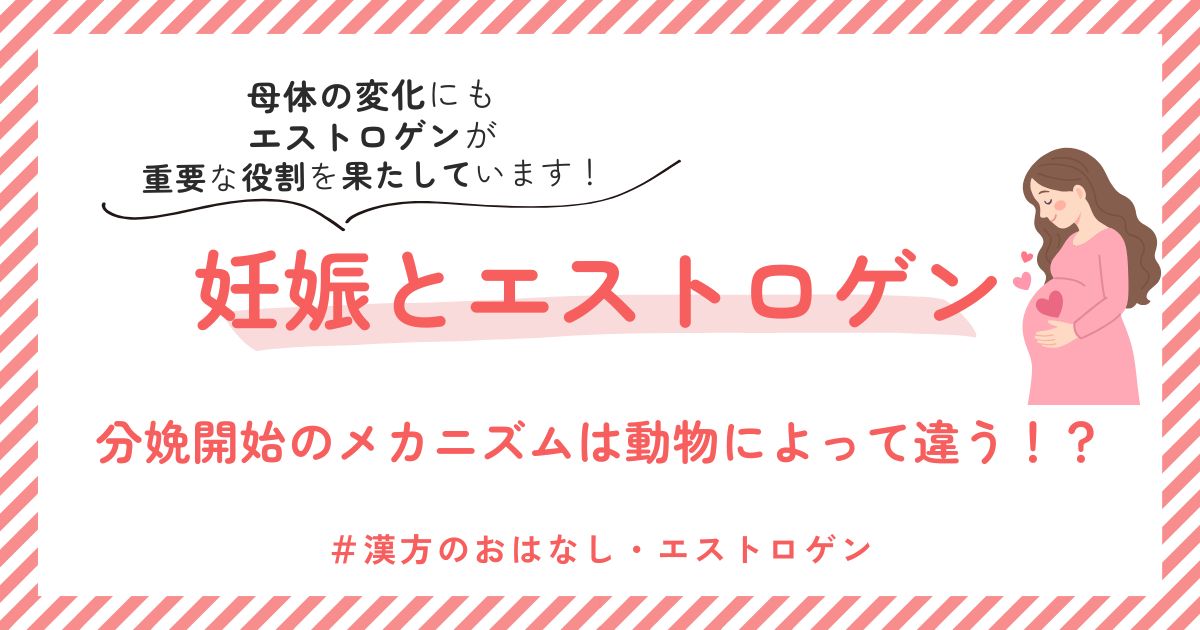
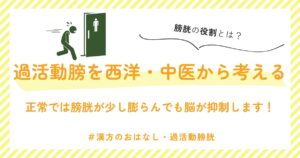
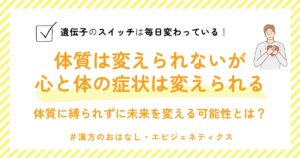
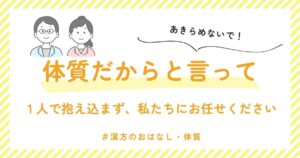
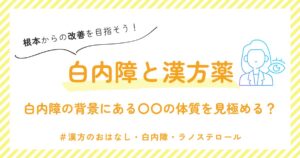
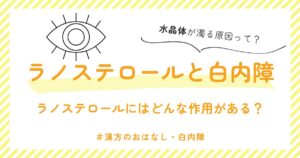
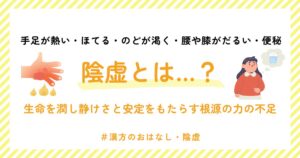
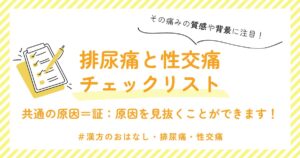
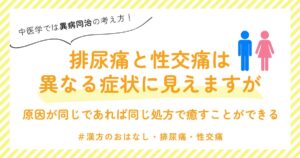
コメント