1.更年期障害とは
日本産科婦人科学会の定義では、閉経の前後各5年間を更年期と呼びます。
この間に現れる多様な症状の中で、精神疾患、内科的疾患、整形外科的疾患などの
症状として説明できないものが更年期症状であり、日常生活に支障をきたす場合に
更年期障害とみなします。
更年期障害の背景には、エストロゲンの低下が深く関係していますが、
加えて加齢に伴う身体的変化、家庭環境、心理的要因、固有の性格などが複合的に絡み合っています。
また、更年期症状の程度や発現率には人種さ、民族差がありますが、生物学的な差によるものか、
あるいは、更年期の受け止め方や女性の不快感の表出の仕方が文化や伝統によって
異なるのかは定かではありません。
***
中医学では、女性は『7の倍数』で身体が変化するといわれています。
例えば、7歳で歯が生え変わる、14歳で初潮…49歳で閉経など。
つまり更年期は『7×7=49歳』の節目で“腎のエネルギー”が
少しずつ減っていく自然な流れです。
思春期と同じく身体と心が揺らぐ時期といえます。
***
☑閉経とエストロゲンの低下
エストロゲンが急激に低下するのは閉経以降ですが、閉経数年前から
エストロゲン分泌は徐々に低下しています。
そのため閉経前から更年期の症状がみられることもあります。
エストロゲンがあるレベル以下になると、更年期症状が発症するわけではなく、
エストロゲンが低下しつつある時期、または大きく変動していることが
更年期症状の誘因となります。月経がある女性で両側の卵巣を摘出した場合や、
あるいは抗がん剤の投与により卵巣機能が低下したような場合には、エストロゲン濃度が
急激に低下するので更年期症状は比較的激しいです。
☑更年期の症状
更年期の症状の中で、エストロゲンの低下に直接関連している症状は、のぼせ(ホットフラッシュ)、
発汗などです。特にのぼせは最も特徴的な症状であり、40~85%の女性が経験します。
不眠もエストロゲンとの関連が指摘されています。
それ以外に憂うつ、イライラ、不安感、めまい、疲労感などの精神神経症状、
頭痛、腰痛、関節痛、肩こりなどの痛みに関連する症状、しびれなどの知覚異常、
全身倦怠感、動悸などの症状があります。
これらの症状は多彩であり、しかも通常の検査では原因がつかめず不定愁訴と呼ばれています。
アメリカ報告では、更年期症状は平均で約10年程度持続するといわれています。
閉経前から出現した場合には、閉経後に出現した場合と比較して更年期症状の
持続期間が長くなる傾向があります。症状の程度はほとんど気にならないものから
この世の終わりというほどの苦痛を訴える女性もおり、実に多様です。
エストロゲンの欠乏は継続しても、いずれ身体はその状態に馴化してくることで
次第に軽減します。また、更年期症状の背景にある家庭環境などが変化してくることも
自然に消失する理由のひとつだと考えられます。
***
中医学では同じ更年期症状でも体質や原因が違えば治し方も違う
“同病異治”(どうびょういち)という言葉があります。
ほてりやのぼせ、発汗に寝汗、不眠や動悸、イライラや情緒不安定…などの
症状でも原因のタイプ(陰虚・陽虚・気滞)の違いを見極めて
それぞれの体質に合った治療法を考えていきます。
***
2.更年期障害にはエストロゲンが有効
更年期症状の根底にエストロゲンの低下がありますが、それのみでは説明できない
多くの要因が関与しています。したがって、エストロゲンを補えば更年期症状は
すべて解消するということではありません。
のぼせ、発汗などの血管運動神経症状はエストロゲンの低下が直接関与していて、
エストロゲンが有効です。閉経前に近いエストロゲンレベルに近い状態になるように
エストロゲンを補充すれば、90%以上の有効率が期待できます。
それ以外の症状にもエストロゲンの低下によりもたらされる血管運動神経症状が2次的に
さまざまな症状を発症していることも多く、エストロゲン製剤投与で軽減できる場合もあります。
例えば、抑うつ気分や不安感に対しては40%程度の効果が期待できます。
なお、抑うつ状態に関してはエストロゲン低下に伴い、脳内のセロトニンが減少することや
セロトニンに対する感受性が低下することが原因の一つと考えられています。
また、不眠や疲労感などに対してもエストロゲンは比較的有効です。
なお、肩こり、腰痛などの痛みに対してはエストロゲン低下との因果関係は弱く、
エストロゲン製剤の有効率は高くありません。
☑エストロゲン投与の副作用
閉経後の女性に対するエストロゲン投与の副作用としては、乳房が張ったり痛くなる
性器出血、おりものが増えるなどがあります。これらは副作用というよりはエストロゲンの
本来の作用というべきものです。また、エストロゲン製剤のみを数か月以上投与すると
子宮内膜が肥厚し、子宮体がんのリスクが高まります。
そのため、子宮のある女性にエストロゲンを投与する際には必ず黄体ホルモン製剤を
併用するべきであります。これにより、子宮体がんのリスクの増加は防ぐことができます。
なお、子宮を摘出している場合にはエストロゲン製剤を単独投与できます。
3.閉経年齢が高い女性は〇〇に注意
エストロゲンが低下すると一般に動脈硬化が進みやすくなります。
女性の閉経年齢は50歳前後ですが、閉経年齢が早いほど動脈硬化による
脳卒中が増加します。逆に55歳まで月経がある女性では罹患率は低下します。
最近のアメリカ在住の女性を対象とした研究によると、46歳未満で閉経を
迎えると、動脈硬化による心疾患や脳卒中は約2倍に増加することが示されました。
また閉経が早いと骨粗鬆症のリスクも高まる可能性があります。
つまり、これらの疾患は年齢ではなく、閉経後の年数とともにリスクが高まるということです。
比較的若くして閉経を迎えた女性は、少なくとも50歳くらいまではエストロゲンの補充を
行うことで動脈硬化による疾患や骨粗鬆症をある程度予防可能です。
この場合には閉経後速やかに開始したほうがよいでしょう。なぜならば、
エストロゲンが欠乏した期間が長期になるにつれて、動脈硬化が進行する
ことになるからです。いったん動脈硬化が起こると、エストロゲンを投与しても
改善せず、逆にエストロゲンの投与により、細くなった血管内に血栓が
できやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクを高めることになります。

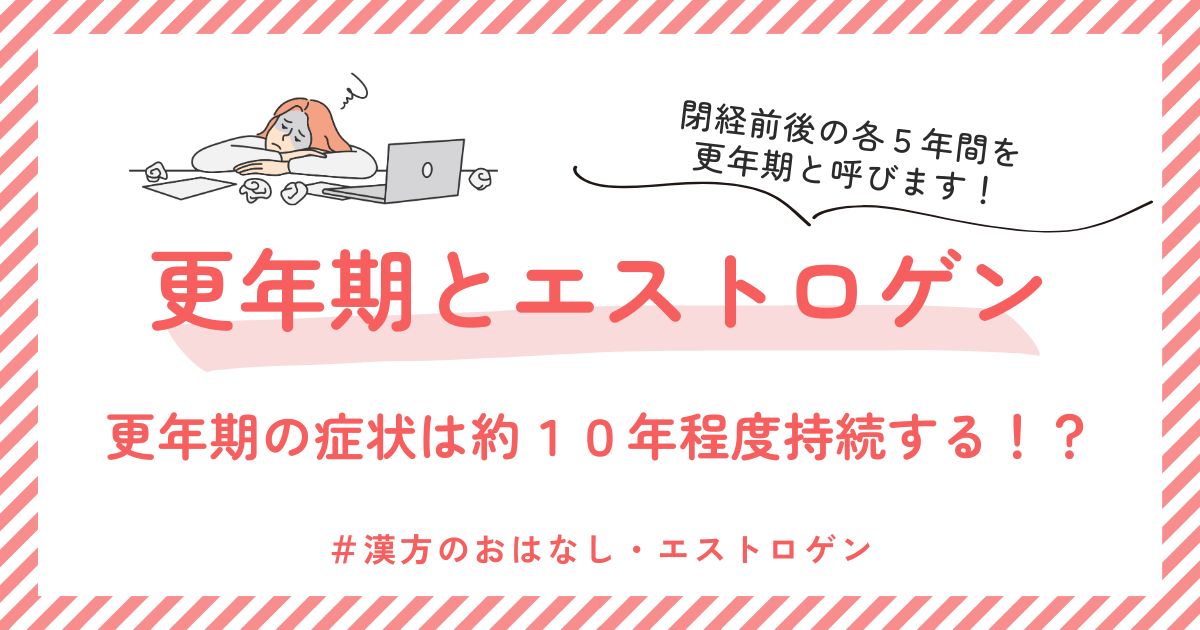
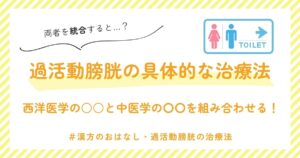
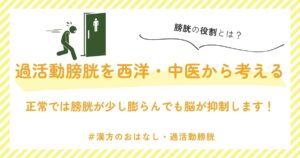
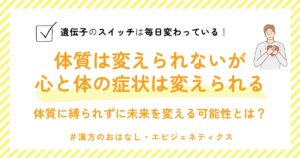
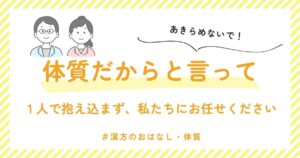
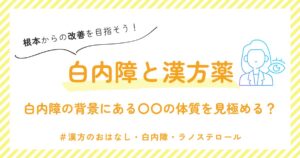
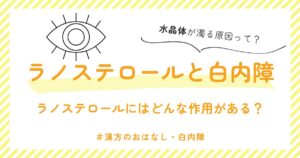
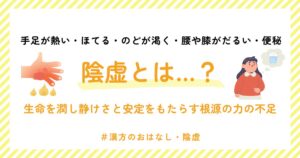
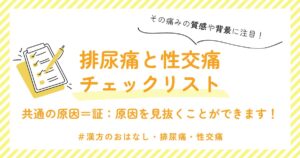
コメント