寒湿困脾とは、寒邪や湿邪が脾胃に停滞し、消化機能が低下する病態を指します。
脾は陽気を好み、湿を嫌いますが脾の影響を受けると運化機能(消化・吸収)が低下し、
胃腸の不調や水分代謝異常を引き起こします。
目次
寒湿困脾の病因(発生要因)
1.冷たい飲食の摂取
- 冷たいものや生ものの過剰摂取が脾胃を冷やし、寒湿を生じる
2.湿邪の侵入(環境要因)
- 梅雨時期や湿気の多い場所に長時間いると、寒湿が脾を侵す
3.過剰な湿潤環境
- 水仕事の多い職業、湿度の高い地域に住んでいると発症しやすい
4.脾陽虚の進行
- もともと脾陽が不足している人は、寒湿が停滞しやすい
5.慢性の消化不良
- 胃腸の機能が低下すると、消化がうまくいかず、湿邪が滞る
寒湿困脾の病理メカニズム
1.寒邪の影響
- 胃腸の陽気が阻害され、消化吸収機能が低下する
2.湿邪の停滞
- 水分代謝が悪化し、体内に余分な水分が溜まる
3.脾の運化障害
- 気血の生成が低下し、倦怠感やむくみが発生
4.胃腸の蠕動低下
- 消化が進まず、食欲不振や胃もたれが生じる
5.水湿の蓄積
- 体内の水分が排出されず、下痢や浮腫を引き起こす
寒湿困脾の影響を受ける臓腑と症状
1.脾(運化機能の低下)
- 胃もたれ、食欲不振、倦怠感
2.胃(消化不良)
- 消化吸収の低下、吐き気、嘔吐
3.腎(陽気の不足)
- 寒冷感、下半身の冷え、尿量減少
4.肺(水分代謝の停滞)
- 痰が多く、咳が出やすい
寒湿困脾の主な症状
- 消化不良(食欲不振、胃もたれ、腹部膨満感)
- 冷え(特に下半身が冷たい)
- 軟便・下痢(食後すぐに排便する)
- 倦怠感(気力が出ない、身体が重い)
- むくみ(特に朝、顔や手足に浮腫が出る)
- 舌の特徴(胖大、白い苔、湿り気が多い)
- 口の中が粘る、味が感じにくい
寒湿困脾の悪化条件
- 冷たい食べ物や飲み物の摂取 → 胃腸がさらに冷え、機能低下
- 梅雨時期や湿度の高い環境 → 外湿が体内に入り、悪化
- 長時間の座り仕事・運動不足 → 体の気血循環が悪化し、寒湿が滞る
- 過労・ストレス → 気血の流れが悪くなり、脾の運化機能が低下
- 過剰な水分摂取 → 水湿の停滞を助長し、むくみがひどくなる
寒湿困脾の問診ポイント
1.消化状態
「食後に胃が重くなったり、もたれたりしますか?」
2.排便の状態
「便がゆるく、水っぽくなりやすいですか?」
3.冷えの有無
「手足が冷たく、温めると楽になりますか?」
4.浮腫の有無
「朝、顔や足がむくみやすいですか?」
5.食事の好み
「温かいものと冷たいもの、どちらが食べやすいですか?」
★まとめ
寒湿困脾は、脾胃に寒邪と湿邪が停滞し、消化不良や下痢、冷え、むくみなどの症状を引き起こす病態です。
治療では、**温中化湿(胃を温め湿を除く)**が基本です。
食養生としては、**温かい食事(生姜・味噌汁・スープ類)**を摂取し、
冷たいものや生ものを避けることが重要です。また、運動や半身浴で体を温め、湿の停滞を防ぐことも有効です。

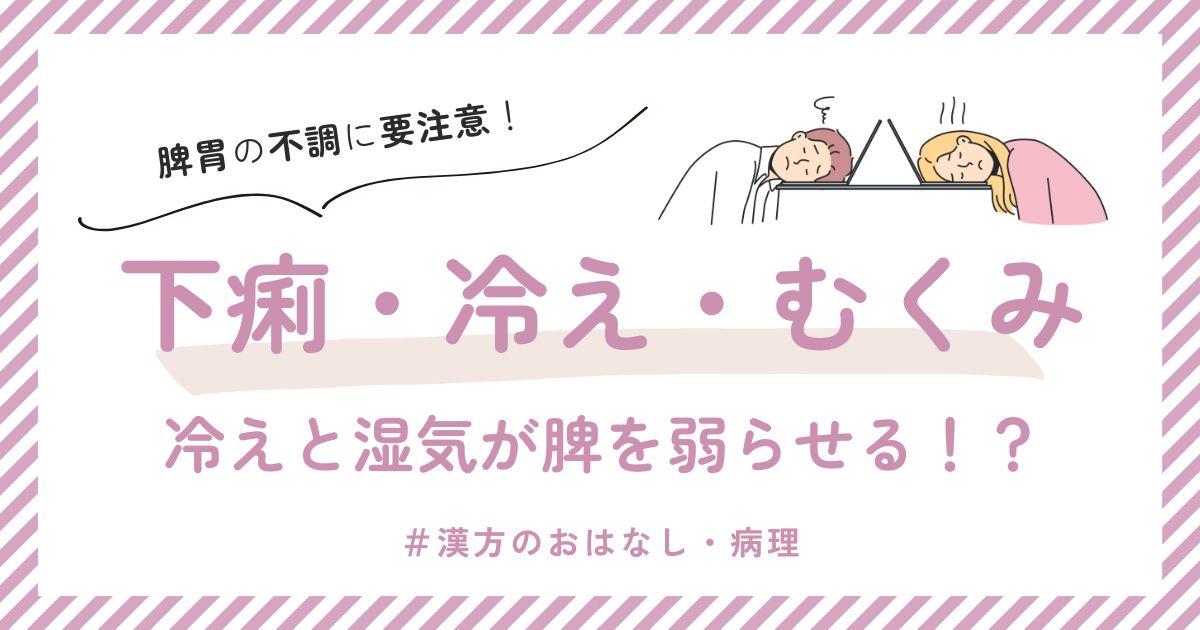
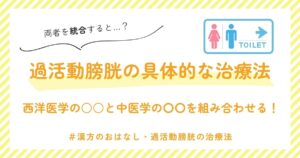
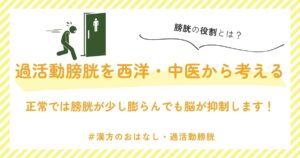
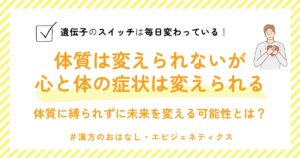
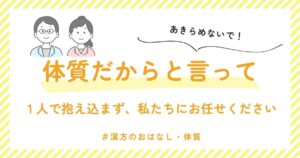
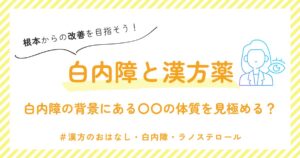
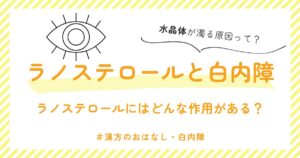
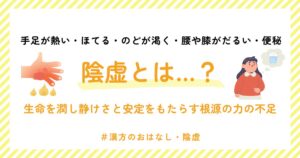
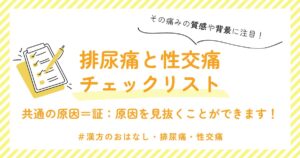
コメント