漢方の歴史について古代中国から遡っていくつかのシリーズで解説させていただこうと思います。
第三回目に古代中国において既に体系化されていた本草書のお話しです。
この時代に作られた本草書は現代へと続く、後に作られる本草書の大本となっている。
今回の記事の概要をまず冒頭でご説明いたしまして、
続いて概要に記載している内容の詳しい説明を記載していきます。
簡単に歴史を知りたい方は序文だけをお読みいただき、
更に詳しく知りたい場合は目次よりご興味のあるタイトルをクリックしリンクへとお飛びください。
今回の概要
古代中国について第一回、第二回と殷王朝の遺跡の発掘や漢字文化の存在、扁鵲伝説や、
その時代から医師や医書についての分類が既に行われていたこと、
また古代の漢方の知識がより体系化された漢代(とくに前漢の時代)についてご説明いたしました。
前漢の時代、いくつかの生薬を組み合わせて実際に病に対する治療を行っており、
前漢以前の古代中国の時代から受け継がれた医書も重要な書として保管されていた。
といったことをご説明いたしました。
続く後漢の時代では漢方の三大古典とも言われる
『神農本草経』『黄帝内経』『張仲景方(傷寒雑病論)』のうちの
『神農本草経』や『張仲景方』がなったとされています。
伝説上の帝王「神農」の名を託した『神農本草経』は、生薬の解説書です。
365種類の生薬を薬効別、更に人にどのように作用するかといった人間を中心とした分類をしています。
『神農本草経』はその後の本草書の規範となり継承と発展を繰り返し、
明代には李時珍が『本草綱目』を発刊し、現在でも絶大に支持され中国において、
李時珍は科学者の英雄として評価されている。
話しは変わりますが、私自身テレビをほとんど見ないのですが、
そんなテレビ素人の私がオススメする番組です(急にすみません)。
先日テレビをつけましたら(といってもソファで寝転がっていたら足元にあったリモコンを押してしまい
自然とテレビが付いた状況)たまたまやっていた番組です。
「NHK空からクルージング」という番組です。
上空からドローンで趣ある町の風景や雄大な自然を撮影し、
ゆったりとその地域を見ることの出来る番組です。
時より字幕によるナレーションが入り、ただただその美しい映像を静かに眺めるのには最適の番組です。
一言、地球が作り上げた自然の美しさに心が洗われました。
その日はイタリア・シチリア島を特集していました。
シチリア島の雄大な自然を映像として目の前に思う存分に見せてくれます。
紀元前に建てられた神殿が今でも町の教会として利用されており、
古代ヨーロッパの建築技術のすごさにただただ驚かされました。
また、シチリア島のギリシャ劇場には1万5千人もの人を収容できたそう。
空一面に青空の広がる劇場に1万5千人が集まったときの人々の熱気を想像しますと胸が熱くなります。
そして、その時代に1万5千人にどうやって演劇の日時を知らしめたのか。。。
その劇場にはお風呂もあり、なんと入浴しながら劇の鑑賞も出来てしまいます。
古代の人々が人生を愉しみつくそうとしたその姿に尊敬の念を覚えます。
現在も修復を繰り返しながら利用されているそうです。
そしていつの間にか番組は終わりピタゴラスイッチが始まっていました。(ピタゴラスイッチも面白い。)
第三章 神農伝説(しんのうでんせつ)と『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』
簡単なまとめ↓
■ 中国医学の三大古典(漢方の三大聖典)
1.『神農本草経』:後漢(紀元前31年~紀元220年)になる。
- 薬物学書。365種の薬物を薬効別に分類。
2.『黄帝内経』:戦国時代(紀元前475年~紀元前221年)になる。
- 医学理論と針灸術についての記述。『素問』『霊枢』などがある。
3.『張仲景方(傷寒雑病論)』:後漢(200~210年)になる。
- 張仲景が著した処方書。『傷寒論』『金匱要略』などが現存。
☑これらは中国伝統医学の基礎であり、以後2000年にわたり重視され続けている
詳細↓
中国において殷・周・春秋・戦国時代を通じて、膨大な経験と知識の集積のもとに
中国特有の医学が形成されていった。
そして漢代になり、中国医学は体系化され基盤が確立した。
このことを示す漢方の三大古典といわれるものがある。
ひとつは『神農本草経』という薬物学書。
ひとつは『黄帝内経』という医学理論と物理療法(針灸術)について記載。
(現存のテキストは『素問』『霊枢』『太素』『明堂(めいどう)』)
もうひとつは『張仲景方』という三世紀初めに張仲景によって書かれた医方書。
(後に『傷寒雑病論』と称され、現存のテキストは『傷寒論』『金匱玉函経(きんきぎょくかんけい)』『金匱要略』)
これら三大古典は中国伝統医学の三大源流というべきもので、
以降2000年近くに及ぶ漢方医の歴史はこれらの聖典をいかに解釈し、
位置づけ、応用するかの延長線上でとらえることが出来る。
神農伝説
簡単なまとめ↓
■ 神農伝説
- 神農は伝説上の帝王(三皇の一人)で、医薬・農業・商業の神。
- 赤い鞭で草木を打ち、その薬効や毒性を調べたとされる。
- 実際には、中国古代の経験知を神話化した象徴的人物。
- 現代日本でも「神農祭」として信仰が継承されている(例:大阪・東京)。
詳細↓
中国古代の伝説上、三皇(三人の帝王)がいる。
医学の分野においては伏羲(ふっき)・神農(しんのう)・黄帝(こうてい)をいう。
伏羲は易の創始者、神農と黄帝は医薬に深い関係を持つ帝王である。
神農の姓は姜(きょう)、炎帝(えんてい)とも称され、陳に都を置き、後に魯(ろ)に移し140年在位したとされる。
牛の頭をしていて角があり、木の葉で作った衣装をまとい、人民に初めて農耕を伝えた。
赤い鞭で草木を打って採取し、その効用や毒性をひとつひとつ検査して確定していった。
神農は一日に70回も中毒を起こしたという。
もちろんこれは史実ではなく、
太古からの中国人の経験の集積を一人の人物に業績にあてはめ神話化したものに他ならない。
神農は農耕・医薬・商業の神としてまつられてきた。
現在の日本においても大阪や東京(御茶ノ水や日本橋)では「神農祭」が行われている。
『神農本草経』と本草
簡単なまとめ↓
■ 『神農本草経』の概要
- 成立時期:後漢(1~2世紀)
- 内容:365種の動・植・鉱物薬を収録
- 特徴的分類(三品分類):薬効による人間中心の分類
- 上薬(120種):養命薬。毒性なし。不老長寿向け。
- 中薬(120種):養性薬。体力増進。条件次第で有毒。
- 下薬(125種):治病薬。有毒。治療に用いるが、長期服用は不可。
☑治療より**養生(予防・健康維持)**を重視する思想が根底にある。
■ 本草の思想と比較
- 西洋(例:ディオスコリデス本草):自然中心・形態分類
- 東洋(例:神農本草経):人間中心・薬効分類
☑東西の思考法の違いが本草分類にも明確に現れている。
■ 漢方の薬学的アプローチの特徴
- 複合処方(君臣佐使・七情):薬の組み合わせ・相互作用を重視
- 調剤技術(修治・炮炙)と剤型:加工法・製剤形状による効果の変化も考慮
☑西洋の「単一成分抽出・合成」重視とは正反対のアプローチ。
詳細↓
神農に名を託した書に『神農本草経』という古典がある。
これは個々の生薬について解説したもので、中国最古(1~2世紀の後漢代のもの)の薬物学書である。
「本草」とは草に本(もと)づくの意で、薬に植物性のものが多いことがこのことからもうかがえる。
また、「本草」とは健康維持をも含む広義の薬用動植鉱物(本草個体・生薬)を指し、
「漢方薬」の原料となるものである。
「本草書」は、これらの様々な本草個体を集めて分類し、薬学的解説を加えた書である。
『神農本草経』には365種の漢方薬(動・植・鉱物薬)が収載されている。
そしてそれらは上品・中品・下品(上薬・中薬・下薬とも)の三ランクに分類。
この分類は生薬の基原的・形態的ではなく、薬効による分類であることが特徴である。
本草の三品分類といっている。
「上薬は120種ある。君主の役目で、養命薬つまり生命を養う目的の薬であり、毒性がない。
長期間の服用が可能。身体を軽くし、元気を益し、不老長寿の作用がある。」
「中薬は120種がある。臣下の役目で、養性薬つまり体力を養う目的の薬であり、
使い方次第で無毒にも有毒にもなる。
服用に当たっては注意が必要。病気を予防し、虚弱な体を強壮にする。」
「下薬には125種がある。佐使つまり召使の役目で、治病薬つまり病気の治療薬である。
これは有毒であるから長期間服用してはいけない。
寒熱の邪気を除き、胸腹部にできたしこりを破壊し、病気を治す。」
本草経では保健・予防的・体力増進的な薬が上ランクに、病気の治療薬が下ランクにある。
常に上品ないし中品で健康を保ち、下品に頼るのは最後の手段で本来好ましい事ではないという思想である。
このように保健薬を上ランクに置くのは、中国医学の根本である養生思想に基づくものである。
『周礼』の維持制度では食医を病気の治療医よりも上ランクに置き、
『黄帝内経』では上医は未病を治し、下医は已病を治すといった言葉からも同じ考えに由来するものである。
時を同じくして、ヨーロッパにおいては『ディオスコリデス本草(ギリシア本草)』という薬物書が作成された。
ここでは植物は自然形態学的な観点から分類され、収載されている。
それに対し、中国本草の三分類は人間本位の薬効分類である。
この好対照は自然を主体に置いた西洋の分析的科学的思考法と、
人間中心主義的に分類・認識しようとした東洋思想を如実に反映したものと考えられる。
『神農本草経』には薬物の配合に関する説明もある。
君臣佐使 (くんしんさし)、そして七情といった考え方である。
これら君臣佐使・七情、三品分類は漢方医学独特の考え方である。
西洋の薬物学ではこのような薬物の複合作用といった点には関心が払われず、
単味の薬を規準として薬効薬理や治療法が検討された。
これに対し、中国伝統医学では単味の薬物は一素材とし、治療はあくまで複合薬剤の処方単位の考えで行われた。
西洋の薬学は生薬単味からさらに単一の有効成分の抽出へと努力が積み重ねられ、
それが分かれば次に天然物成分の化学的合成、そしてドラックデザイン(新薬の開発合成)への方向へ進んだ。
一方、漢方医学は、生薬をいかに巧みに組み合わせ、優秀処方を作成するかという全く逆の方法論を選択した。
いかにも対照的である。
また、漢方には独特の薬の調剤法がある。
修治(あるいは炮炙)と剤型である。
修治や炮炙を行うことで薬効が変わり、同じ薬物構成でも剤型が異なると薬効も異なる。
漢方薬は古代からこういった工夫も積み重ねてきている。
本草学の継承と展開
簡単なまとめ↓
■ 『神農本草経』の継承と発展
📚 『神農本草経』の継承と発展(時系列表)
| 時代・人物 | 本草書名 | 内容・特徴 |
| 後漢末 | 『名医別録』 | 『神農本草経』と同数(365種)を追加 |
| 南朝・陶弘景 | 『神農本草経集注』 | 朱墨で『神農本草経』と『名医別録』を区別(朱墨雑書) |
| 唐代(659年) | 『新修本草(唐本草)』 | 勅撰、850種収録。『神農本草経集注』を基礎に増補 |
| 宋代(978~1082) | 『開宝本草』『嘉祐本草』『証類本草』 | 本草書の再整理・増補(最大で1744種) |
| 明代・李時珍 | 『本草綱目』 | 金元医学を統合した本草書の大成 |
- 『名医別録』(後漢末):365種追加収録。
- 陶弘景(南朝梁時代):『神農本草経』+『名医別録』を合体し、朱墨で区別(神農=朱書、名医=墨書)
- →『神農本草経集注』を編纂(以後の本草書の基幹に)
- 唐代(659年)『新修本草』(=唐本草):初の勅撰(天皇の命によって、編纂 すること)本草。850種収録。
- 宋代:印刷技術の発達とともに本草書が次々刊行
- 『開宝本草』(978年)劉翰
- 『嘉祐本草』(1061年)掌禹錫
- 『証類本草』(1082年頃)唐慎微(1744種収録)
- 明代:李時珍の『本草綱目』が総まとめとして成立
***
中国最古のバイブル的な薬学書『神農本草経』に続いて、
後漢末には別に365種の薬物を収載した『名医別録』という本草書が作られた。
そして『神農本草経』は紀元500年ごろに梁の美男子で医学を極め、
芸術の分野にも精通した陶弘景(とうこうけい)によって再整理された。
当時存在した『神農本草経』四巻本に基づき、『桐君採薬録』『雷公薬対』『呉普本草』『李当之本草』を参考にし、
神農本草経品365種、名医別録品365種の計730種を選定して新たに『神農本草経』三巻を校訂した。
陶弘景の『神農本草経』は神農の『神農本草経』の文は朱書し、
『名医別録』の文は墨書して区別した(朱墨雑書)という。
つまり、陶弘景は『神農本草(しんのうほんぞう)』と『名医別録(めいいべつろく)』を合体させて編纂し、
『神農本草経(六朝期)』を作成、その内容は以後の本草書において重視され、本文とされる。
また、陶弘景は『神農本草経(六朝期)』に自身で新薬や注を加え
『神農本草経集注』を私撰本草書として世に出した。
中国正統本草における基幹本として歴代校訂本草書に引き継がれた。
唐の顕慶4年(659年)には蘇敬ら儒官医官によって『新修本草』20巻が編纂された。
これは『本草経集注』を基本文献とし、新しい薬物と注を加えたもので全850種の薬品を収録。
中国王朝初の勅撰本草で『唐本草』とも称され以後の勅撰本草の規範となった。
宋代に入ると印刷技術の普及もあり、政府が続々と医薬書を校訂・刊行した。
978年に※尚薬奉御(しょうやくほうぎょ:皇帝の薬を管理する重職)である劉翰(りゅうかん)の『開宝本草』、
1061年に掌禹錫(しょううしゃく)の『嘉祐本草』、1082年ころには怪医とも呼ばれた唐慎微(とうしんび)の
『証類本草』が編纂された。
『類証本草』には1744種類もの薬物が掲載されている。
※日本において有名な漢方家の浅田宗伯は「尚薬奉御」 と名乗っていた。
「尚薬」とは官名で天子あるいは東宮の侍医をさす。
浅田宗伯は「侍医」という官に任官したのではなく、「拝診御用」という職に就任し、
「御用」制度(格式に縛られない任命方式)によって宮廷医に準ずる扱いを受けた。
現に『漢洋病名対照録』(1888 年(明治21年)発刊。
初めて「糖尿病」という病名を使用)では、
浅田宗伯は「滋明両宮尚薬奉御」の肩書で本書の校閲を担当していることを明らかにしている。
「御用」という名辞は宮中や官庁の用務をさし、戦前にはよく使用されていて、
「御用掛」という名辞も使用されることがあった。
この御用掛という慣例の制度は現在でこそみられないが、
戦前にはごく普遍的な人事採用の方法として広く用いられていた。
これによって定員や被採用者の資格を限定せず、
格式にしばられずに採用側の意向に即した方法として用いることができる利点をもったかなり融通無碍
(思考や行動に障害がなく自由でのびのびとした様)な方法であった。
そして明代には金元医学を取り入れた李時珍(りじちん)の『本草綱目』が作成された。
これら一連の本草書の編纂過程では、前代の本草書の文章には原則手を加えずに、
新たな注を加え編纂している。
そのため後の代の本草書にはそれ以前に編纂された本草書の注がそのまま残されていることになる。
参考文献:小曽戸洋. 漢方の歴史 中国・日本の伝統医学.大修館書店.2014

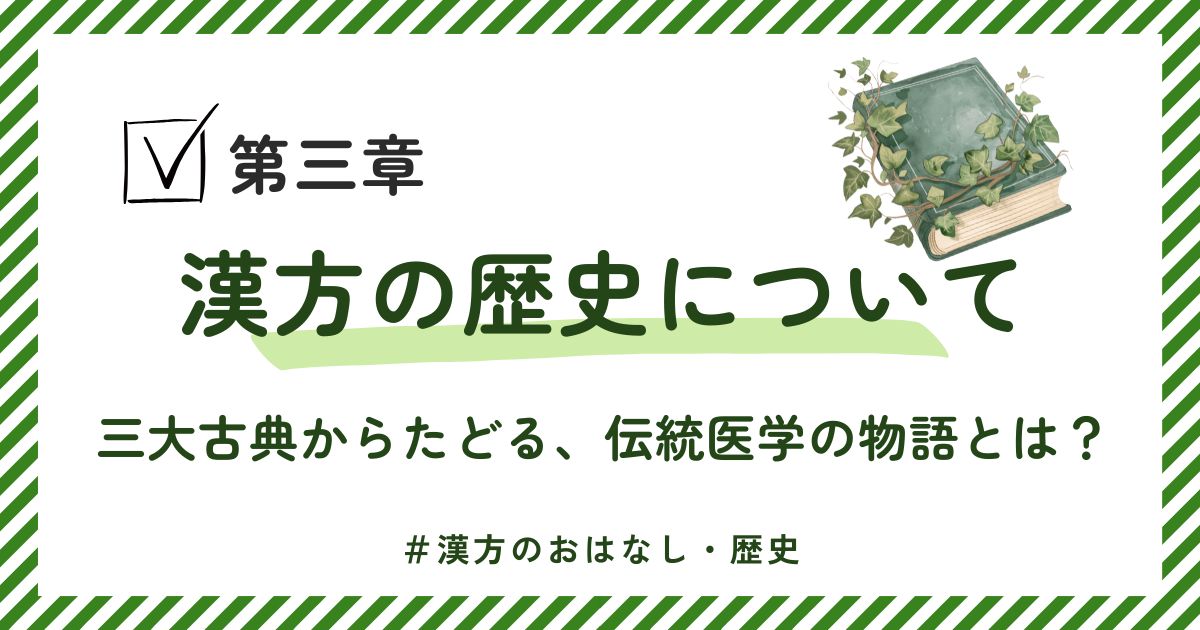
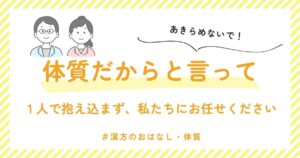
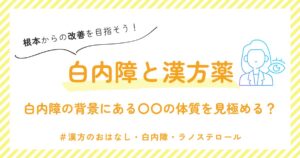
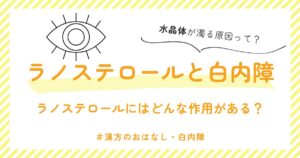
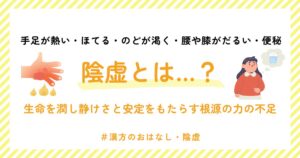
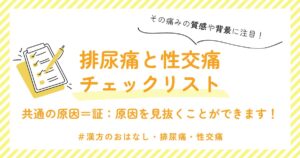
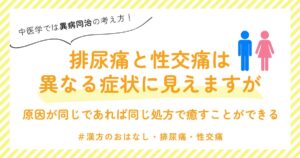
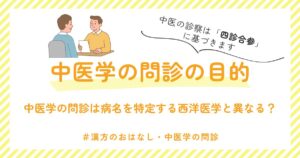
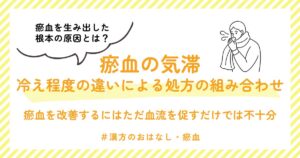
コメント