漢方の歴史について古代中国から遡っていくつかのシリーズで解説させていただこうと思います。
まず、第一回目に古代中国(今から約3000~2000年前)のお話しです。
今回の記事の概要をまず冒頭でご説明いたしまして、
続いて概要に記載している内容の詳しい説明を記載していきます。
簡単に歴史を知りたい方は序文だけをお読みいただき、
更に詳しく知りたい場合は目次よりご興味のあるタイトルをクリックしリンクへとお飛びください。
今回の概要
約3000年以上前の古代中国殷の時代から続く漢字文化。
このころから中国では疾病を意味する「疾」といった漢字が存在していた。
甲骨文字の研究において、殷王朝でこの文字は占いに使用された形跡が確認されたが、
このころから手当てといった医療行為が存在していたと考えられる。
そして春秋戦国時代(BC8世紀~BC3世紀)では名医「扁鵲」が活躍。
死んだ人をも生き返らせ、人を見ただけで病が分かるといった伝説を持つ。
扁鵲は数百年生きたとされ、このことからもこの時代に活躍された医師団を
ひとりの人物に当てはめていることがうかがえる。
周王朝の時代(BC11~BC3)ではすでに医師制度の制定がされており、医師の官職にランク付けもなされていた。
前漢(BC202年)の時代には医書の分類もされており、古代中国の時代から高度な医療技術があったことが分かる。
以上が古代中国(殷・周・春秋・戦国・前漢・後漢)の漢方の歴史についての概要です。
もう少し詳しく知りたい方は引き続きお読みいただけたらと思います。
特に、そもそも漢方とは何かといったところは漢方を学んでいる方でも混乱しやすい部分かと思いますが、
歴史から紐解きますとわかりやすいかと思います。
はじめに-東洋医学と漢方
東洋には三つの主要な医学文化がある
一.
ギリシア医学を基に発展したユナニ医学(グレコ・アラブ医学、イスラム医学)
二.
インドのアーユルベーダ医学
三.
中国医学(東アジア医学)
***
特に中国の伝統医学は古代から朝鮮半島や日本など東アジア全域に広がり、
日本では「漢方」と呼ばれ、中国では「中医学」、韓国では「漢医学」または「東医学」と称されている。
☑つまり漢方とは「中国の医術」のことであり、正確には日本人が中国から伝来した医術を指していった言葉。
そもそも漢方とは?
- 「漢方」は「漢=中国」「方=医術」を意味し、中国伝来の医術を日本で指す言葉。
- 「蘭方」はオランダ医学、「和方」は日本独自の医学を指す。
- 古くから「方技」「方術」は医術を意味し、『漢書』の「方技書」には『黄帝内経(こうていだいけい)』などが含まれ、針灸もその一部。
- 中国では自国の医学を「中医学」「国医」と呼び、日本の「漢方」とは区別される。
- 日本漢方の歴史は平安時代の『医心方』に遡り、鎌倉・南北朝・室町時代を経て江戸時代を通じて培われ、特に江戸時代には日本の漢方は独自の発展を遂げ、清朝の漢方(中国伝統医学)をも凌ぐ展開をみせたものである。
***
☑現在、日本において「漢方」といえば、日本化された中国伝統医学を指し、
現代日本で行われている伝統医学のことである。
正確には「日本漢方」と言い、また「中医学」といえば、現代中国で再整理され行われている伝統医学を指し、
本来の中国伝統医学と区別するために「現代中医学」と称す必要がある。
第一章 中国医学の形成
四大文明のひとつ、中国文明の最大の特徴は文明の伝統を一時として絶やすことなく受け継いできたことにある。
例のひとつに漢字がある。漢字の始まりは甲骨文字であり、
変化を伴いながら基本的には一貫した文字体系として3,500年もの間用いられ、今日に至る。
こういったことは他の文明には類を見ない。
このことからも中国伝統医学が東アジアで発展し、漢方・中医学として現代医療の中に活用されている事実も、
中国文明の悠久なる継続性を物語っている。
甲骨文字の発見と漢方
中国最古の歴史書、司馬遷の『史記』には大昔、夏とか殷といった王朝があったと記されている。
20世紀初め(1900年代)までは、学者の間では伝説上として信じられていなかった。
ところが、1899年、当時学者として最高位の王 懿栄(おういえい)によって甲骨文字が発見され、
古代王朝の遺跡が発掘されるに至り、殷王朝が史実として実在したことが認められるようになった。
このきっかけとなったのが漢方薬に使われる竜骨であった。
実際に文字の掘られた竜骨はカメの甲とウシの肩甲骨であったため、甲骨文字とされた。
これは殷王朝の占い師が占いの趣旨を刻み、裏を火であぶり、表にできた亀裂で吉凶を占うために使われていた。
殷王朝の遺跡の所在地は甲骨文字の研究によって、
河南省安陽(あんよう)の小屯(しょうとん)という村であることが判明し、
大規模な発掘作業によって巨大な殷王朝の遺跡が3,000年の歳月を超えて姿を現すことになった。
名医・扁鵲の伝説
簡単なまとめ↓
- 扁鵲は古代中国の名医で、脈診の達人。
- 病の進行段階に応じた治療法を説き、治療不能な「六不治の病」を示した。
詳細↓
古代中国きっての名医に扁鵲といった医師がいます。
中国最古の歴史書、司馬遷の『史記』の扁鵲倉公伝に扁鵲伝説は書かれており、
中国において扁鵲は名医の代名詞ともなっている。
扁鵲は病人を見ると一目で内臓の病変が見え、まさに超能力者であった。
世間においては脈診の達人として名を馳せた。
扁鵲伝説として、虢(カク)という国の皇太子が突然死した際に、仮死状態であると判断し、
扁鵲による薬と針の治療によって全快させた。
そのことによって人々は扁鵲は死人を蘇生させる術を持っていると信じた。
扁鵲は「当然生きるべき者の手助けをしたに過ぎない」といった。
斉の国に行った時には、王の桓侯(かんこう)の顔色を見たときに病気があることを知り、治療を進めた。
王はうそを言っていると言い、信じず治療を受けなかった。まもなく王は亡くなった。
扁鵲は「病気が体表にあるときは湯液や膏薬が効きます。
血脈に進行したときは針が効きます。
腸胃に進行したときは薬酒が効きます。
しかし骨髄にまで進んでしまうと、もう神様でもどうしようもありません。
王の病気は骨髄に入ってしまったのです。
扁鵲は患者を見て、こういった。以下のような患者の病気は治せない↓
- 驕り高ぶって道理をわきまえない人
- 身体を粗末にして財産を重んじる人
- 衣食の節度を保てない人
- 陰陽ともに病み、内臓の気が乱れ切った人
- 痩せ衰えて薬が服用出来ない人
- 巫(ふ・おがみやさん)を信じて、医を信じない人
これは扁鵲の六不治の病と言われる。
古代中国の医師制度
簡単なまとめ↓
- 『周礼』による医師の官職は食医(食事療法)、疾医(内科)、瘍医(外科)、獣医に分かれ、食医が最上位。
- 医師は技術によって上医・中医・下医に分類され、「未病を治す」ことが最も重要視された。
詳細↓
古代中国において周王朝の制度を記した古典『周礼(しゅらい)』(礼は制度という意)には医師の官職が認められ、
「医師は医の政令を掌り、毒薬を聚めて以て医事に供す』と規定。
①食医(食事療法医)
②疾医(内科医)
③瘍医(外科医)
④獣医といった四種の専門医を制定。
上の順ほど格が高い。予防医学を重視する中国らしい格付けである。
技量の程度による分類もある。上医(上工)・中医(中工)・下医(下工)といった区別である。
上工:望診・脈診・撮診の三つに熟練した医者、十人中九人治せる。
中工:二つに通じ、十人中七人は治せる。
下工:一つに通じ、十人中六人は治せる。
上工は未病を治し、已病を治さず(霊枢)」上級の医者は病状が発現しないうちに見抜いて治療を施すもので、
病状が悪化してからはじめて治療をするのはランクの低い医者だという意味である。
「未病を治す」という考えは中国医学古典の根底を貫くひとつの哲学思想である。
医書の分類(『漢書』芸文志より)
簡単なまとめ↓
- 方技書は「医経」「経方」「房中」「神仙」の四種に分けられる。
- 医経:医学総合理論書(例:『黄帝内経』)
- 経方:薬物中心の治療書(例:『傷寒論』)
- 房中:男性の性と養生に関する書
- 神仙:不老長寿や錬金術の書で、後に西洋科学にも影響を与えた
詳細↓
医学書の分類については 『史記』に次ぐ中国第二の正史(国家によって正式に作成された歴史書で、
前漢について記載があり、後漢の時代に編纂された)『漢書』芸文志に記載があります。
芸文志とは、当時の国家図書館の総目録であり、中国現存最古の図書目録である。
今から二千年前に中国にはどのような書物が存在し、どの様に分類されていたかが分かる。
当時医学のことを方技といい、医書を方技書といった。
漢書芸文志では方技書を「医経」「経方」「房中」「神仙」の四種類に大別。
「医経」とは医学総合理論書。『黄帝内経を』をはじめ、『扁鵲内経』も分類される。
「経方」とは薬物を中心とした具体的治療書・処方集。
『五臓六腑痺十二病方』『婦人嬰児方(ふじんえいじほう)』『神農皇帝食禁』『湯液経法』が分類。
漢方医学の聖典とされる『傷寒論』も経方書とされ、『湯液経方』の延長線上としてある。
「房中」とは男性権力者の為に書かれたセックス養生書。陰道とも。『容成陰道』が収録される。
平安時代に宮中医官を務めた鍼博博士・丹波康頼(たんばやすより)が撰した、
日本において最古の医学書『医心方』(紀元984年)にも記載がある。
いかに精力を消耗せずに楽しみ、逆に相手から精力を吸収するか、そしていかに優秀な子孫を残すかといった術が記されている。
「神仙」とは不老長寿の神仙術を記載したもの。
『上聖雑子道』が収録。錬金術も神仙に属す。錬金術も神仙目的で発している。
この知識はシルクロードを経て欧州に伝えられ、ルネッサンスの洗礼を受け、現代の化学に繋がった。

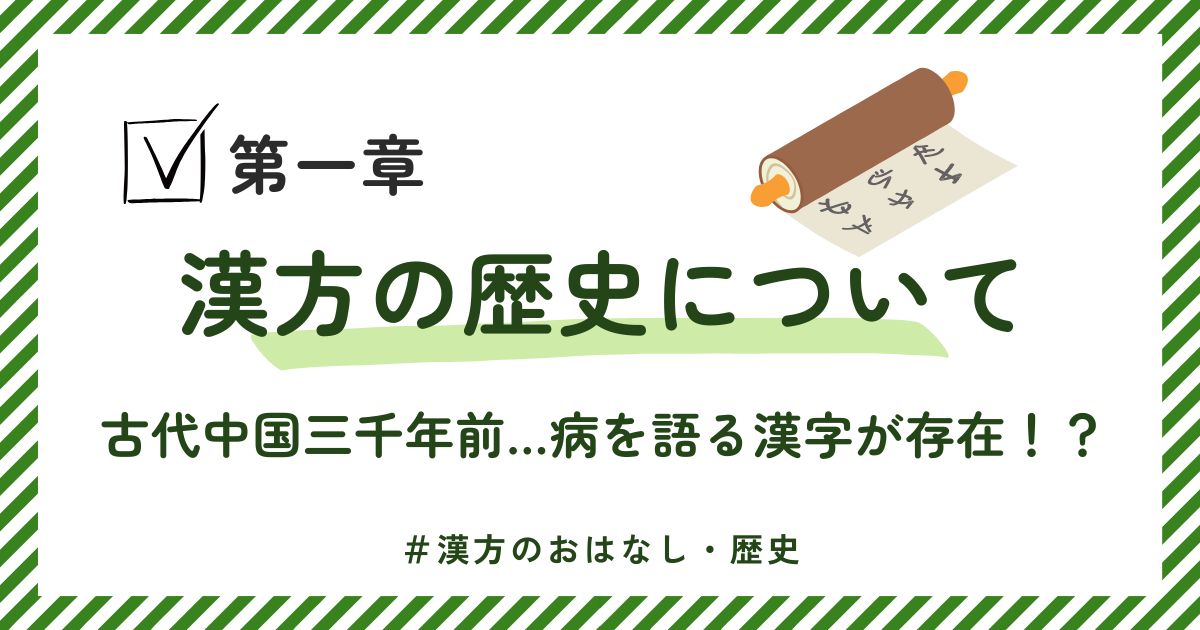
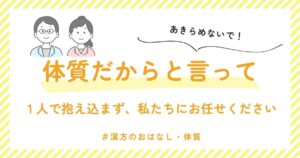
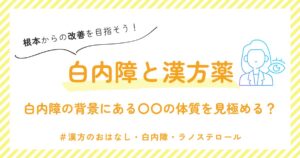
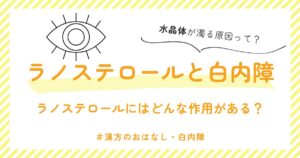
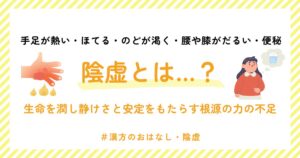
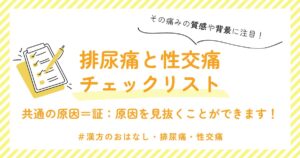
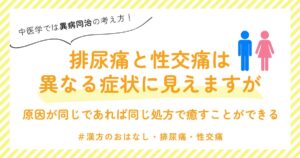
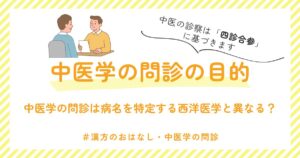
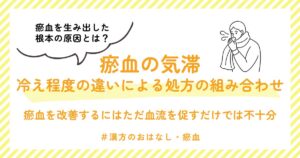
コメント