1.飲酒はエストロゲンの濃度を高める
アルコールは肝臓で代謝され分解されます。また、体内で作られたエストロゲンも
肝臓で処理されます。飲酒により、肝臓はアルコールの分解という仕事が増えるため、
エストロゲンの代謝がスムーズにいかなくなり、過度な飲酒は肝臓の機能を障害します。
その結果、エストロゲンが分解されにくくなり、体内に蓄積してしまいます。
そのため、高度な肝機能障害をきたす肝硬変を患っている男性では、女性のような
乳房がみられることがあります。肝臓の病気がなくてもアルコールはエストロゲン値を
上昇させるようです。閉経後の女性では卵巣からエストロゲンはほとんど分泌されませんが、
相当量の男性ホルモン、特にテストステロンが分泌されています。
テストステロンは脂肪組織でエストロゲンに変換されます。よって、閉経後女性では、
脂肪の総量とエストロゲン値は相関していることになります。アルコールは脂肪組織における
テストステロンからエストロゲンへの転換を刺激します。そのため飲酒習慣のある女性は
量的には少ないですが、エストロゲンの補充療法を行っているような状態です。
***
長期的に飲酒が続くと『湿熱』がたまりやすくなります。
身体の中に余分な“湿”と“熱”がこもる状態です。
この状態を『肝胆湿熱(かんたんしつねつ)』といい、主な症状は、
口が苦い・イライラ・じゅくじゅくした赤み・黄疸などの症状が現れます。
また、過度なアルコールの摂取は身体の中の『陰』を消耗してしまいます。
***
☑エストロゲンが枯渇すると
一般に、女性では心臓病や脳卒中の頻度は閉経後に急に高くなります。この主たる理由は
エストロゲンが枯渇することであります。ある研究によりますと、閉経後女性が1週間に
グラス3~6杯程度のワイン相当のアルコールを摂取すると、わずかではありますが
エストロゲン値が増え、心臓病や脳卒中のリスクを低下させることがしめされています。
しかも、この程度のアルコール摂取は、骨や肝臓に対して悪影響を与えません。
とはいえ、アルコールの個人への影響は個々で異なり、心臓病や脳卒中の予防として
アルコールが推奨されているわけではありません。
2.アルコールはエストロゲン様物質を含む
ワイン、バーボン、ビールなどのアルコール飲料水には、発酵によるさまざまな副産物を
含んでおり、それゆえに特有のうま味や香りをもたらしています。しかし、副産物の中には
植物由来のエストロゲン様物質の変化したものが存在していて、これらもなんらかの作用を
及ぼすことが考えられます。特に、身体が作るエストロゲンがほとんど枯渇している閉経後の
女性では、アルコール飲料水に含まれるエストロゲン様物質は、エストロゲンとして作用
していることが確認されています。しかし、この作用は必ずしも有害な作用とはいえず、
動脈硬化を遅らせる善玉コレステロールを増やすといういい側面もあります。
3.飲酒の不妊への影響
妊婦や授乳婦は、赤ちゃんに対する影響からアルコールを控えるべきであることは
よく知られています。では、アルコールがエストロゲン値を変化させるとしたら、
アルコール愛飲者では不妊となるのでしょうか。
女性の場合では、毎日グラス1杯のワイン(アルコール約15g)なら、まず問題ない
と思う人が多いでしょうが、その程度の量から摂取量に比例して妊娠しにくくなります。
また、ワイン、ビール、ウイスキーなどアルコール飲料の種類ではなく摂取した
アルコール総量に比例して妊娠の確立が低下するようです。
☑生殖機能にどのように作用する?
アルコールは、生殖機能にどのように作用するのでしょうか。
アルコールによって排卵が障害されたり、排卵が起こったとしても排卵後に
妊娠の成立や維持に不可欠な黄体ホルモンが十分に分泌されなくなります。
アルコールは男性にも生殖能力に影響を及ぼします。例えば、5日間連続して
アルコールを摂取するとエストロゲンは増加して、エストロゲン/テストステロン比は
上昇するという研究報告があります。さらに注目するべきことに、飲酒により精子の状態も
やや低下する傾向がみられます。精子への影響はアルコール、またはその代謝産物が精子に
作用することや、エストロゲンの増加のため精子の産生が障害されることなどが考えられます。
また、飲酒量が増えるほど男性は不妊になりやすいです。ただし女性と比較して、男性のほうが
アルコールによる生殖能の低下は禁酒により回復するということです。男性は、精子が作られる
全期間は約3か月であるため、少なくとも妊娠を計画している3か月前には飲酒量を制限したほうが
いいでしょう。


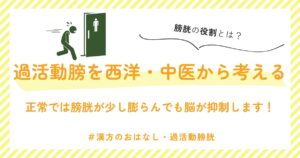
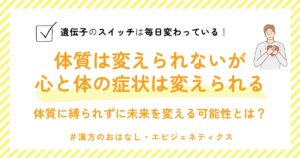
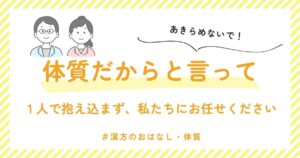
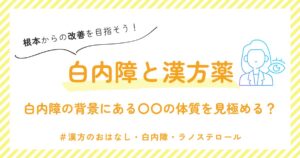
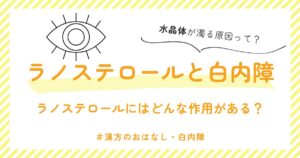
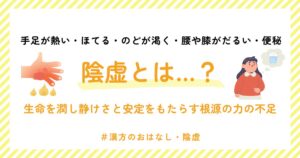
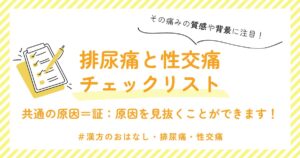
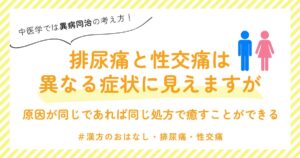
コメント