1.月経はエストロゲンにより生じる
卵巣機能が正常な女性では、月経は約28日間隔で起こります。
月経開始日を月経周期の第1日目とすると、排卵は14日目あたりに起こります。
月経時にはエストロゲンは最も低値となり、その後排卵に向けて徐々に上昇します。
排卵直前に急峻に増加してピークを形成し、排卵時にはいったん低下します。
なお、妊娠可能期間は排卵前の3~4日間から排卵後1日間であります。
排卵後、エストロゲンは排卵直前のピーク時ほどではないが、再び上昇します。
エストロゲンとともに、黄体ホルモンが分泌され、そのため体温が0.3~0.5℃
高くなります。(高温相)
月経が開始する数日前からエストロゲンと黄体ホルモンはともに低下し、
月経時にはエストロゲンは最低値となり、黄体ホルモンはきわめて低値となります。
このようにエストロゲン分泌の特有な変動により正常な月経が起こります。
正常な月経とは28日前後で周期的にみられ、3~7日間持続し、総出血量は
50~250グラムであります。
卵巣機能が障害されると月経の周期が短縮されたり、逆に伸びたりして、
さらに定期的にくる月経の出血のパターンとは異なってきます。
卵巣機能が高度に障害されると無月経になります。
***
中医学では女性は14歳になると天癸(てんき)が満ち、月経がはじまるとされています。
『肝・腎・脾』の役割が月経と深く関わっていて、この3つのバランスが崩れると
月経が乱れる主な原因と考えられています。
***
2.月経周期に伴うエストロゲンの変動
エストロゲンは女性の生殖器のみならず、情動や全身の代謝にも影響を及ぼします。
そのため女性の気分や体調は月経の時期によって変化します。
ヒトでも一般にエストロゲンのみが作用しているときは、女性は活動的になります。
しかしエストロゲンに黄体ホルモンが加わると、活動は抑制される傾向にあります。
動物では食欲などの要求が満たされると快感を覚えます。
このように快感を呼び起こす食物は報酬といえます。
また異性との接触も報酬となります。
ヒトでは金銭、物質、名誉なども間接的に快感に結びつくので報酬となります。
ヒトや動物の脳内には快感をもたらした行動を繰り返すことを制御する中枢があります。
これを報酬系とよび、生命維持や向上心・社会活動を促すことなどに役立っていますが、
一方では薬物中毒などにも関連します。
報酬系はエストロゲンにより活性化され、黄体ホルモンにより制御される。そのため
排卵前には報酬系は最も高まっています。
報酬系は活動を高めることになり、女性ではエストロゲンがピークになる
排卵前に活動性が高まる傾向があります。
また女性アスリートでは、月経周期と運動のパフォーマンスとは特に関係しないという選手が多いが
20%程度ではあるが、月経が終了して排卵に至るまでの時期は体調がよく、
ベストな結果が出せると述べている選手もいます。
さらに排卵前には食事の摂取量が低下する傾向にあり、カロリー量にして
250~600キロカロリー程度摂取量が低下するといわれています。
☑月経前の食欲の変化
排卵後はエストロゲンとともに黄体ホルモンが分泌されるが、
食欲は一般的には増進します。
黄体ホルモンが増加するのは排卵後、あるいは妊娠中です。
これらの時期は、いずれもエストロゲンも同時に分泌されています。
つまり、黄体ホルモンはエストロゲンの食欲抑制効果を打ち消すように
作用しています。
また、甘いものや塩辛いものといった味の好みも月経周期によって
変化することがあり、エストロゲンや黄体ホルモンの作用が
ここにも関係しています。
3.無月経になる理由
エストロゲンを分泌する臓器は卵巣であるが、卵巣は脳の視床下部から出るホルモンが
下垂体に作用し、そこから卵巣機能を調節するホルモンが分泌されることで、
エストロゲンを分泌して、排卵が起こります。
したがって、視床下部、下垂体、卵巣のいずれの障害でもエストロゲン分泌が障害され
月経が不規則、あるいはまったくみられなくなります。(無月経)
体質的に月経が規則的にみられず、3~6か月間程度月経がない女性もいます。
このような女性の多くは、多嚢胞性卵巣症候群と診断されます。
初経以来、月経が不規則の傾向が持続しています。
約10人にひとりにみられ、多くは体質と考え病気ととらえる必要はありません。
また不規則な生活、肥満、糖尿病、肝臓や腎臓などの内臓疾患、甲状腺疾患なども
無月経の原因になりえますが、エストロゲンはある程度分泌されていることが多いです。
***
中医学では多嚢胞性卵巣症候群は複数の体質の乱れが重なった状態と
考えられます。
体質に合ったケアをして身体の巡りや卵巣の働きをサポート
することが改善への第一歩です!
***
エストロゲン分泌が著しく低下する無月経は、無理なダイエットなどにより
3~6か月間で体重が10%以上減少した場合や、
身近な人との離別やその他の高度な心身のストレスを経験した場合などがあります。
同じ視床下部の障害による無月経であっても上記の両者を見分けることが重要です。
なぜなら後者の状態が長期化するようであればエストロゲンの補充が必要だからです。
他方、エストロゲン分泌がある程度保たれている無月経では、排卵がないため
黄体ホルモンが分泌されず、エストロゲンのみがだらだら分泌されているこのような状態では
子宮の内腔を覆っている子宮内膜という組織が過度に増殖し、それは子宮にとって
好ましくなく、半年以上放置すると子宮体がんのリスクが高まるので適切な
治療が必要です。
下垂体や卵巣が障害されている無月経では、一般にエストロゲン分泌は高度に
障害されることが多いです。
下垂体の障害の場合には、下垂体の腫瘍や炎症が原因のこともあり、
早急な診断と治療を要します。
卵巣の障害に関しては、抗がん剤の使用などで起こるものは回復の可能性はありますが、
自然に生じたものは早晩閉経状態に移行します。
妊娠が難しい状態ではありますが、卵巣の機能障害が進んでいない状態では
治療により妊娠は不可能ではありません。
なお妊娠の可能性は卵巣以外の原因で無月経に至った女性では
ホルモン製剤などの治療により十分に期待がもてます。

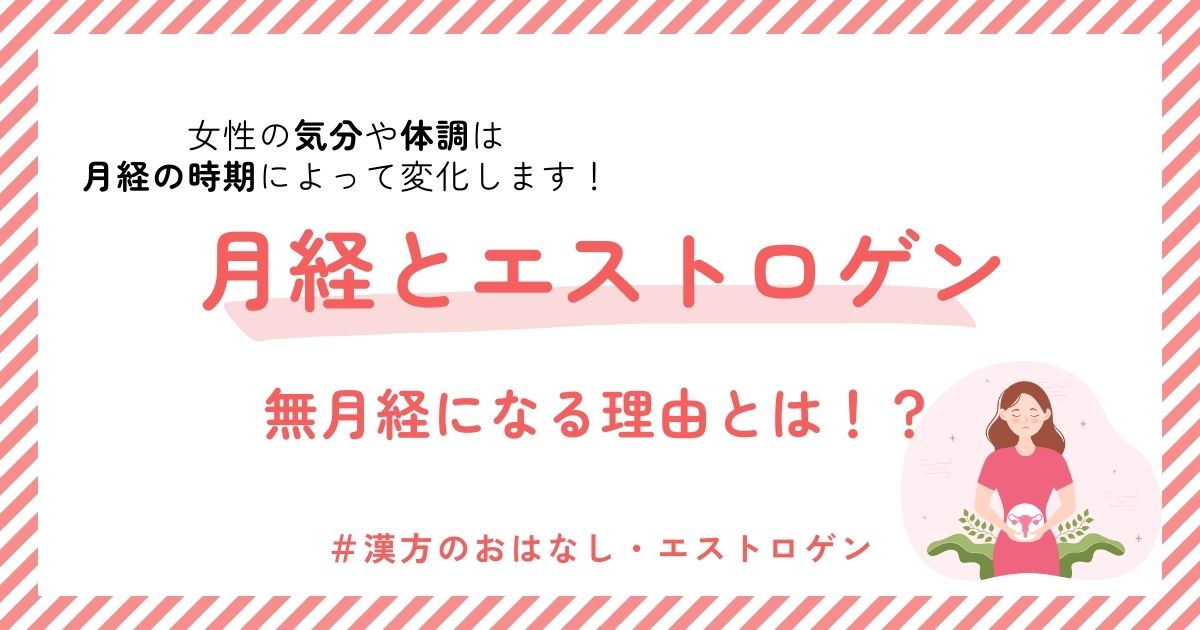
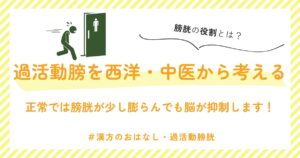
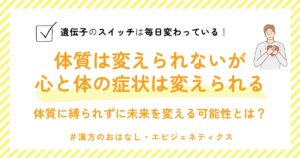
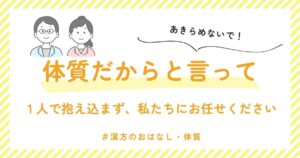
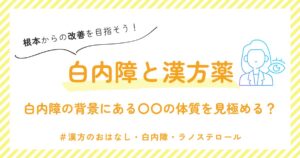
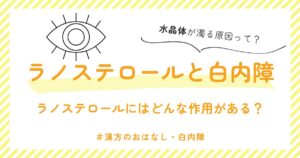
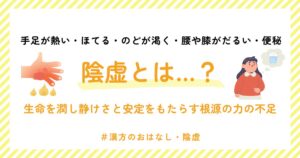
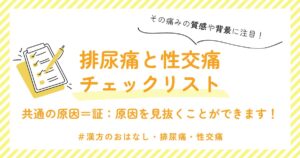
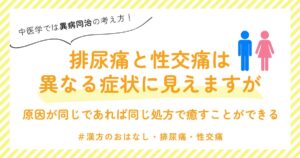
コメント