適応症(大柴胡湯を使用する主な疾病)
- 胆石症・胆嚢炎
- 肝炎・肝機能障害
- 胃炎・消化不良
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍
- 高血圧症・高脂血症
- 肥満症・脂肪肝
- 便秘を伴う頭痛
- 神経症・ストレス性疾患
目次
用いる根拠
大柴胡湯は、「少陽病」+「陽明腑実証」に適応する方剤です。
- 少陽病(半表半裏):寒熱が入り混じり、体内に熱がこもるが、完全には外に発散できていない状態。
- 陽明腑実証(胃腸の熱と滞り):胃腸に熱がこもり、便秘や腹満、腹痛などを引き起こす状態。
大柴胡湯は、小柴胡湯の「少陽病」の調和作用に加えて、「陽明腑実証」の熱や滞りを瀉下する作用があるため、
上記の疾患に応用されます。
方剤の方意と各生薬の配合目的
方剤の方意
- 和解少陽(柴胡・黄芩):少陽病の寒熱を調整し、炎症を鎮める
- 清熱瀉下(大黄・枳実):胃腸の熱を冷まし、腸内の停滞を解消
- 疏肝理気(半夏・生姜):肝気の停滞を解消し、消化機能を整える
- 健脾消滞(白芍):胃腸の機能を高め、腹部の緊張を緩和
各生薬の配合目的
| 生薬 | 目的 | 作用 |
| 柴胡(さいこ) | 和解少陽 | 熱を冷まし、気を巡らせる |
| 黄芩(おうごん) | 清熱燥湿 | 炎症を抑え、余分な熱を除去 |
| 半夏(はんげ) | 理気化痰 | 胃腸の調子を整え、痰湿を取り除く |
| 生姜(しょうきょう) | 温中止嘔 | 胃腸を温め、嘔吐を防ぐ |
| 大黄(だいおう) | 瀉熱通便 | 腸の熱を冷まし、排便を促す |
| 枳実(きじつ) | 破気消積 | 消化を促し、停滞を解消する |
| 白芍(びゃくしゃく) | 養血柔肝 | 筋肉の緊張を緩和し、痛みを和らげる |
まとめ
異病同治の視点で見た場合
大柴胡湯は小柴胡湯よりも実証向け
肝胆系の炎症や胃腸の熱を伴う疾患に広く応用
例えば、「胆石症」と「肥満症」は一見関係なさそうですが
どちらも「肝気の滞り+胃腸の熱のこもり」によって悪化するため
大柴胡湯が適応されるのです。
ご相談お待ちしています。

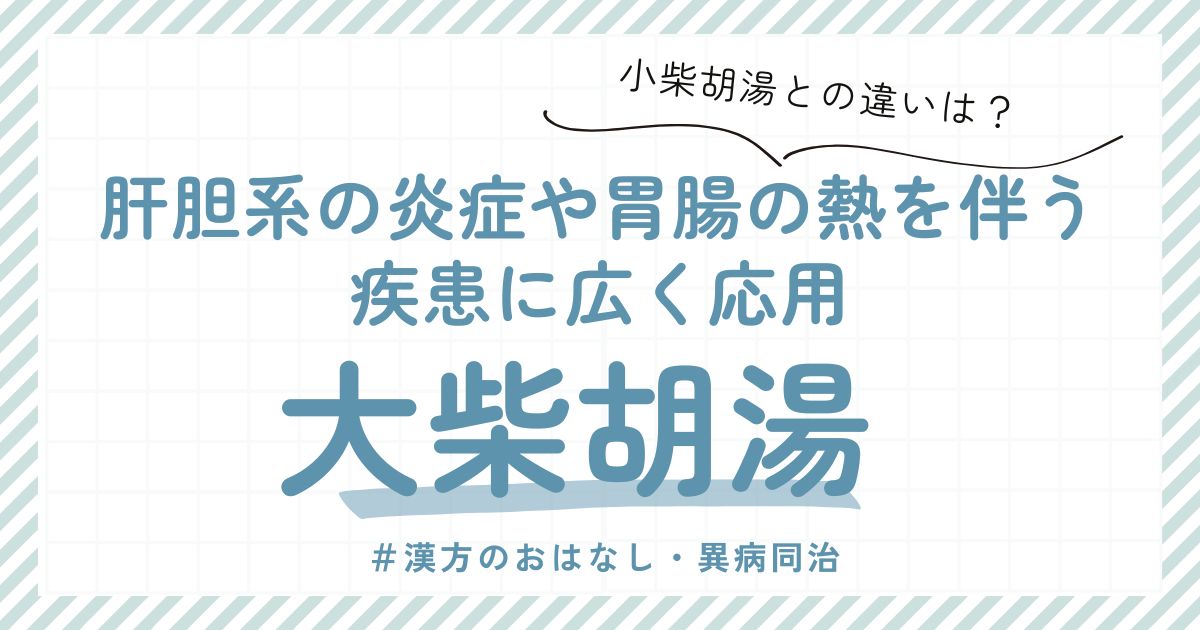
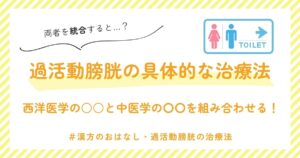
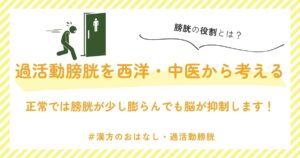
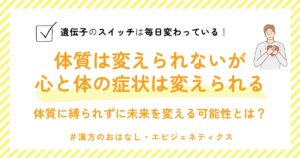
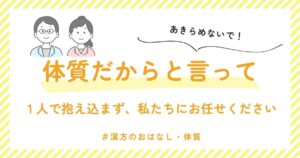
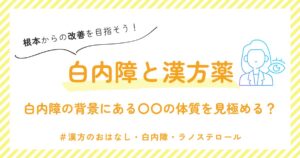
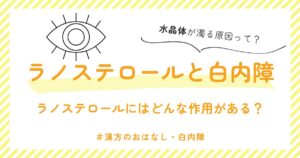
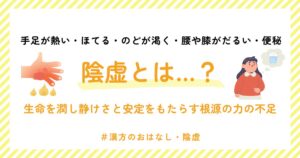
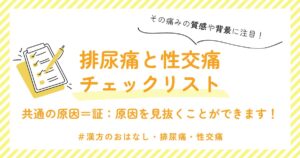
コメント