瘀血は、血の流れが滞った状態を指しますが
その原因は一つではありません。
中医学では、気の停滞による『気滞血瘀』と、血の不足による『気虚血瘀』という
二つのタイプが知られています。
今回は、特に『血虚』がどのようにして瘀血を生むのか
その機序に焦点を当ててみます。
例えば
川の水が流れない理由は
岩にせき止められることもあれば
水そのものが足りないこともあります。
人の体も同じです。
血の流れが滞る『瘀血』には
気の停滞によるものと
血の不足によるものがあり、それぞれ異なる背景を持っています。
「気虚血瘀」と「血虚瘀血」は、どちらも瘀血を生じますが
瘀血の成り立ちの出発点(原因)が異なります。
- 区別:気虚血瘀 vs 血虚瘀血
- 血虚から瘀血が生じる3つの機序
- 血虚から瘀血が生じる3つの機序
- 現代医学的対応 でお伝えします。
1.区別:気虚血瘀 vs 血虚瘀血
| 種類 | 原因 | 瘀血が生じる主因 | 特徴 |
| 気虚血瘀 | 気虚 → 推動力の低下 | 「血を動かす力」が弱まり、血行が停滞 | 倦怠感、無力感、面色淡白、舌質淡紫、脈弱 |
| 血虚瘀血 | 血虚 → 血量不足・血液粘稠・血脈失養 | 「血の質と量」が低下し、血脈の流通が阻害 | 皮膚乾燥、唇・爪の色が淡、舌淡で瘀点あり |
2.血虚から瘀血が生じる3つの機序
① 血量減少 → 血流緩慢 → 局所鬱滞
- 血虚とは「血の量が少ない」「血の栄養力が低い」状態。
- 血管内を流れる血量が減ると、流速が落ち、局所に滞りが生じやすくなります。
- 特に「細い毛細血管」や「四肢末端」などでは、血流停滞=瘀血が形成されやすい。
➡ 例)産後・大出血後・慢性病後に血虚→血流が停滞→瘀血による疼痛や紫暗舌。
② 血液粘稠化(血虚=血の濃縮・質変化)
- 血虚が長引くと、血中の液体成分(津液)も不足し、血液が「濃く・粘る」ようになります。
- この粘稠化した血は流れが悪く、血管壁への摩擦抵抗が高まり、停滞を生む。
中医的には「陰血不足→津枯血濃→瘀滞」と表現します。
現代医学的に対応づけると「脱水・血液濃縮・微小循環障害」に近い。
③ 血脈失養 → 脈道収縮・狭窄 → 血流阻害
- 血は脈を養い、脈は血を運ぶ。
- 血虚が続くと、脈管そのもの(血管壁)が滋養されず、柔軟性を失い硬くなる。
- 結果として血行がスムーズに通らず、瘀血が生じる。
これは「血虚による脈道不利」「血脈枯槁→瘀血成形」と言われる機序です。
現代的には「血管内皮障害・微小循環の狭窄」などに相当します。
3.血虚から瘀血が生じる3つの機序
| 分類 | 典型症状 |
| 全身症状 | 顔色淡白や萎黄・めまい・不眠・動悸・疲労感 |
| 瘀血症状 | 刺痛(しびれるような痛み)、舌に瘀点・爪甲暗紫 |
| 舌診 | 淡紫舌、瘀斑、苔薄 |
| 脈診 | 細弱・澀(せつ) |
4.現代医学的対応
| 中医学の概念 | 現代医学的対応 |
| 血虚 | 貧血・血漿量減少・低アルブミン血症・血管栄養低下 |
| 血虚による瘀血 | 血液粘稠化・微小循環障害・血流遅延・局所虚血性障害 |
血液の「量」と「質(粘度・蛋白量)」が低下し
循環が滞ると微小血栓や局所虚血を生じます。
これが中医学の「血虚瘀血」に相当します。
5.まとめ
| 項目 | 内容 |
| 発端 | 血虚(血量・栄養低下) |
| 過程① | 血流緩慢(量的不足) |
| 過程② | 血濃化(質的変化) |
| 過程③ | 血管硬化(環境変化) |
| 結果 | 血が滞り、瘀血形成 |
| 治法原則 | 養血活血法(補血+活血) |
このように、血虚による瘀血は、血の量や質が不足することで
血の流れが停滞することで生じます。
単に『流れが悪い』のではなく、
『流れる血も足りない』という視点が重要です。
だからこそ
活血だけでなく補血の処方が必要となるのです。
血は命の水。
その水が足りなければ、流れは止まり、よどみが生まれます。
瘀血を解くには、ただ流すのではなく、まず満たすこと。
中医学の知恵は
足りないものを補い
滞ったものを動かす
その両輪で成り立っているのです。

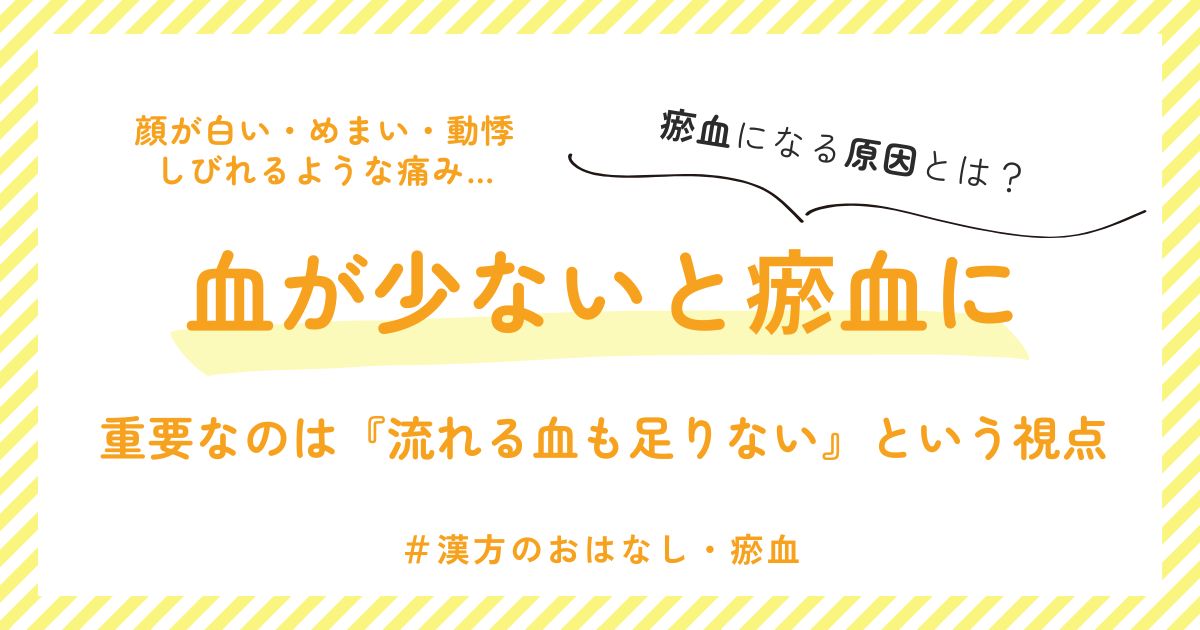
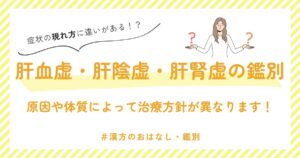
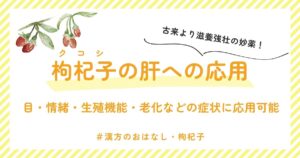
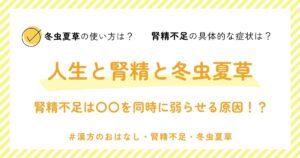
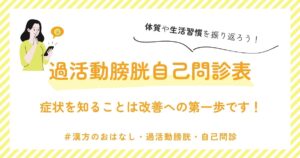
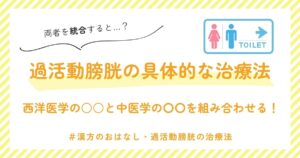
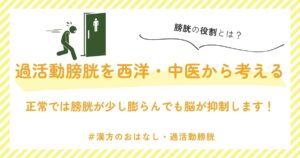
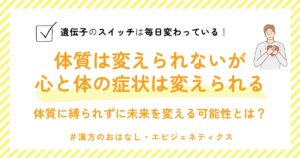
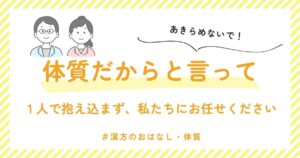
コメント