1.妊娠の成立には母体卵巣由来のエストロゲンが不可欠
排卵・受精・卵の子宮への輸送などの妊娠に先行するさまざまな現象、
および初期胚の着床・発育などの妊娠初期の過程ではエストロゲンは
重要な役割を果たしてます。
また、卵や初期胚の受け皿である子宮側から妊娠の成立過程を見てみると
エストロゲンは子宮内膜に作用して着床可能量を増やすことで妊娠初期の過程が
順調に進行するのを助けています。
妊娠が成立すると、排卵後に形成された黄体は妊娠黄体となり、
そこからエストロゲンが黄体ホルモンとともに分泌されます。
妊娠7~8週ぐらいまでは母体の卵巣由来のエストロゲンが黄体ホルモンとの
巧妙な共同作業のもとに妊娠を継続させます。
2.妊娠8週以降は胎盤でエストロゲンが産生される
妊娠7週では、母体血中のエストロゲンや黄体ホルモンは母体の卵巣と
将来胎盤を構成する絨毛細胞(胎盤)との双方から分泌され、
妊娠8週以降になると絨毛細胞が主要な産生部位にとって代わります。
なお、絨毛細胞は胎盤を構成する中心的な細胞であり、妊娠12~14週で
形態的・機能的に胎盤といえるものが出来上がります。
母体毛血中のエストロゲンは妊娠の進行とともに増加し、妊娠末期まで上昇傾向にあります。
エストリオールは卵巣からはほとんど分泌されないため、
非妊時にはごくわずかしか存在しませんが、妊娠すると約1,000倍に上昇します。
その結果、母体血中に存在するエストロゲンの60~70%はエストリオールとなります。
なお非妊時における主なエストロゲンであるエストラジオール、エストロンも
妊娠により50~100倍程度増加します。
妊娠中のエストロゲンの産生部位は胎盤であり、そこで作られたエストロゲンの
大部分は母体側へ分泌されますが、一部は胎児にも移行します。
そのため、胎児血中のエストロゲン濃度は母体血中に近い濃度となっています。
3.妊娠中に増えるエストロゲン
☑胎児の副腎・肝臓と胎盤との共同作業で作られる
妊娠中は胎盤でエストロゲンが作られ、母児ともに高濃度のエストロゲンに
さらされていることを述べましたが、正確にいえば胎児の副腎で作られる
ステロイドホルモンをもとにして胎盤でエストロゲンが合成されるということになります。
胎児の副腎は出産近くになると5g(ほぼ腎臓の大きさに相当)ほどあり、
ぼぼ成人の副腎に匹敵する大きさであります。
体重比にして胎児の副腎は成人より20倍程度大きいことになり、胎児では副腎は
最も大きい内分泌臓器です。
そのため、胎児の副腎のホルモン分泌量は安静時の大人の2~7倍にもなります。
胎児の副腎の大部分を占めるのは、内層にある胎児層(fetal zone)であり、
外層には成人層(adult zone)があります。
出生後には胎児層は急速に変性委縮し、生後一か月で出生前の50%以上が退縮し、
生後1年後には消失します。
☑DHEAとは
胎児期の副腎が多量に分泌するホルモンは、デヒドロエビアンドロステロンサルフェート(DHEA-S)であります。
副腎の胎児層はまずデヒドロエビアンドロステロ(DHEA)を合成します。
これは弱いが男性ホルモン作用があります。
DHEA-Sに変換されることで男性ホルモン作用はさらに弱くなります。
DHEAがDHEA-Sに変換される理由のひとつは、DHEAが直接血中に移行することによる
女児の男性化を防いでいると考えられます。
あるいは、DHEA-S自体にDHEAとは異なった胎児に対する重要な生理作用があることが
考えられます。なお、胎児副腎では、妊娠8~10周ですでにDHEAの産生が確認されています。
胎盤で作られるエストロゲンとして、エストリオール以外にエストロンや
エストラジオールがあります。エストリオールは、すべて胎児の副腎から出るDHEA-Sを
もとにして合成されます。エストロンやエストラジオールの60%は、
胎児の副腎由来のDHEA-Sを利用しています。また、胎盤における
エストロゲンの産生は、胎盤から出る絨毛性ゴナドトロビン(hCG)により促されています。
4.無脳症ではエストリオールが低い
下垂体を含む脳全体が欠損している無脳児では、下垂体から副腎を刺激するホルモンである
ACTHが分泌されていないため胎児副腎が委縮します。
そのため、DHEA-Sの分泌量はごくわずかとなり、その結果エストオールはほとんど作られません。
しかし、先に述べたように母体の副腎で作られたDHEA-Sが胎盤に運ばれて、
エストラジオールになるため、無脳児ではエストリオールはごくわずかでも、
エストラジオールはかなりの高濃度で存在しています。

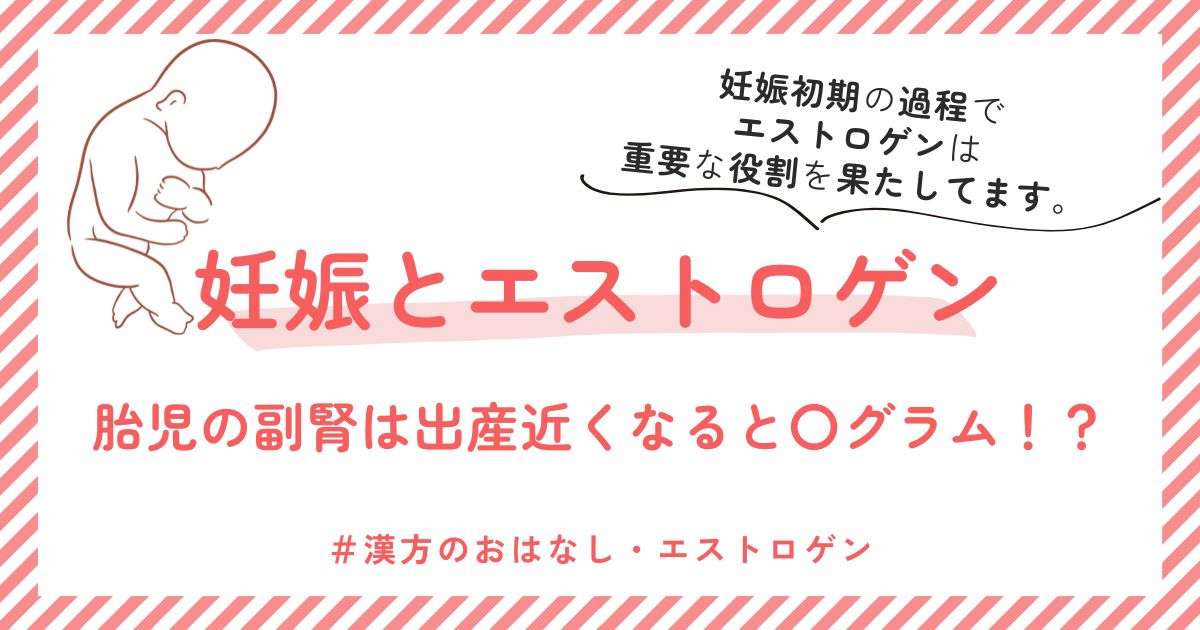
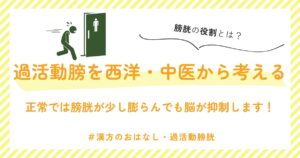
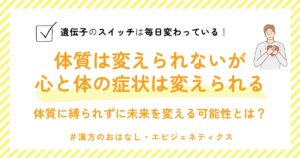
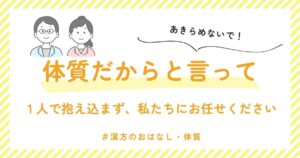
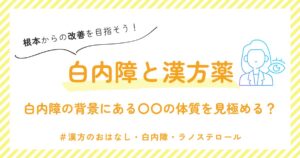
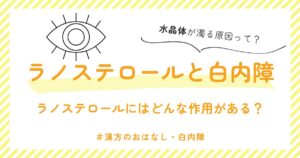
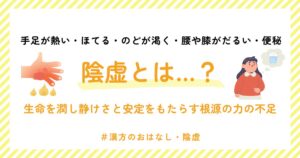
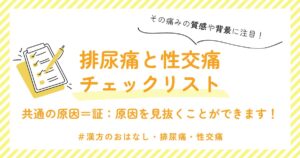
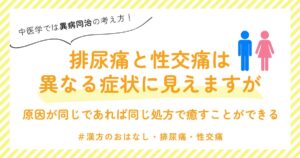
コメント