漢方の歴史について古代中国から遡っていくつかのシリーズで解説させていただこうと思います。
第回二目に古代中国(今から2000年前)のお話しです。
今回の記事の概要をまず冒頭でご説明いたしまして、
続いて概要に記載している内容の詳しい説明を記載していきます。
簡単に歴史を知りたい方は序文だけをお読みいただき、
更に詳しく知りたい場合は目次よりご興味のあるタイトルをクリックしリンクへとお飛びください。
今回の概要
第一回目では、殷王朝の遺跡の発掘とともに3000年もはるか昔の古代中国では
すでに漢字文化が存在し病についての漢字も存在していた事、
そして2000年前の春秋戦国時代に活躍された医師団(扁鵲伝説)や、
その時代から医師を専門分野による分類や、能力による分類もなされ、
医書についても分類がされていた事をご説明いたしました。
これらのことから中国では殷・周・春秋・戦国時代を通じて膨大な経験と知識の集積によって
中国特有の医学が形成され、この後に続く漢代になり、さらに体系化され基盤が確立されていった。
今回は古代の漢方の知識がより体系化された漢代についてです。
前漢の時代には、既に漢方薬を使用して病を治療していた。
それを示すのが時の王様利蒼(りそう)の妻の遺体が2000年の時を超えて発見されたことに由来する。
この妻の遺体は馬王堆(まおうたい)というお墓から発見された。
この女性の遺体は死後2000年以上経っていたのにも関わらず死後直後かと思うほど生々しいものであり、
この婦人の手には漢方薬がにぎられていた。
そして馬王堆から出土した書からは、古代中国の医書の四つの分類「医経」「経方」「房中」「神仙」
すべての分野の医書が揃っていた。
第二章 よみがえる古代医学の遺物
二千余年前の貴婦人と漢方薬
簡単なまとめ↓
1971年、中国湖南省長沙の馬王堆で前漢初期の三つの墓が発掘され、
一号墓からはほぼ死後直後の状態で保存された貴婦人の遺体が見つかった。
彼女は紀元前193年頃の利蒼の妻で、九つの病気にかかっており、
死因は胆石症から誘発された心筋梗塞と推定された。
副葬品には漢方薬も含まれ、彼女の手にも握られていた。
詳細↓
20世紀(1990年代)後半、中国において考古学的発見があった。
1971年の暮れ、中国湖南省の省都・長沙の東の郊外にある馬王堆(まおうたい)
といった墳丘(遺体を葬るために土を積み上げて作った丘)を掘り起こすと、三つの墓が発掘された。
この墳丘は前漢初期の墓で、馬王堆一号・二号・三号漢墓と名付けられた。
一号墓からは死後直後かと思うほど生々しい婦人の遺体が発見された。
三号墓からは紀元前の医学書が大量に出土した。
この貴婦人の遺体は地下20メートルの墓室に四重の棺に大量の古代の遺品とともに埋葬されており、
その中に死後服用するための漢方薬も含まれ、また貴婦人の手には漢方薬が握られていた。
この貴婦人は紀元前193年に長沙の王侯となった利蒼(りそう)という人の妻で、
身長154センチ生前の推定体重は70kgで贅沢な食生活の為に肥満しており、年齢は50歳前後であったとされる。
今を遡る2200年近く前の遺体である。
理解剖の結果、貴婦人は九つの病に侵され、死因は胆石症に誘発された心筋梗塞の発作によるもの、
副葬された漢方薬からリウマチ疾患に起因する心臓疾患によるものと推定された。
このことは河南省安陽(あんよう)の小屯(しょうとん)の殷墟の発見と並び20世紀最大の成果と言われる。
両方ともに漢方薬と深いゆかりを持つことはとても面白い。
そして馬王堆の発掘されたこの長沙という土地は奇遇にもその400年後『傷寒論』を著した張仲景が
太守(古代中国の群における長官)となった場所である。
出現した古代の医学書
簡単なまとめ↓
三号墓からは2200年前の大量の古代医学書が出土。
医書は「医経」「経方」「房中」「神仙」の四分野にわたり、『十一脈灸経』など気血や経絡の理論が記されていた。
発掘された帛書(はくしょ:帛ハクと呼ばれた絹布Kに書かれた書。)は折本形式で、
冊子本の原型が戦国時代に存在したことを示した。
詳細↓
馬王堆漢墓の三号墓は夫妻の三十代の息子のものであり、ここからは大量の古代医書が出現された。
実に2200年も前の医療の様子を伝える現物としての超一級の資料である。
馬王堆出土の書からは、古代中国の医書の四つの分類「医経」「経方」「房中」「神仙」
すべての分野の医書が揃っていた。
「医経」に属するものとして、『十一脈灸経』(『足臂十一脈灸経』(そくひ:足とうで)と
『陰陽十一脈灸経』のテキストからなる。)がある。
中国医学では気血の運行経路に十二経脈というものが設定されている。
気血は十二経脈を順に巡り、身体にエネルギーや栄養を補給している。
陰陽をそれぞれ三つに分け三陰三陽とし、かつ臓腑理論と結び付けることから生まれた。
三陰三陽を手足に配当すると6×2=12となる。
一方五行理論での臓腑は五臓五腑で10の数字である。12と10ではうまく対応しないため、
五臓(肝・心・脾・肺・腎)五腑(胆・小腸・胃・大腸・膀胱)に新たに心包という臓と三焦という腑を加え、
六蔵六腑とし、手足の三陰三陽と対応させた。
馬王堆の十一脈灸経を見ると心包経が無い。
これは五臓五腑にまず三焦の腑を加えて五臓六腑とした時点での理論である。
心包経を加えて六蔵六腑とする以前の発展段階のものである。
今でも人体の内臓を「五臓六腑」というのはその名残である。
他に『五十二病方』といった処方集(処方だけでなく灸法や呪法も記載)や、
脈診の書、養生の書、補益・小児・毒虫に関する雑方書、産科の書、呼吸保健法の書、房中術の書が出土した。
『導引図』といった体操によって気を巡らせ病を除く医療運動法が描かれた帛画も出土した。
ちなみに紙は紀元105年に蔡倫(さいりん)が発明した。
それ以前の書物は絹(帛書:はくしょ)や、竹(竹簡)、木(木簡)に書かれている。
馬王堆医帛の復元研究
簡単なまとめ↓
発掘された帛書(はくしょ:帛(ハク)と呼ばれた絹布(ケンプ)に書かれた書。)は折本形式で、
冊子本の原型が戦国時代に存在したことを示した。
詳細↓
馬王堆漢墓発掘当時の中国は文化大革命のさなかで、何重にも折り畳まれた帛書の剥離作業は慎重さを欠き、
復元作業を過ったと思われる個所が多くある。
そこで小曽戸洋先生が五年の歳月をかけて帛書の解析を行った。
そしてこの帛書は蛇腹状に折り畳まれた折本の形で保管されていたことが分かった。
絹の帛書は木竹簡と同様巻物であったとされ、
紙も同じく巻物形式でのちに折本(御朱印帳のような蛇腹状の本)となったとされており、
冊子本は後代に発明されたとされるが、今回の復元により冊子本ははるか昔の戦国時代に存在したことが
明らかとなった。
新出の医学史料
簡単なまとめ↓
湖北省や甘粛省などでも古代の医学書や医療器具が発見され、古代中国医学の実態が明らかに。
2013年には「天回医簡」と呼ばれる扁鵲の医書と経絡人形が出土し、
漢代の医学が高度に発達していたことが判明。「黄帝内経」はこの「天回医簡」の解説書である可能性が高い。
詳細↓
1983年に発掘された湖北省江陵県の張家山漢墓から医書(竹簡)『脈書』と『引書』が発見。
『脈書』は馬王堆帛書の『陰陽十一脈灸経』に相当。
『引書』は馬王堆帛書の『導引図』の説明書であり、馬王堆医書を補完する資料となった。
1972年には甘粛省の武威県旱灘坡(ぶいけんかんだんは)の漢墓から
『武威医簡』と称される後漢前期の医方書の現物も発見された。
木簡・木牘(もくとく:木簡より幅のある札)の類で、種々の病に対する治方が記載され、
薬物療法や鍼灸療法に関する記述もある。
1968年、河北省満城県の中山王・劉勝(りゅうしょう)の墓からは、
古代医療の実際を示す医療器具が出現した。金針や銀針、銅盆(銅性の鍋)などが発掘された。
1992年に四川省の綿陽の前漢墓(紀元前179~141年)から黒漆塗りの木製人形(経絡人形)が出土し、
これには左右対称に各九本と背部正中線に一本の朱漆線が引かれている。
2013年には成都の老官山前漢墓から、扁鵲による天回医簡(医書)と、
綿陽のものより進化した経絡経穴人形が出土した。
※四川省人民政府新聞弁公室が2023年に会見を行い、「天回医簡」は散逸したとされていた
古代中国の春秋戦国時代における伝説的な名医である扁鵲の「医書」である可能性があるという。
竹簡のほとんどは望診と脈診を合わせた診察や鍼・灸の原理に関する内容で、
扁鵲の医学分野とも一致している。
さらに、「五色脈診」の内容も発見されており、それはまさに、「扁鵲」を象徴する医学分野となっている。
『天回医簡』は、扁鵲ともう一人の医師・淳于意(倉公)が記した医書で、
その内容は漢の時代の主流医学だったことを証明。
そこに書かれている内容から、漢の時代の医学レベルは非常に発達しており、
『中成薬(中医薬・生薬製剤)』を使用していたほか、
望診と脈診を合わせた診察の詳細な体系もあったことが分かった。
これにより2000年以上昔にはすでに比較的整った医学の理論や臨床体系があったことが証明された。
中国最古の医学書と呼ばれている「黄帝内経」は、「天回医簡」の解説書である可能性があることも発見した。
「黄帝内経」との比較研究では、「黄帝内経」は「経典」ではなく、
経典の解説書で、教師が学生に講義する際の資料のようなものであるとみられ、
その「経典」が「天回医簡」ではないかとみられている。
※以下引用元:
参考文献:小曽戸洋. 漢方の歴史 中国・日本の伝統医学.大修館書店.2014
KN. 2000年以上昔の医学書「天回医簡」は伝説的な名医「扁鵲」の著作か 2000年以上昔の医学書「天回医簡」は伝説的な名医「扁鵲」の著作か. 2023. https://j.people.com.cn/n3/2023/0421/c94475-20009383.html.人民網.2025

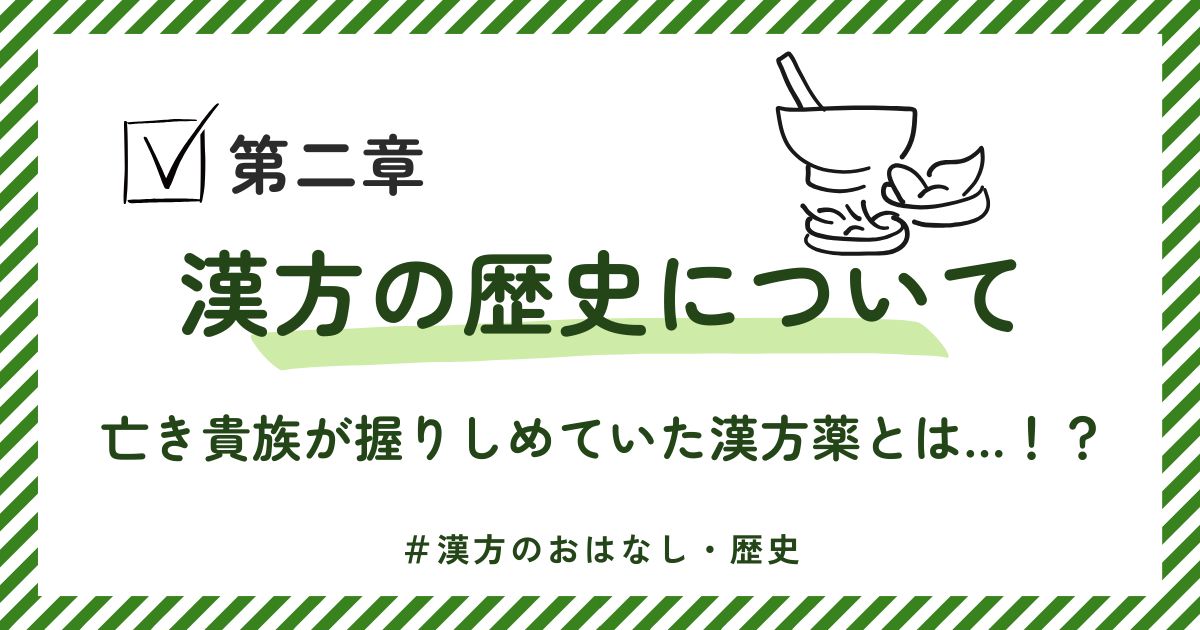
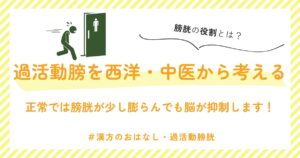
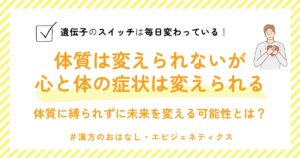
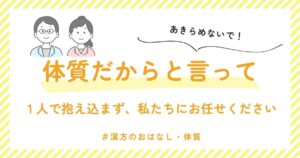
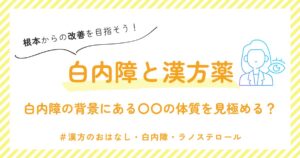
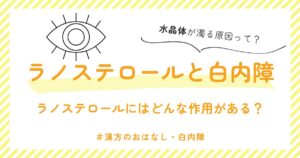
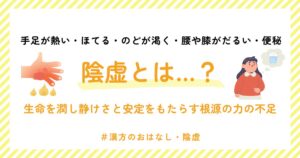
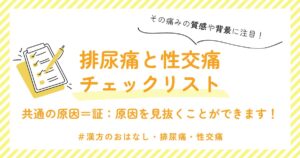
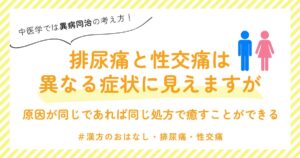
コメント