中医学では
鬱病は 「鬱証(うつしょう)」
「気機の失調」「気血陰陽の不足」「痰飲・瘀血の阻滞」 により発症すると考えられます。
目次
Ⅰ. 肝気鬱結(気滞による抑うつ)
(ストレスや情志の変動が原因で起こるタイプ)
症状
- 気分が落ち込みやすい、ため息が多い
- ストレスを感じると悪化
- 胸や脇が張る感じがする
- 食欲不振、消化不良
- 女性では生理不順、PMSが強い
- 舌質:淡紅、舌苔:薄白または薄黄、脈:弦
病理
- ストレスや情緒の不安定さが肝気の巡りを阻害し、気滞を生じる
- 気が滞ることで精神的に抑うつ状態となる
悪化条件
- ストレスや精神的緊張で悪化
- 過労や睡眠不足で悪化
問診のポイント
- ストレスを感じやすいか?
- 胸の張りやため息が多いか?
- 食欲の変化があるか?
Ⅱ. 心脾両虚(気血不足による抑うつ)
(精神的な疲労や過労により発症するタイプ)
症状
- 気力がなく、集中力低下
- 不眠(特に夢をよく見る)、健忘
- 食欲不振、疲れやすい
- 顔色が青白く、めまいがする
- 舌質:淡、舌苔:薄白、脈:細弱
病理
- 脾の気血生成能力が低下し、心血が不足することで精神状態が不安定になる
- 長期の思慮過多やストレスが脾を傷つけ、鬱状態を引き起こす
悪化条件
- 過労・長時間の考えごとで悪化
- 食欲低下時に悪化
問診のポイント
- 疲れやすいか?
- 集中力が低下していないか?
- 食欲不振や消化不良があるか?
Ⅲ. 陰虚火旺(陰虚による抑うつ)
(陰液不足により心火が過剰になり不安感が強いタイプ)
症状
- 焦燥感が強く、不安がある
- 夜になると気持ちが不安定になる
- 口の渇き、寝汗、微熱
- 動悸、不眠(特に入眠困難)
- 舌質:紅、舌苔:少、脈:細数
病理
- 心陰虚により、心火が過剰になり、不安・焦燥感が強まる
- 腎陰虚を伴うことが多く、寝汗や微熱も生じる
悪化条件
- 夜になると悪化
- ストレス・過労・暑さで悪化
問診のポイント
- 夜の不安感があるか?
- 寝汗や口の渇きがあるか?
- 焦燥感やイライラがあるか?
Ⅳ. 瘀血阻滞(血の巡りが悪くなる抑うつ)
(血流の滞りが原因の抑うつ)
症状
- 精神的にふさぎ込みやすい
- 刺すような頭痛や肩こりがある
- 顔色が暗く、皮膚がくすむ
- 手足の冷え、舌下静脈怒張
- 舌質:紫暗、舌下静脈怒張、脈:渋または結代
病理
- 血瘀により、脳や心の血流が悪くなり、精神不安定が生じる
- 気滞が悪化して瘀血化することも多い
悪化条件
- 寒冷環境で悪化
- 運動不足で悪化
問診のポイント
- 冷え性か?
- 顔色が暗くないか?
- 舌下静脈が膨れていないか?
☆まとめ
| タイプ | 特徴 |
| 肝気鬱結 | ストレスが原因の抑うつ |
| 心脾両虚 | 気血不足の抑うつ |
| 陰虚火旺 | 不安・焦燥感が強い |
| 瘀血阻滞 | 血流不良による抑うつ |
Ⅴ. 気滞痰鬱の特徴
主な症状
- 気分が落ち込み、思考がはっきりしない
- 胸が詰まる感じがする(胸悶感)
- のどに「何か詰まった感じ」(梅核気)
- ため息が多い
- 痰が多く、粘る
- 身体が重だるく、集中力が低下
- 食欲が低下し、胃がつかえる感じ
- 舌質:胖大(腫れぼったい)、舌苔:白膩(べたついた苔)、脈:滑または弦
病理(発生のメカニズム)
- ストレス・感情の抑圧 → 気の流れが滞る(気滞)
- 気滞が続くと、痰湿が発生 → 体内に停滞して気の流れをさらに阻害
- 気滞+痰湿の相互作用により、心の活動が抑制され抑うつ症状が悪化
Ⅱ. 気滞痰鬱の悪化条件
- ストレスや感情の抑圧 で悪化
- 湿気の多い環境 で悪化(痰湿が増える)
- 運動不足や過食(特に脂っこいものや甘いもの) で悪化
- 睡眠不足 で悪化
Ⅲ. 気滞痰鬱の問診ポイント
五臓
- 肝 → 肝気鬱結による気滞が主因
- 脾 → 脾虚により痰湿が発生
- 心 → 心神の不安定化(精神的な鬱状態)
五志(感情)
- 抑圧感が強い、イライラしやすい
- 怒りっぽいが、感情を表に出せずに内にこもる
六淫(外因)
- 湿邪(湿気)が影響しやすい
- 天候が悪いと気分が落ち込む
七情(内因)
- 情緒の抑圧が主な原因(特にストレス・怒り・悲しみ)
陰虚・陽虚
- 陰虚:明確な陰虚症状(寝汗、口渇など)は少ない
- 陽虚:明確な陽虚症状(冷え、無気力など)は少ない
痰飲
- 痰が多く、のどに詰まる感じ(梅核気)
- 身体が重だるく、頭がぼんやりする
瘀血
- 血瘀の症状(刺すような痛み、舌下静脈怒張)は少ないが、長期化すると血瘀に移行することもある
Ⅴ. 気滞痰鬱の治療ポイント
① 気を巡らせる
- ストレスを減らし、リラックスする習慣をつける
- 適度な運動(ウォーキングやヨガなど)を取り入れる
② 痰湿を取り除く
- 消化を助ける食事を心がける(脂っこいもの・甘いものを控える)
- 湿気の多い環境を避ける
③ 肝と脾のバランスを整える
- ストレスを軽減する(気を巡らせる)
- 胃腸の調子を整える(痰湿を減らす)
★気滞痰鬱のまとめ
| タイプ | 特徴 |
| 気滞痰鬱 | のどの詰まり、胸の圧迫感、ストレスによる鬱 |
🔍 最後に
- 気滞痰鬱は「気の流れの滞り」と「痰湿の停滞」が主な原因
- ストレス管理や食事、運動で気の流れを良くすることが重要
ご相談お待ちしています。

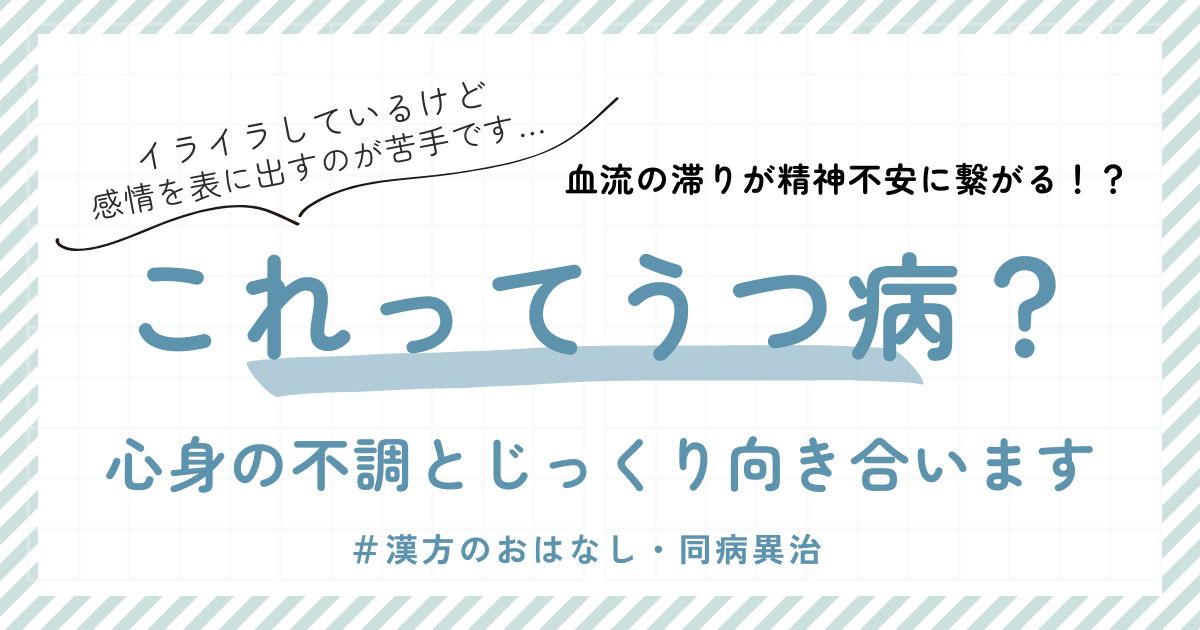
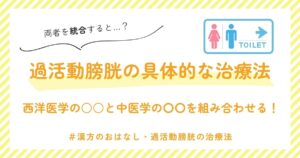
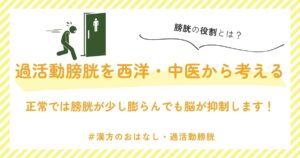
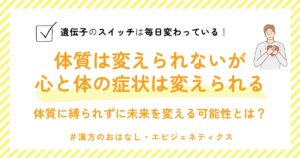
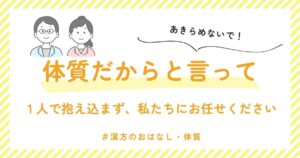
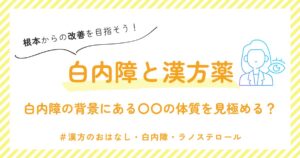
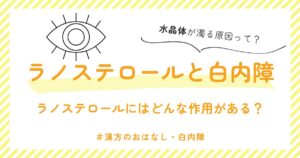
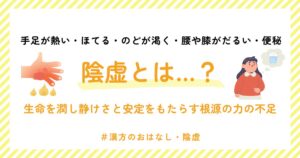
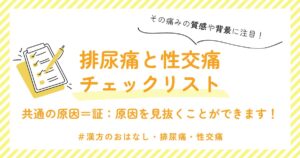
コメント