金縛りとは?
入眠時(睡眠開始時麻痺)又は覚醒時(覚醒時麻痺)に、一時的に体を動かせなくなる現象
意識はあるのに、体がまったく動かせない状態になるため、不安や恐怖を感じる事
レム睡眠と金縛りの関係
金縛りは**レム睡眠(REM睡眠: Rapid Eye Movement Sleep)**と深く関係しています。
(1)レム睡眠の特徴
- 夢を見ることが多い
- 脳は覚醒状態に近い(活発に活動している)
- 筋肉は完全に弛緩している(運動抑制がかかる)
- 急速眼球運動(Rapid Eye Movement)が起こる
(2)レム睡眠中の運動抑制
レム睡眠では、脳幹の「橋延髄系」が運動ニューロンを抑制し、全身の筋肉が弛緩
これにより
夢を見ている間に体が動いてしまわないようにする仕組み:運動麻痺が働いている。
(3)金縛りが起こる原因
金縛りは、
レム睡眠から覚醒する際に、脳は起きたのに「運動麻痺」の解除が遅れることで発生
- 夢を見ている途中で急に目覚めると、まだレム睡眠の運動抑制が残っているため、
- 体を動かせない状態になります。
- 視覚や聴覚が覚醒しているため、幻覚(誰かが上に乗っている感じ、声が聞こえるなど)を伴うこともあります。
金縛りが起こりやすい要因
金縛りは、睡眠リズムの乱れやストレスが関与すると考えられています。
原因として考えられるもの:
- 睡眠不足や不規則な睡眠(レム睡眠が異常に増える)
- 過労やストレス(自律神経が乱れ、睡眠の質が低下)
- 仰向け寝(仰向けのほうが金縛りが起こりやすい)
- 過度な夢見(レム睡眠の増加)
- ナルコレプシー(レム睡眠異常の疾患)
金縛りを防ぐ方法
金縛りを防ぐには、睡眠の質を改善し、レム睡眠の異常な増加を防ぐことが重要です。
対策
- 規則正しい睡眠習慣(毎日同じ時間に寝る・起きる)
- 睡眠時間をしっかり確保する(6〜8時間)
- ストレス管理(リラックスする習慣を持つ)
- 寝る前にスマホやPCを見ない(ブルーライトは睡眠の質を下げる)
- 仰向けではなく横向きで寝る(金縛りを防ぎやすい)
金縛りの中医学的な視点
中医学では、金縛りは「気滞(気の流れが滞る)」「陰陽の不調和」と関連すると考えられています。
- 肝気鬱結(ストレスによる気の停滞):心悸(動悸)、不眠、夢が多い
- 腎精不足(精力不足):疲労感、無力感、冷え
- 瘀血(おけつ)(血の巡りの悪化):頭が重い、首や肩のこり
対策(中医学的)
- 肝気を整える:柴胡疎肝湯、加味逍遥散
- 腎精を補う:六味地黄丸
- 瘀血を改善:桂枝茯苓丸、血府逐瘀湯
まとめ
- 金縛りは、レム睡眠中の運動麻痺が解除されずに起こる現象。
- レム睡眠の乱れが主な原因で、ストレスや睡眠不足で発生しやすい。
- 改善策は、睡眠の質を高めること。
- 中医学的には「気滞・腎精不足・瘀血」などが関与。
金縛りは怖いものではなく、睡眠リズムが乱れているサイン
生活習慣を見直すことが大切です!
夢遊病(睡眠時遊行症)と金縛り(運動麻痺)の違い
夢遊病(睡眠時遊行症):睡眠中に無意識に歩いたり行動したりする現象。
レム睡眠中は:夢を見ている間に体が勝手に動かないようにする仕組み(運動麻痺)が働く。
レム睡眠と運動麻痺(REM Atonia)
- レム睡眠(Rapid Eye Movement Sleep)は、夢をよく見る浅い睡眠の段階
- レム睡眠時は脳幹の「橋延髄系(Pons-Medulla system)」が
運動ニューロン(筋肉を動かす神経)を強く抑制 - その結果、全身の筋肉が弛緩し、体が動かない(運動麻痺)状態になる
夢遊病はノンレム睡眠中に起こる
- 夢遊病(睡眠時遊行症)はレム睡眠ではなく
「深いノンレム睡眠(特に睡眠第3・4段階)」で発生 - 脳はまだ深く眠っているが、運動を抑制する仕組みが完全には働かないため
体が動いてしまう - 夢を見ているわけではなく、無意識の状態で行動する(覚醒と睡眠の中間状態)
ポイント
夢遊病は、橋延髄系による運動抑制がうまく機能しないため、睡眠中でも体が動いてしまう
夢遊病とレム睡眠行動障害(RBD)の違い
- 夢遊病 → ノンレム睡眠中に起こる(夢を見ていない)
- レム睡眠行動障害→ レム睡眠中に起こる(夢に合わせて体が動く)
通常、レム睡眠では運動麻痺があるが、レム睡眠行動障害では
抑制がうまく働かず、夢に合わせて手足が動いてしまう(寝ながら殴る・蹴る)
まとめ
レム睡眠では橋延髄系が働き、運動麻痺によって体が動かないようにする
夢遊病はノンレム睡眠中に起こり、脳が深く眠りながら体だけが動く
**レム睡眠行動障害(RBD)**はレム睡眠中に起こり、夢に合わせて動いてしまう
レム睡眠の金縛り・レム睡眠のレム睡眠行動障害・ノンレム睡眠の夢遊病
この仕組みを理解すると
「なぜ夢遊病の人は動くのに、普通の人は夢を見ても動かないのか」が解り易くなります!
レム睡眠・脳の覚醒状態による浅い眠りや多夢の改善(中医学的アプローチ)
睡眠が浅い、夢が多い(多夢)という状態
中医学:五臓の「心」「肝」「脾」「腎」のバランスの乱れによるものと考えます。
問診では
五臓の状態、精神的な影響(五志・七情)、外因(六淫)
体質(陰虚・陽虚・痰飲・瘀血)を重視します。
浅い眠り・多夢の中医学的分類と治療
(1)心脾両虚(しんぴりょうきょ)—「心」と「脾」の気血不足による睡眠の浅さ病理
病理
- 「脾」は血を生み、「心」は血を主るため、脾の働きが弱まると血が不足し
心神を養えず不眠や多夢が発生する。 - 脾虚→気血不足→心神不安定の流れ。
症状
- 浅い眠り、夢が多い、寝ても疲れが取れない≒脾
- 動悸、顔色が悪い、食欲不振、胃もたれ、倦怠感、めまい
- 便がゆるい(脾虚)
悪化条件
過労、過度の思考、栄養不足、食事の不摂生
問診のポイント
眠りの質、夢の内容(多夢)、消化機能の状態、食欲、便通、疲労感の有無
(2)肝気鬱結(かんきうっけつ)—「肝気の停滞」によるストレス性不眠
病理
- 「肝」は気の流れを調節するが、ストレスや情緒の乱れにより気滞が起こると
「肝火」が生じ、心神をかき乱す。 熱上昇気流 心かき乱す - 肝気が脾を攻めると、脾虚も併発しやすい。肝気横逆
症状
- 浅い眠り、寝付きが悪い、悪夢
- イライラ、怒りっぽい、ため息が多い
- 頭痛、肩こり、胃の張り、月経不順
悪化条件
精神的ストレス、抑圧、不規則な生活
問診のポイント
ストレスの有無、怒りやイライラの頻度、食欲や消化の状態、頭痛や肩こり
(3)陰虚火旺(いんきょかおう)—「陰虚」による心熱・肝火の上昇
病理
- 陰虚(体液や精不足)により陰陽のバランスが崩れ、「虚熱」が生じ、心神が乱れる。
- 肝気鬱結はストレスによる肝火 実 陰虚火旺は陰虚による虚熱
- 夜間の体温上昇やのぼせが特徴的。
症状
- 浅い眠り、夜間覚醒、口や喉の渇き
- 手足のほてり、寝汗、ほてり
- イライラ、不安感
悪化条件
過労、長期のストレス、夜更かし、乾燥した環境
問診のポイント
- ほてりの有無、口渇、寝汗、夜間覚醒の回数
(4)痰熱内擾(たんねつないじょう)—「痰熱」による精神不安と多夢
病理
- 飲食の不摂生やストレスで「痰熱(不要な水分と熱の停滞)」が生じ、心神を乱す。
- 「胆気虚」による悪夢や不安感も関係。
- 肝気鬱結に脾虚が加わったと考えても分かりやすい
症状
- 夢が多い、浅い眠り、不安感
- 胸苦しさ、胃の不快感、吐き気
- 体が重い、頭がぼーっとする
悪化条件
油っこい食事、甘い物の過剰摂取、ストレス 甘生痰
問診のポイント
食生活の習慣、胃の調子、胸のつかえ感
(5)瘀血阻滞(おけつそたい)—「血の滞り」による不眠と多夢
病理
瘀血(血行不良)が起こると、脳の血流が悪化し、睡眠の質が低下する。
症状
- 寝付きが悪い、途中で目が覚める
- 頭痛、顔色がくすむ、冷え、肩こり
- しびれ、月経痛
悪化条件
冷え、運動不足、血行不良
問診のポイント
手足の冷え、月経の状態、頭痛や肩こりの有無
まとめ
| タイプ | 病理 |
| 心脾両虚 | 気血不足 |
| 肝気鬱結 | ストレス・気滞 |
| 陰虚火旺 | 陰虚による虚熱 |
| 痰熱内擾 | 痰と熱が心神を乱す |
| 瘀血阻滞 | 瘀血による脳血流低下 |
生活養生
- 睡眠のリズムを整える(夜更かししない)
- 食事を整える(油っこいもの、甘いものを控える)
- ストレスを溜めない(気血の巡りをよくする)
- 温める習慣(特に血行不良・瘀血タイプ)
「眠りの質」を改善するには、体質に合った漢方と生活改善が重要!
ご相談お待ちしています。

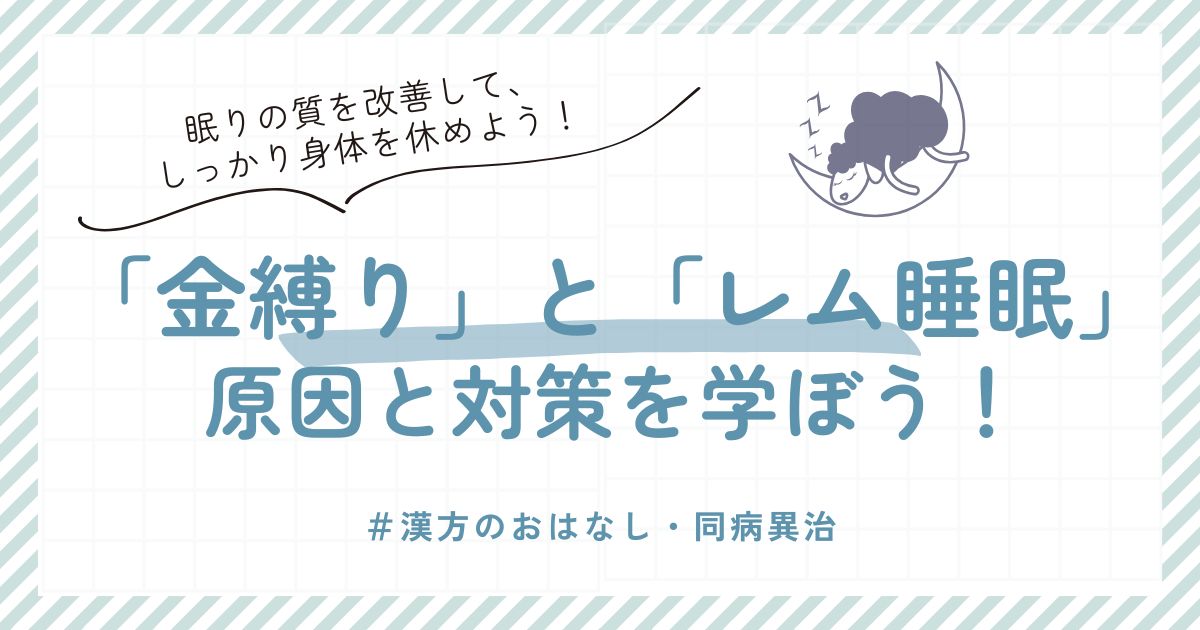
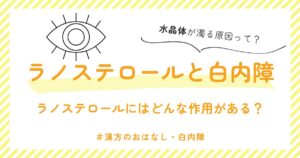
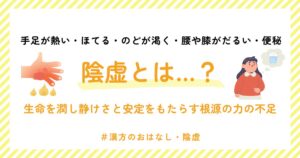
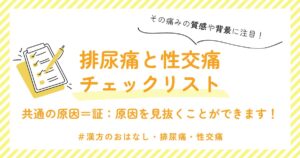
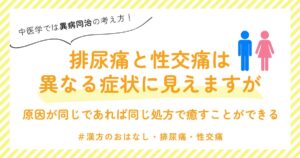
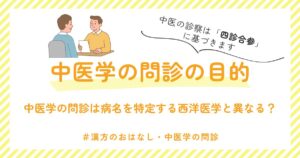
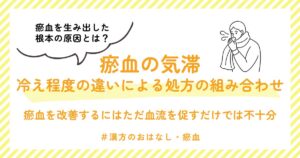

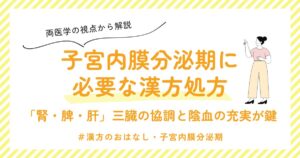
コメント