- 漢方薬の伝統的な服用方法で、乾燥した生薬を水で煮出して服用する薬。
- 「煎じる」とは、薬効成分を抽出するために弱火でじっくり煮ること。
- 古代中国から続く医療文化の象徴であり、現代でも根強い支持がある。
1.煎じ薬の特徴
吸収が良い
有効成分が水に溶け出すため、体内への吸収が早い
処方の柔軟性
患者様の体質や症状に応じて生薬の組み合わせや量を調整可能
香りと温度の力
煎じる過程で立ち上る香りや温かさが、心身に穏やかな作用をもたらす
手間がかかる
煎じる時間や器具の準備が必要で、忙しい現代人にはハードルになることも
2.よくあるご質問
| 質問 | 回答 |
| 煎じ薬はどれくらい煮ればいい? | 通常30分〜1時間。生薬によって異なるため、薬剤師の指示に従うのが安心です。 |
| 保存はできますか? | 冷蔵保存で1〜2日が目安。再加熱時は沸騰させず温める程度が理想。 |
| 味が苦手です… | 蜂蜜や黒糖を少量加えることで飲みやすくなります。 |
| 煎じ薬とエキス剤の違いは? | エキス剤は煎じ薬を濃縮・乾燥させたもので、手軽さが魅力。一方、煎じ薬はより細やかな調整が可能。 |
3.次のステップへ
煎じ薬は「手間の中に癒しがある」伝統的な治療法
体質や症状に合わせたオーダーメイドの処方が可能
4.煎じ役をお勧めする理由
煎じ薬の力で、健康を取り戻す
煎じ薬は、ただの「薬」ではありません。
それは、体と心に深く働きかける“養生の時間”でもあります
理由① 幅広い有効成分が体に深く作用する
- 生薬を水で煮出すことで、揮発性成分や水溶性成分など、幅広い薬効が抽出される。
- 加工されていない自然のままの生薬を使うため、複雑な相乗効果が期待できる。
- 体の奥深くまで届くような、じんわりとした作用が特徴。
理由② 慢性の不調や体質改善に適している
- 冷え、疲れやすさ、便秘、頭痛など、原因が複雑な慢性症状に対応しやすい。
- 体質や季節、生活習慣に合わせて処方を調整できるため、オーダーメイドの治療が可能。
- 一時的な対症療法ではなく、根本からの改善を目指す。
理由③ 煎じる時間そのものが“養生”になる
- 湯気に包まれながら薬を煎じる時間は、心を落ち着ける「セルフケア」のひととき。
- 五感を使って薬と向き合うことで、自然とのつながりを感じられる。
- 「煎じる」という行為が、すでに治療の一部であり、生活のリズムを整える力がある。
★まとめ
煎じ薬は、
「薬を飲む」から「薬と暮らす」への一歩。
体質改善を目指す方、慢性の不調に悩む方、
そして“養生”を大切にしたいすべての人におすすめです。
※煎じ薬とエキス剤の違い
エキス剤について
- 煎じ薬を煮出して濃縮・乾燥させた粉末状の漢方薬。
- 水やぬるま湯に溶かして服用するため、手軽で持ち運びにも便利。
- 成分の抽出は工場で行われるため、品質が安定している。
- 忙しい現代人や煎じる時間が取れない方に向いている。
煎じ薬について
- 生薬を自宅で煮出して服用する、伝統的な漢方薬の形。
- 揮発性成分や微量成分まで抽出できるため、薬効が深く広い。
- 処方の柔軟性が高く、体質や症状に合わせて細かく調整可能。
- 煎じる時間そのものが“養生”となり、心身を整える効果も期待できる。
☆まとめ
| 比較項目 | エキス剤 | 煎じ薬 |
| 手軽さ | ◎(即服用可) | △(煎じる手間あり) |
| 薬効の深さ | △(抽出成分に限りあり) | ◎(広範な成分が抽出可能) |
| 処方の柔軟性 | △(既製処方が中心) | ◎(個別調整が可能) |
| 養生効果 | △(服用のみ) | ◎(煎じる時間が養生になる) |
| 保存・携帯性 | ◎(粉末で持ち運び可) | △(液体で保存に注意) |
煎じ薬は「手間の中に癒しがある」薬。
エキス剤は「日常に取り入れやすい」薬。
それぞれの特徴を理解し、目的や生活スタイルに合わせて選ぶことが大切です。
※煎じ薬と五行・体質分類の関係
五行・体質分類とは?
五行学説は、自然界のすべてを「木・火・土・金・水」の五つの要素に分類し、それぞれが人体の五臓(肝・心・脾・肺・腎)と対応すると考える東洋医学の基本理論です。
| 五行 | 対応する臓器 | 季節 | 味 | 色 | 主な症状傾向 |
| 木 | 肝 | 春 | 酸味 | 緑 | イライラ、目の疲れ、頭痛 |
| 火 | 心 | 夏 | 苦味 | 赤 | 不眠、動悸、不安感 |
| 土 | 脾 | 梅雨・季節の変わり目 | 甘味 | 黄 | 食欲不振、疲労、便秘 |
| 金 | 肺 | 秋 | 辛味 | 白 | 咳、乾燥、肌荒れ |
| 水 | 腎 | 冬 | 鹹味(塩味) | 黒 | 冷え、腰痛、耳鳴り、老化傾向 |
〇煎じ薬との関係
煎じ薬は、生薬の組み合わせを通じて五臓のバランスを整えることができるため、五行・体質分類と非常に相性が良い治療法です。
〇具体的な関係性
体質に応じた処方
たとえば「肝(木)」が弱っている人には、気の巡りを良くする柴胡や香附子などを中心にした煎じ薬が処方されます。
季節に応じた調整
秋には「肺(金)」が弱りやすいため、潤いを補う麦門冬や百合などを使った煎じ薬が選ばれます。
味と色の対応
五行に対応する味や色を意識した生薬選びが可能。たとえば「腎(水)」には黒色の生薬(地黄、黒豆など)や鹹味のあるものが用いられます。
相生・相克のバランス調整
肝(木)が過剰で脾(土)を抑えている場合、脾を補う生薬(白朮、山薬など)を加えることで全体のバランスを整えることができます。
◎まとめ:煎じ薬は“動的な五行調整ツール”
煎じ薬は、五行の理論に基づいて「今のあなた」に合わせて処方を調整できる、非常に柔軟で深い治療法です。
体質・季節・感情・生活習慣など、複雑に絡み合う要素を読み解き、五臓のバランスを整えることで、根本からの改善を目指します。

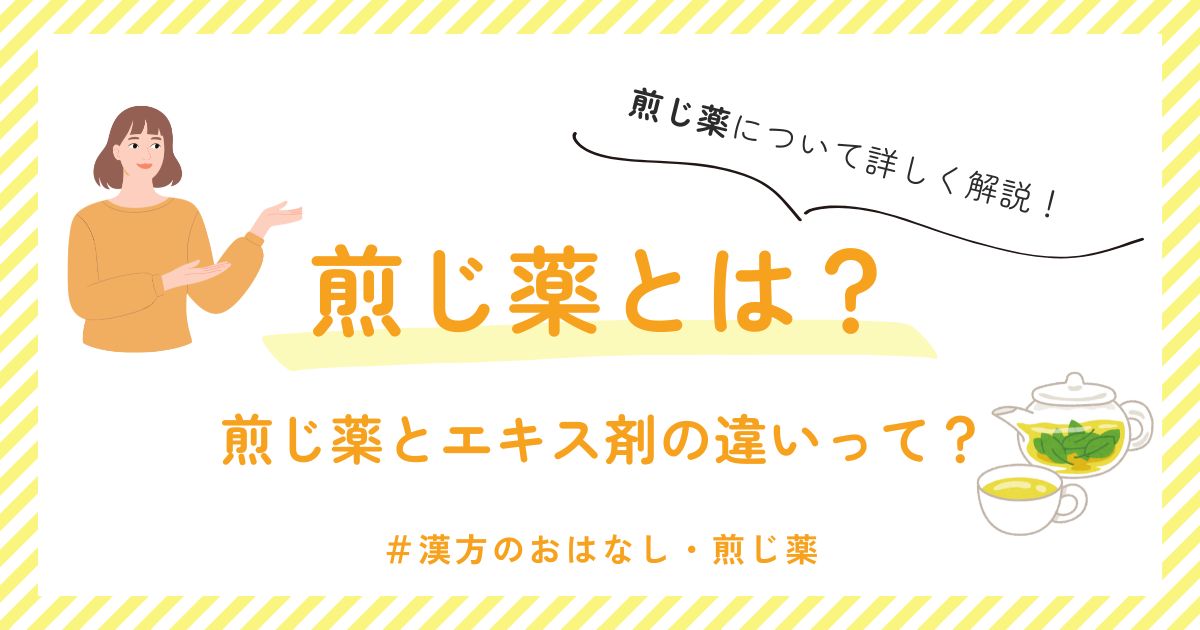
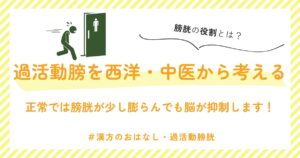
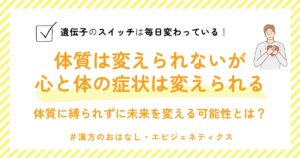
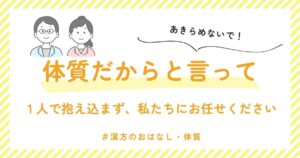
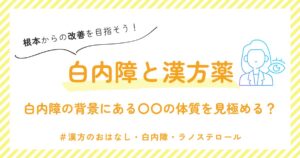
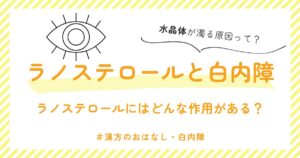
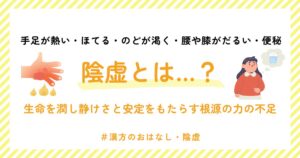
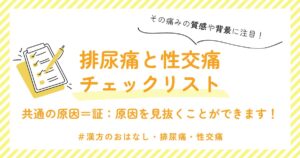
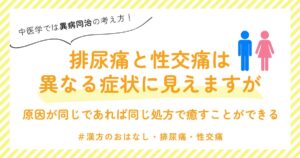
コメント