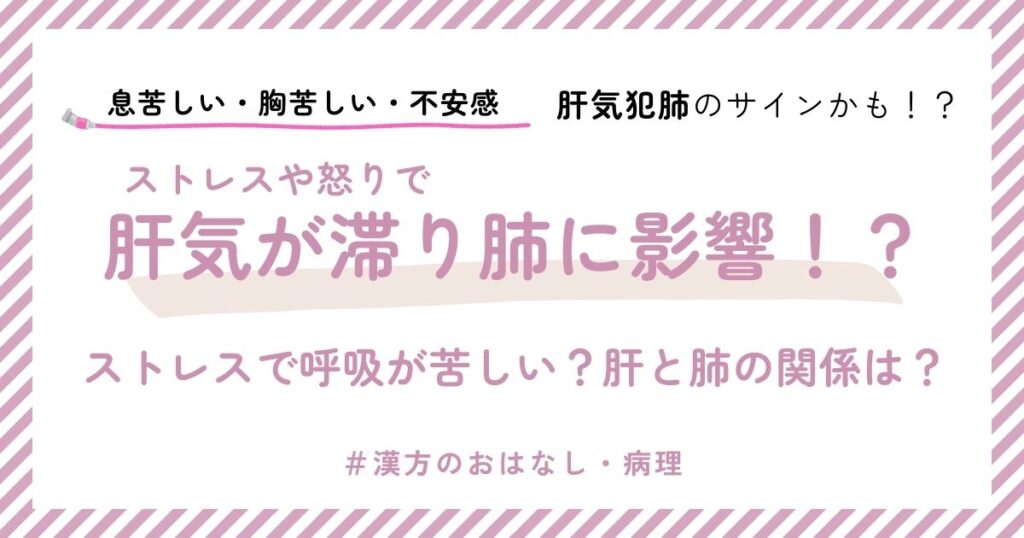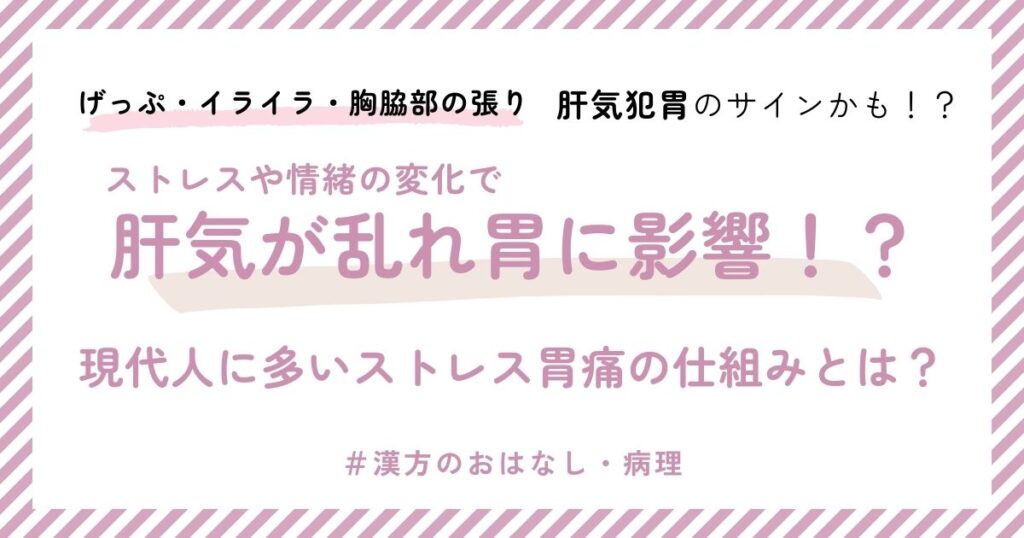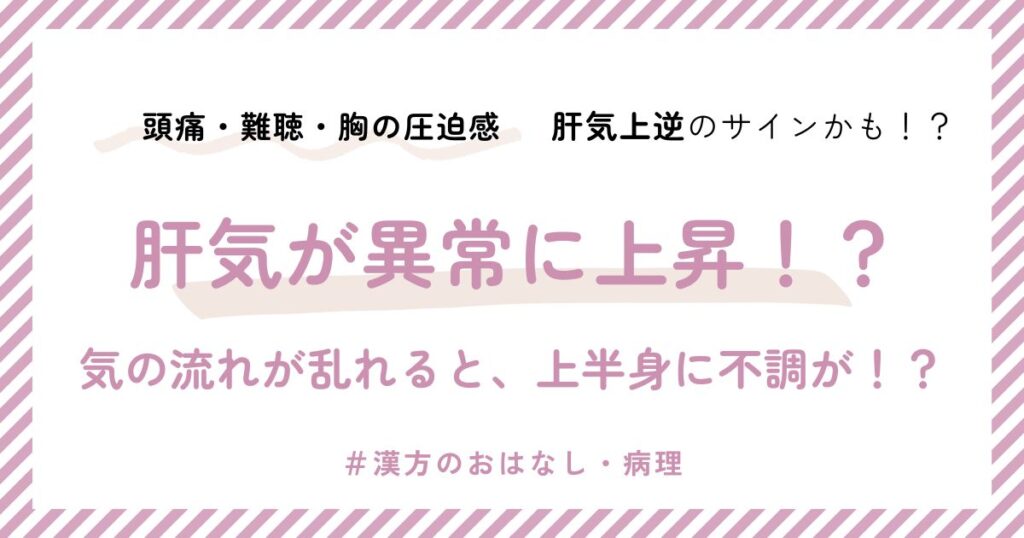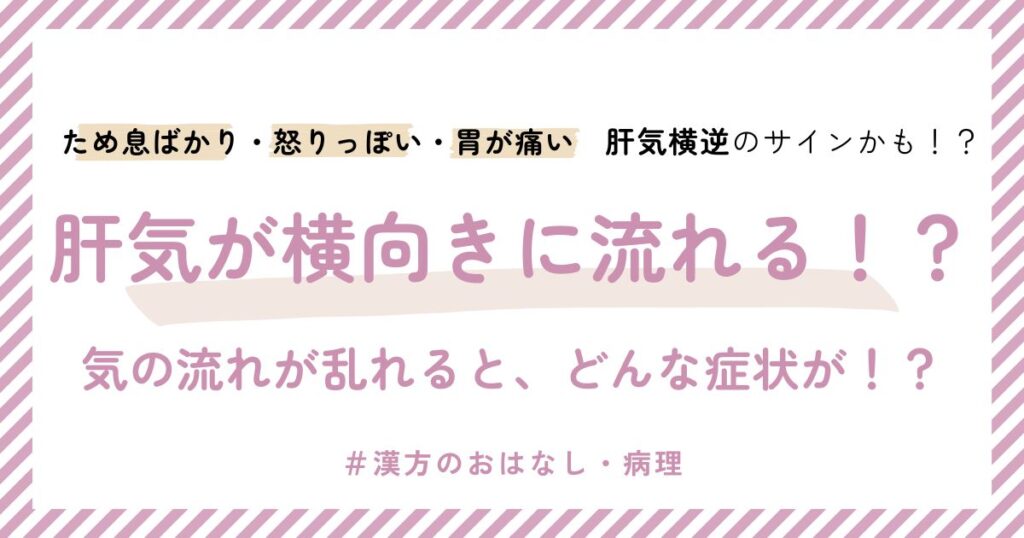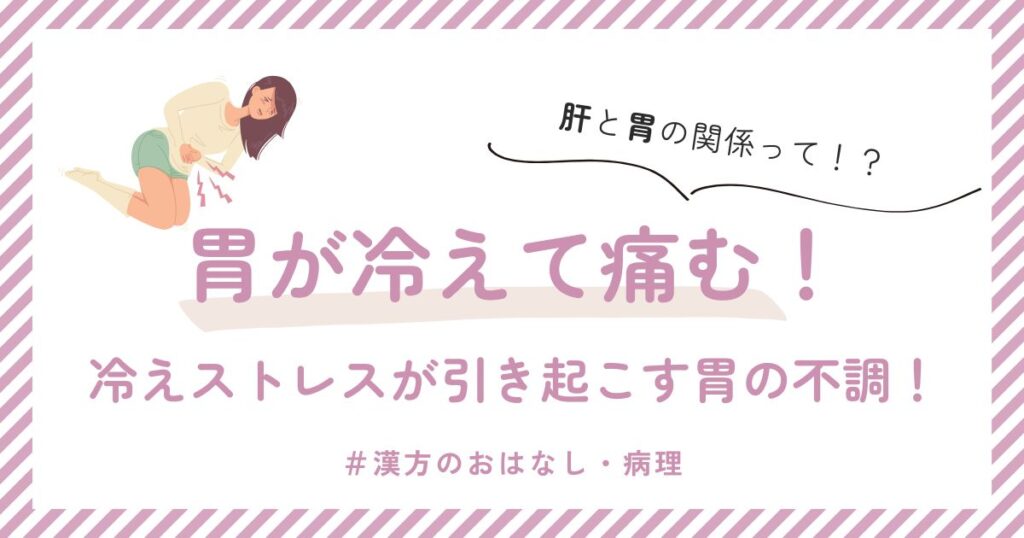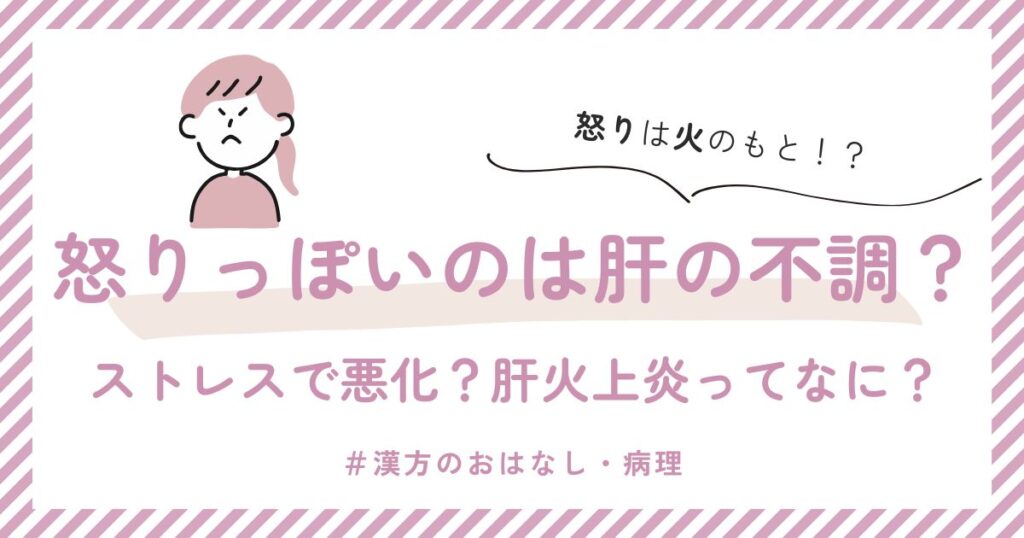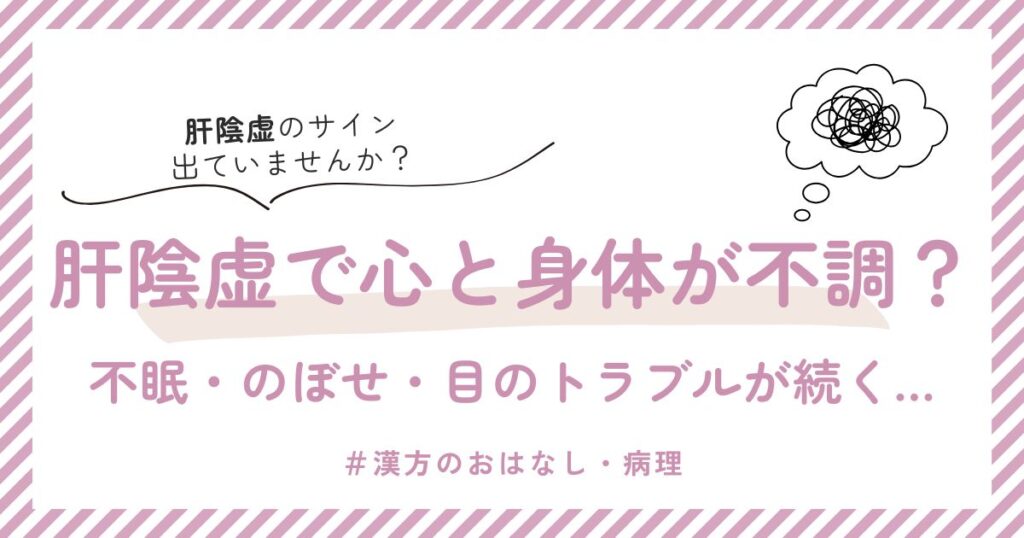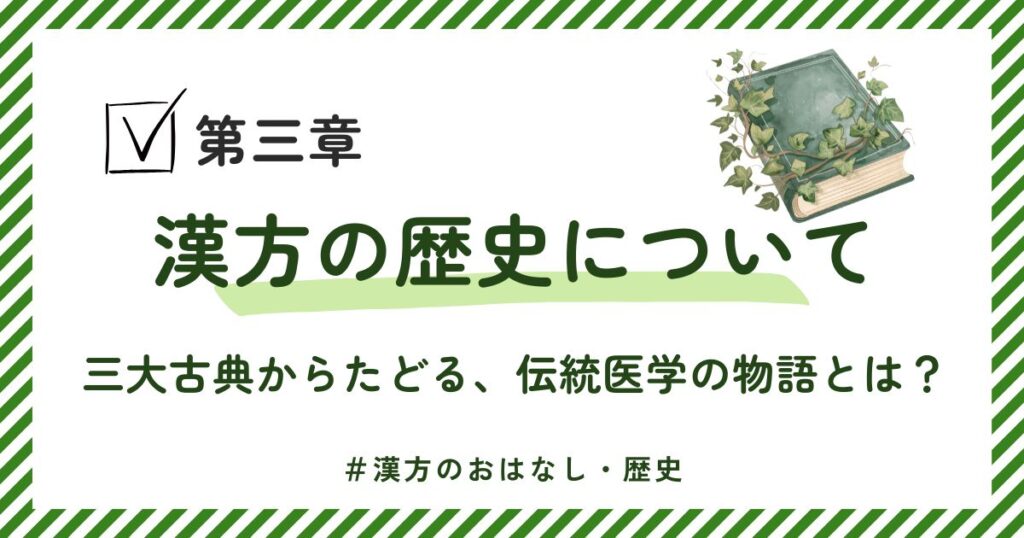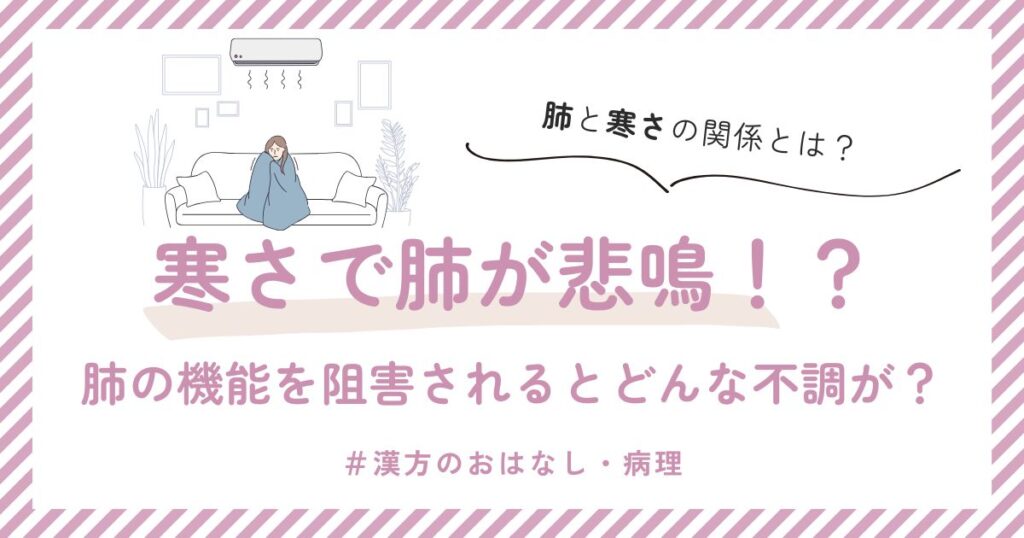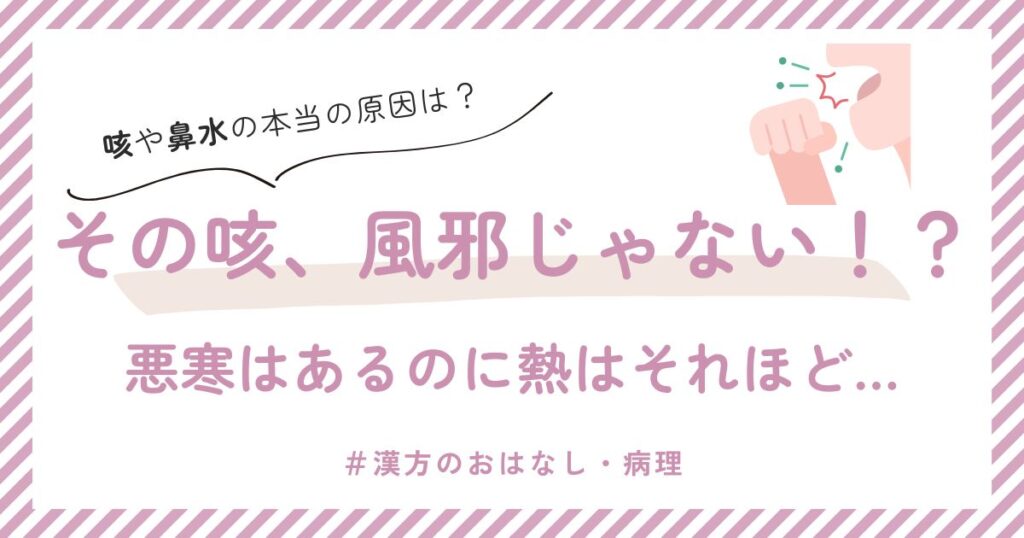中医学– category –
-

肝気犯肺(かんきはんはい)の病理
1. 肝気犯肺とは? ☑ 「肝気犯肺」とは、肝の気が鬱滞して肺を犯し、気の流れを乱すことで、呼吸器症状や精神症状を引き起こす病理状態。☑ 肝は「疏泄(... -

肝気犯胃(かんきはんい)の病理
1. 肝気犯胃とは? ☑ 肝の疏泄機能が失調し、気機が上逆して胃を犯す病態。☑ ストレスや情緒の変動が原因で、胃の消化機能が影響を受ける。☑ 主な... -

肝気上逆(かんきじょうぎゃく)の病理
1. 肝気上逆とは? ☑ 肝の気が過度に上昇し、頭部や上半身に異常な影響を及ぼす病理状態。☑ 「肝陽上亢」や「肝火上炎」へと発展しやすい。☑ スト... -

肝気横逆(かんきおうぎゃく)の病理
1. 肝気横逆とは? ☑ 肝の気が正常な上昇・疏泄作用を失い、異常な横向き(横逆)に流れる病理状態。☑ 特に「脾胃」や「肺」に影響を及ぼし、消化不良や... -

肝寒犯胃(かんかんはんい)の病理
1. 肝寒犯胃とは? ☑ 外寒(寒邪)や内寒(陽虚)が肝経を侵し、胃の機能を乱す病態。☑ 肝寒が胃に影響を与え、胃気が停滞して消化機能が低下。☑ ... -

肝火上炎(かんかじょうえん)の病理
1. 肝火上炎とは? 「肝火上炎」とは、肝の陽気が異常に高まり、「火」となって上昇し、頭部や顔面を中心に症状を引き起こす病理状態。☑ 肝は「疏泄(そせつ)... -

肝陰虚(かんいんきょ)の病理
肝の「陰液(血・津液)」が不足し、肝の機能(蔵血・疏泄)が低下する病証です。 1. 肝陰虚とは? 陰液が不足すると、肝の滋養作用が弱まり、筋・目・爪・皮膚・精神状... -

『漢方の歴史について』第三章
漢方の歴史について古代中国から遡っていくつかのシリーズで解説させていただこうと思います。 第三回目に古代中国において既に体系化されていた本草書のお話しです。 ... -

寒風束表が原因の肺失宣粛(はいしつせんしゅく)
寒風束表(かんぷうそくひょう)とは、寒邪(かんじゃ)と風邪(ふうじゃ)が体表を侵し、 肺の宣発(せんぱつ)・粛降(しゅくこう)機能を阻害する状態を指します。 ... -

寒邪犯肺が原因の肺失宣粛(はいしつせんしゅく)
寒邪犯肺(かんじゃはんはい) が原因の肺失宣粛( はいしつせんしゅく) 病理(病態)↓ 寒邪が肺を侵襲すると、肺の宣発・粛降機能が阻害され、 咳・喘鳴・息苦しさ・...